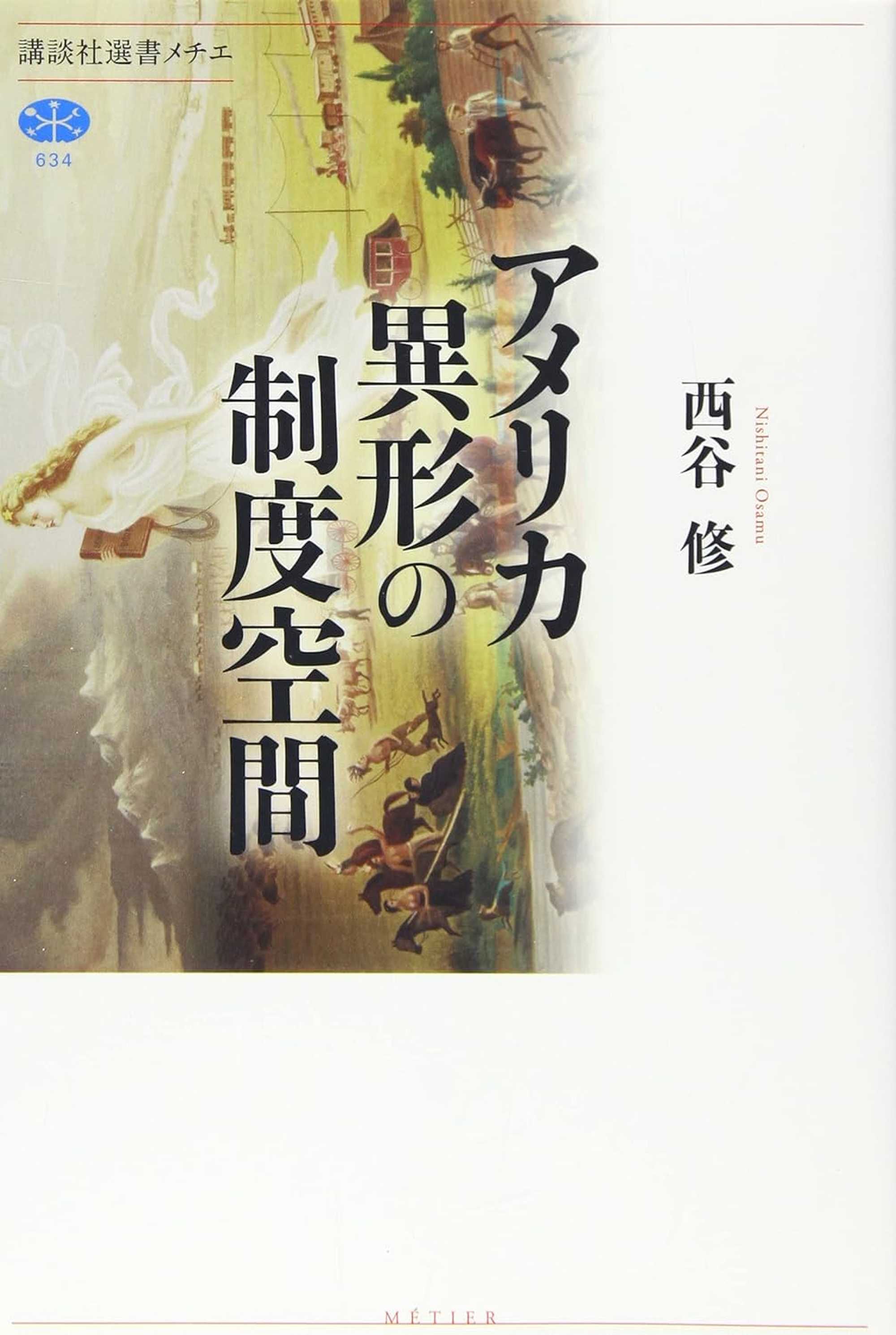その後ウクライナでは2014年に親ロ派(そういうのは便宜上である)政権を倒す「マイダン革命」が起こり、米有力政治家などの背後からの介入で成立した新政権は、東ウクライナで起こった抗議デモを民族派民兵に鎮圧させ(オデッサ労働会館放火虐殺など)、その状況を見てロシアがクリミア(フルシチョフの時代にソ連内でウクライナ帰属となったが、ソ連軍そして後にはロシア海軍の最重要拠点が置かれていた)を独立させ併合し、ドンバス地方の二共和国が独立宣言することになる。キーウの政権は民族派民兵をアゾフ大隊として国軍に統合し、それを派遣して東ウクライナは内戦状態に入る。
そこでドイツ、ベラルーシを加えて調停のための二度のミンスク合意が交わされるが、膠着したままの内戦状態は続く。その間、キーウ政権はロシア語を公用語から外し、EU加盟義務を憲法に書き込むなど、ロシアとの敵対姿勢を鮮明にしてきた。そしてNATOはウクライナを守ると称して北海や黒海で大規模な軍事演習を繰り広げる。
「第三の立場」はない?
2022年2月末、ロシア軍がウクライナに侵攻したのはそうしたかけ引きの果てである。するとたちまち「大国ロシアが隣国に侵略戦争をしかけ」、「独裁者プーチンが民主国家を侵略」と大々的な国際キャンペーンが始まった。もちろん、侵攻は国連憲章違反であり、国際法違反である。だからそれを批判し、ロシア軍の退却を求めるのはいいとしても、国家間抗争を仲裁するのは第三者でなければならない。ともかく、裁くのは第三者でなければならない。
ところがこのとき、国連のロシア非難、最初の制裁決議あたりはいいにしても、西側(米EU)諸国はロシアを「悪魔化」し、調停する代わりにロシアに強い経済制裁(たぶん歴史上最大規模)を課す一方で、ウクライナを全面支持する姿勢を打ち出した。ただし、直接派兵するとNATOの規約からして、NATO諸国がロシアと直接交戦しなければならないことになるため、それは避けながら、ありったけの兵器や情報その他の支援をウクライナにつぎ込むことになった。そして世界にその姿勢を共有させようとした。
つまりこの「戦争」に第三の立場はない。「ロシアを勝たせてはいけない」というのだ。ロシアが「勝つ」とは何をもっていうのか? ウクライナがロシアに併呑(へいどん)される? ともかく、ウクライナが「負ける」と、プーチンの野心は際限がなくなり(かつてのヒトラーのように)、つぎはバルト三国、そしてポーランド、さらにはヨーロッパ全体が侵略の危険に晒される、だからここで食い止めなければならない、と言うわけである。EU諸国はそう危機感を露わにして、ウクライナの軍事支援と後方支援に血道をあげた。
このとき、西側諸国(とそのメディア)は、第三の立場に立つことはすでにロシア(プーチン)の味方をすることだ、として中立であることさえ否定した。何のことはない、これは「テロとの戦争」以来のアメリカと西側先進国の戦争論理である。「敵につくか味方につくか、二つにひとつだ」(ブッシュ)というわけだ。つまりロシアは「テロ国家」であって、国際社会から締め出さなければ(できたら抹消しなければ、少なくとも独裁者プーチンは抹消しなければ)ならないのだ。ウクライナのゼレンスキー大統領がことあるごとにロシアの侵攻を「テロ行為」というのはそのためである。
公論・メディアの一方向性
両国の抗争であるなら、ソ連解体以降の両国関係の経過を見てみるのは当然のことである。だが、上に述べたような事情をもちだすと、「プーチンの肩をもつ」とか「ロシアの宣伝(フェイクニュース)を真に受けている」と指弾して、そうした言説を排除する。ひたすら「侵略戦争だ」、「独裁者プーチンの戦争」だから悪いに決まっていると切り捨てる。そんな風潮が西側世界の公論やメディアを染め上げ、マイダン革命のドキュメンタリーを作ったオリバー・ストーンはそれまでの業績に対する信用を失って排除され、リアリストとして一定の信望を得ていた米戦略理論家ジョン・ミアシャイマーももはや発言ができなくなり、ウクライナの事情に精通していたスイスの諜報専門家ジャック・ボーの論文も、「ロシア寄り」として流通から排除されるようになる(とくにSNSは自動検閲でこの手の情報を拡散させないようにしている)。
すると「エンベッド取材(記者が軍事行動を行う部隊と寝食を共にして行う取材)」をしてきたジャーナリストが「戦場の現場を見ろ」と興奮して「ロシアの肩をもつ」者たちに罵声を浴びせる。だが、戦争になったら現場が凄惨になるのはもはや自明のことである。核時代に戦場はますます非人間的になり、冷戦後、それが民族抗争として演出されるようになってからは相互憎悪で戦場は目も当てられなくなっている。そこで戦地の住民が、見えない兵器による攻撃や検証のしようもない情報戦のなかで翻弄されることも現代の戦争の特徴だ。それに今ではAIを使った兵器やドローンまでの新兵器が実戦で試されている。
だからこそ、戦争にしてはいけないし、ましてやどこの国でも政府は戦争が起こらないよう努めねばならないのだ。にもかかわらず政府は戦争を避けようとしない。それどころか権力を維持するために戦争を利用しようとさえする(ゼレンスキー政権も同じである)。
プーチンの「独裁」がそのままロシアの「悪」の根拠のように言われるが、ゼレンスキー政権のもとのウクライナの実情についてはほとんど語られない。ときおり、ロシア侵攻以前の財政破綻状況とか、軍関連の武器支援や徴兵に関する汚職とか、要人の更迭とか(最近では軍責任者のサルジニー将軍の更迭・イギリスへの「追放」)が漏れ出てくるだけである。しかし、「被害者」側であるウクライナについてそんなことを詮索するのは言語道断だと言うかのようだ。とにかく「ウクライナを負けさせてはいけない」と。
「平和会議」という戦争支援談合
ロシアの侵攻が始まり、最初のキーウ制圧がプーチンの算段を挫いて失敗し、戦線が「本来」のドンバス周辺に固まったころ、3月にトルコで始まりかけた停戦交渉は代表団の一人(後にキーウで二人)がロシアのスパイとして現場で処刑されて頓挫し、米EU諸国が大規模な武器支援を決定、5月にオースチン国防長官がこの戦争の目的を問われて「可能な限りロシアを弱体化すること」と答えてその意図を明かにして以来、西側(とくに日本)では戦況報道は米ネオコンのシンクタンクと英軍機関の出す情報に依存していて、まともな情報はほとんど広められない。
ロシアの侵攻が始まって2年余り、西側の「支援疲れ」が取り沙汰され、それが何とか克服されて東部戦線での膠着が続く中、2024年6月のイタリアでのG7会議の後、スイスでゼレンスキー大統領を招いて「平和会議」が開かれた。そこでは向こう十年のウクライナ軍事支援の計画が作られたという。ロシアと交渉する話はまったく出ず(「テロリストとは交渉しない」がテロとの戦争の原則だ)、向こう十年、西側諸国はウクライナに戦争を続けさせようというのだ。