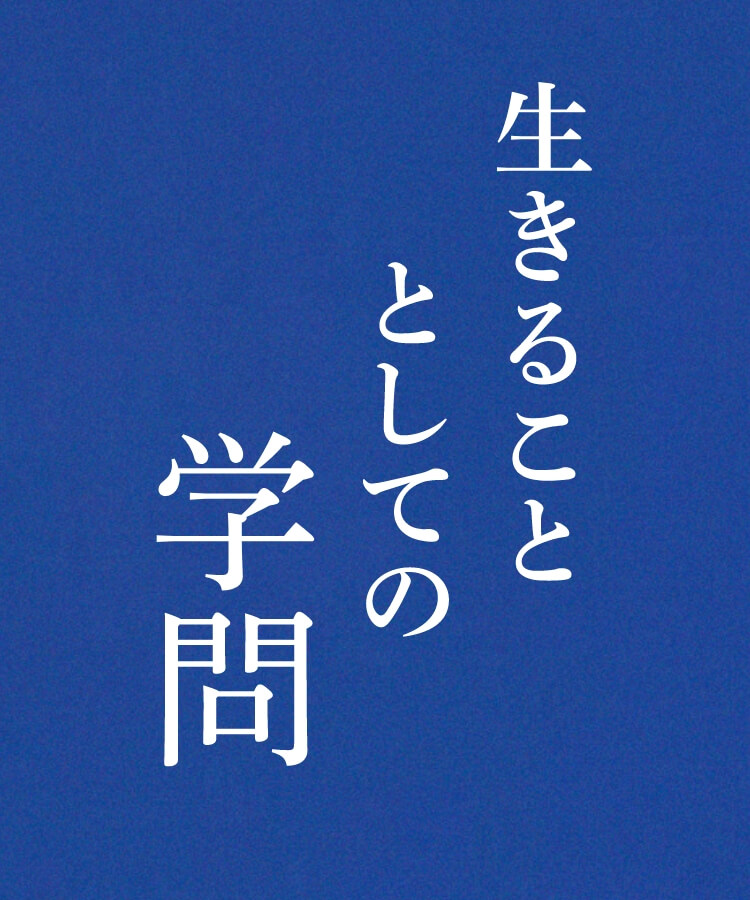
「トイビト」とは、ご想像の通り「問う人」という意味です。ただしこれは、問う人とそうでない人がいると言いたいわけではありません。夕陽はなぜ赤いのか、鳥はなぜ飛べるのか、人は死んだらどうなるのか、他人の心を知ることはできるか、自分は何のために生きているのか……。物心ついてからこうした問いを一度も抱いたことがないという人は、おそらくいないでしょう。現代人のすべてがホモ・サピエンス(=賢い人)であるのと同じように、われわれはだれもが問う人である。それが、この名前の意味するところです。
われわれがこのような存在であると教えてくれるのは、やはり子どもたちの姿です。地べたにしゃがみこんでアリの行列を見つめたり、車の窓越しにどこまでもついてくる月を眺める彼・彼女らのなかには、たとえ言葉にはなっていなくても、大きな「?」が浮かんでいることでしょう。しかし、こうした経験やそれをもたらす感性(ありていに言えば好奇心)は、多くの場合、年齢を重ねるごとに漸減していくように思えます。
生きていくためには社会や組織のしくみを知り、そこで役立つ知識・技術を身につけなければならない。大人になるとはそういうことで、アリだの月だのにいつまでも構っていられないのは当然だ、と言われるかもしれません。しかし、そのように「成長」した大人たちの多くが一様に疲れ、その目から輝きが失われて見えるのは、きっと私だけではないはずです。人が社会で生きていくのは確かですが、既存のシステムにただ取り込まれ、現状を追認して(問うことを忘れて)日々数字を追いかけることが、本当に、大人になるということなのでしょうか。
私は、こうした事態の背景には、学問の世界と社会の分断(今やほぼ断絶)があると思っています。研究者でもなんでもない素人が言うのは気が引けますが、学問の本質とは未知のものやことを追い求めるのと同時に、これまで常識とされてきたものに疑いの目を向け、新たな見方や考え方、解釈の可能性を探っていくことだと思います。そこには絶対的な正解もゴールもありません。ある研究は次の研究に(批判的に)引き継がれ、乗り越えられていく定めにあるのです。
これに対して大多数の人が経験する学問(それを学問と呼ぶのであれば)には、明確な正解がありゴールがあります。受験勉強にせよ、資格や就職のためのものにせよ、そこで求められるのは事前に決められた答えに辿り着くテクニックであり、答えそのものに疑問をさしはさむことではありません。言うなればこれは、「合格」や「内定」という目的と対になった「手段としての学問」です。それが無意味だとは言いませんが、こうした理解があまりにも一般的になった結果、学問そのものが道具だとみなされ、ほとんどの人にとっては学校に行っている間だけやる(やらされる)ものになってしまったのではないかと思うのです。
では、一般社会に生きる私たちにとって、そうではない学問とはなんでしょうか。私は「生きることとしての学問」を提案したいと思います。何かのためにするのではなく、食事や睡眠と同じように、それ自体が日々の営みのひとつであるような学問を考えてみたいのです。
「学問」という言葉は「問うことを学ぶ」と読めます。これを踏まえるなら、「生きることとしての学問」はわれわれに、日常的に問うことを要請するでしょう。当然それは「正解」を暗記したり、権力者やAIの指示通りに動くよりもはるかにめんどくさい生き方です。「コスパ」も「タイパ」も悪いどころか、そもそも何が得られるのか(得られるのかどうか)さえわかりません。しかし、いえ、だからこそそこには自由があり、自分を世界を変えていく無限の可能性があります。そしてそれこそが、われわれが本来そうである「問う人」の生き方ではないかと思うのです。
マックス・ヴェーバーは『職業としての学問』のなかでトルストイの言葉を引用し、学問が、「われわれがなにをなすべきかやどう生きるかについてなにごとも答えない」ことを「争う余地のない事実である」と認めています(尾高邦雄訳、岩波文庫、42-43頁)。しかし学問するということ、事象と向き合い、真摯に問い、自らの認識を不断に更新しつづけていくことは、(ヴェーバーが生きた時代と同じく)混迷を極める現代において、われわれが生きていく指針のひとつになりうるのではないでしょうか。
そんな思い(込み)をもとに、「トイビト」というサイトは運営されています。といってもここは、人生いかに生くべきかを明らめんとする求道の場というわけではありません。学問に興味のある人ならだれでも出入りできる、自由な知の公園です。覚えなければいけない年号や、取るべき単位などはもちろんありません。と同時に、実生活ですぐに役立つ情報(ラクをして稼ぐ方法とか、人に好かれるテクニックとか)が得られることもまずないでしょう(保証します)。それでもよければ、またいつでも散歩にいらしてください。この場所からひとつでも多くの問いが生まれることを願っています。
トイビト 加藤哲彦