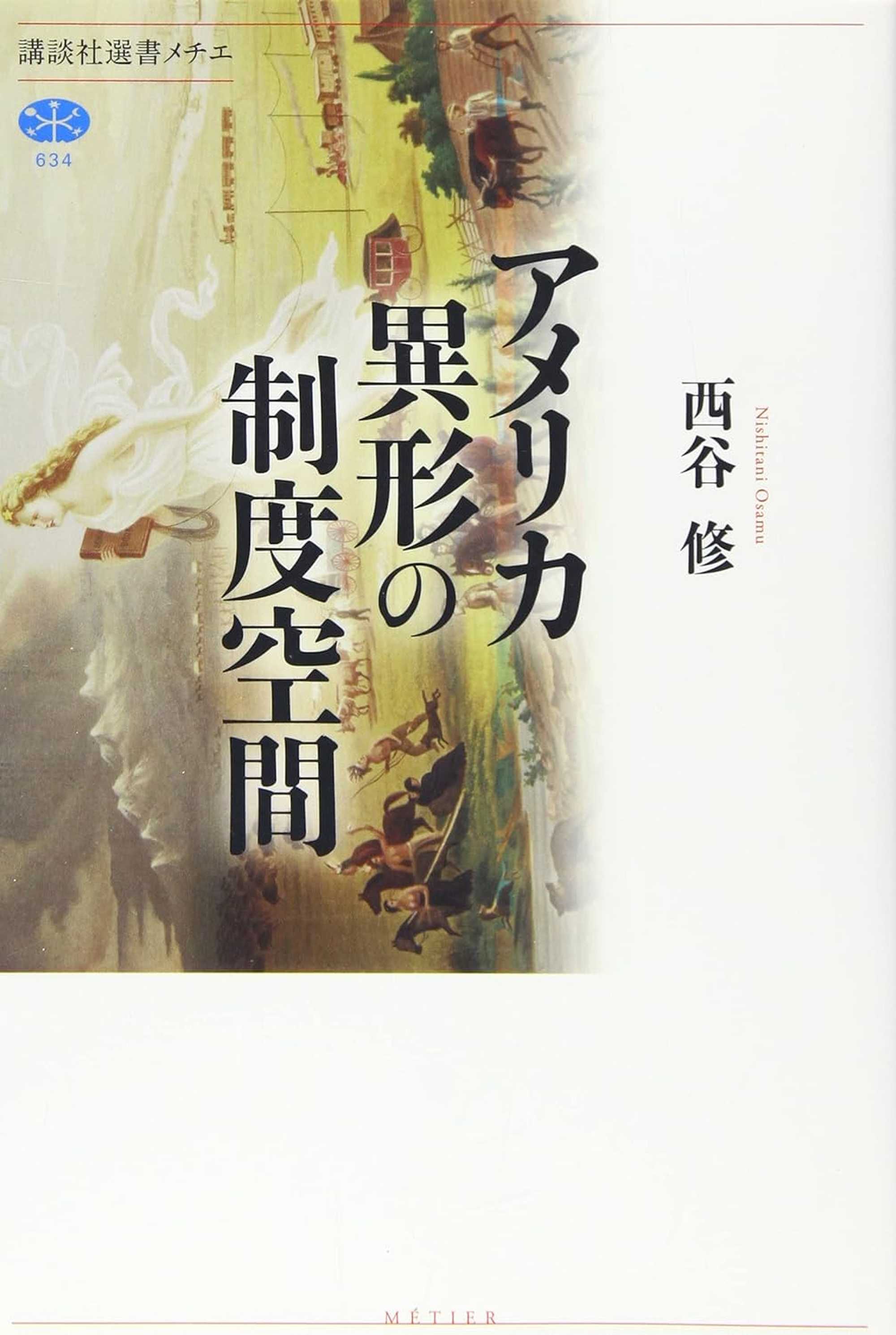「西側=オクシデント」の再浮上
東西の冷戦が終わって四半世紀が経ち、「テロとの戦争」も後景に退いたとされる昨今、「西側」という用語がふたたび随所で顔を出すのはなぜなのだろうか?
中国やロシアが台頭して東西の冷戦構造が再来している、というのはだれが言うのか。ソ連崩壊後のロシアの「復興」や、グローバル経済下での中国の「成長」が、どうして世界にとっての危険なのか。もちろん経済成長や発展には軍事力が伴う。だがそれは相互的なものだ。両国の台頭が「危険」だというのは、端的に言ってアメリカにとって「危険」だというに過ぎない。あるいは、アメリカと利害を共有する西洋先進国、つまりは「西側」にとってであり、世界全体にとってはむしろ恩恵でさえある。
中国もロシアも、冷戦後、グローバル市場経済に参入することで成長してきた(ロシアは「ショックドクトリン」の適用で壊された社会がそれなりに回復)。それは世界経済全体の拡大を推し進めることになり(労働力と資源、市場の供給)、とくに中国経済の「成長」にその後の世界(アメリカも含めて)経済は大いに依存してきたはずだ。だが、中国がグローバル経済推進の主要なアクターとなると、たちまち「西側」は警戒する。そこには「自由と民主主義がない」というのだ。
「自由」でないから貿易も「不正」だとされ、たとえば対米関係では、輸出がアメリカにとって過重になると、それを「不正」だとして関税を倍増するなど経済制裁を課されることになる。IT産業が発展すると、中国会社の重役をカナダ出張中に逮捕したりする。当然それが米中関係を悪化させる。そしてこの経済関係は軍事的関係ともつねに連動している。
ヨーロッパ諸国は、冷戦後、中国やロシアとの関係を拡大することで、それまで閉じられていた新たな「成長」を展望できるはずだった(もちろん、中国経済の浸透がイタリアに見られたような闇市場の無秩序化を深めたりもしたが、それは関係そのものがオープンでないことの副次効果でもある――2008年のR・サヴィアーノのベストセラー小説『ゴモラ』に描かれたような)。フランスやドイツは一時中国との関係拡大に動き始めた。EUのその他の国々もそうだ。だがそれはアメリカに牽制される。中国は独裁的(専制主義)でかつ貿易不正の国だという。その批判をイギリスが後押しし(香港・新疆ウィグル自治区の「弾圧」)、仏独は鎹(かすがい)で引き止められたようにアメリカの対中圧力にしたがって中国と距離をとる。
「この道しかない」
イギリスのサッチャーは1980年代に「この道しかない」という有名な断言で自国の「社会的なもの」の解体を推し進めたが、それはどこに通じる「道」なのかといえば、言うまでもなくイギリスが大英帝国時代以来築いた繁栄を保つこと、ひいては西洋諸国(あるいは北大西洋に結ばれた英米二国)が歴史的に獲得した地位をそのまま保持して世界での優位を保つ「道」ということだ。
その内実は「規制緩和、民営化、小さな政府」と要約されるいわゆる新自由主義路線である。経済的な「自由」とは、富を持つ者が、政治的・国際的制約を受けずに、更なる富を獲得・集積・運営する「自由」である。かつてはそれは帝国権力と結びついた世界統治の原理だった。グローバル化によって変わったのは、その「自由」を主張する権利主体が、ナショナルな政治主体ではなくその枠を超えた私的主体(多国籍企業)になったということだ。
いまや中国はGDPでアメリカを凌駕するのも目前といわれている(2010年頃イギリスのシンクタンクがそれを発表した)。それが米英にとってもっとも危惧される事態だ。だから米英は「この道」を確保するために、中国やロシアを「法と秩序」に従わない「悪しき国家」として世界(国際社会)から分断し、できることならその「体制転換(民主化)」を促したい。1972年の米中国交正常化があったにもかかわらず(「一つの中国」を認めているにもかかわらず)、東アジアで「台湾危機」(中国の台湾侵攻危機)が醸成され、旧ソ連の基盤国家のひとつだったウクライナが、ロシアと西側諸国の係争地になったことにはそのような背景がある。
ここでは踏み込まないが、二十世紀の境目に起こった義和団の乱とその後に交わされた北京議定書(清による日本も含めた西洋諸国に対する租界・諸利権の割譲)以来、この百二十年間の西洋(=西側諸国)と中国との関係を大まかにでも振り返ってみれば、西側諸国は幾重ものごまかしを重ねないと中国を「政治的道義的」に非難することなどできないだろう。ましてやイデオロギー的に非難するなど、まさにイデオロギー的詐欺行為だと言わざるをえない(米中国交正常化で中国の正統性をアメリカは承認したはずなのに、その後もアメリカは一貫して――冷戦後は「民主化要求」を掲げて――「中国敵視」を止めたことがない)。
ロシアのウクライナ侵攻の前段階
ウクライナはと言えば、グルジア出身のスターリン以後、ソ連共産党を率いたフルシチョフも、その後を継いで長いソ連の停滞時代に君臨したブレジネフも、共にウクライナの出身だった。ソ連時代のウクライナには(当時の国境画定の関係で)ロシア系の住民が多く、二人とも東ウクライナから出てモスクワの中央権力の座に就いた人物だった(いわゆるウクライナ民族主義者が多いのはリビウを中心とした西部だった)。
ソ連の最末期、その大統領だったゴルバチョフを追い落とすべく、エリツィン(当時のロシア大統領)はロシア・ベラルーシ・ウクライナに呼びかけて独立国家共同体を結成し、それがソ連を最終的な崩壊に追いやることになった(1991年)。そのとき、つまりウクライナやロシアの独立期、両国の関係はそのようなものだったのである。
その後ウクライナには多数の北米(主にカナダ)移民からの支援や民主化運動が入り、また冷戦崩壊後の「民族原理」復活によって西ウクライナの民族主義勢力が伸張し、それがウクライナに分断を生み出すことになり、この国は親西側派と対ロシア関係維持派との間で引き裂かれることになる。そこに2008年、当時のアメリカのブッシュ大統領が、ウクライナとグルジアをNATOに加盟させる方針を打ち出したのである。冷戦解消時の黙契を無視して東方拡大してきたこの西側軍事同盟は、このときロシアが対象であることを公然と表明することになった。ロシアのプーチン大統領が西側との協調を最終的に断念して大ロシア主義に転じるのはこのときである。