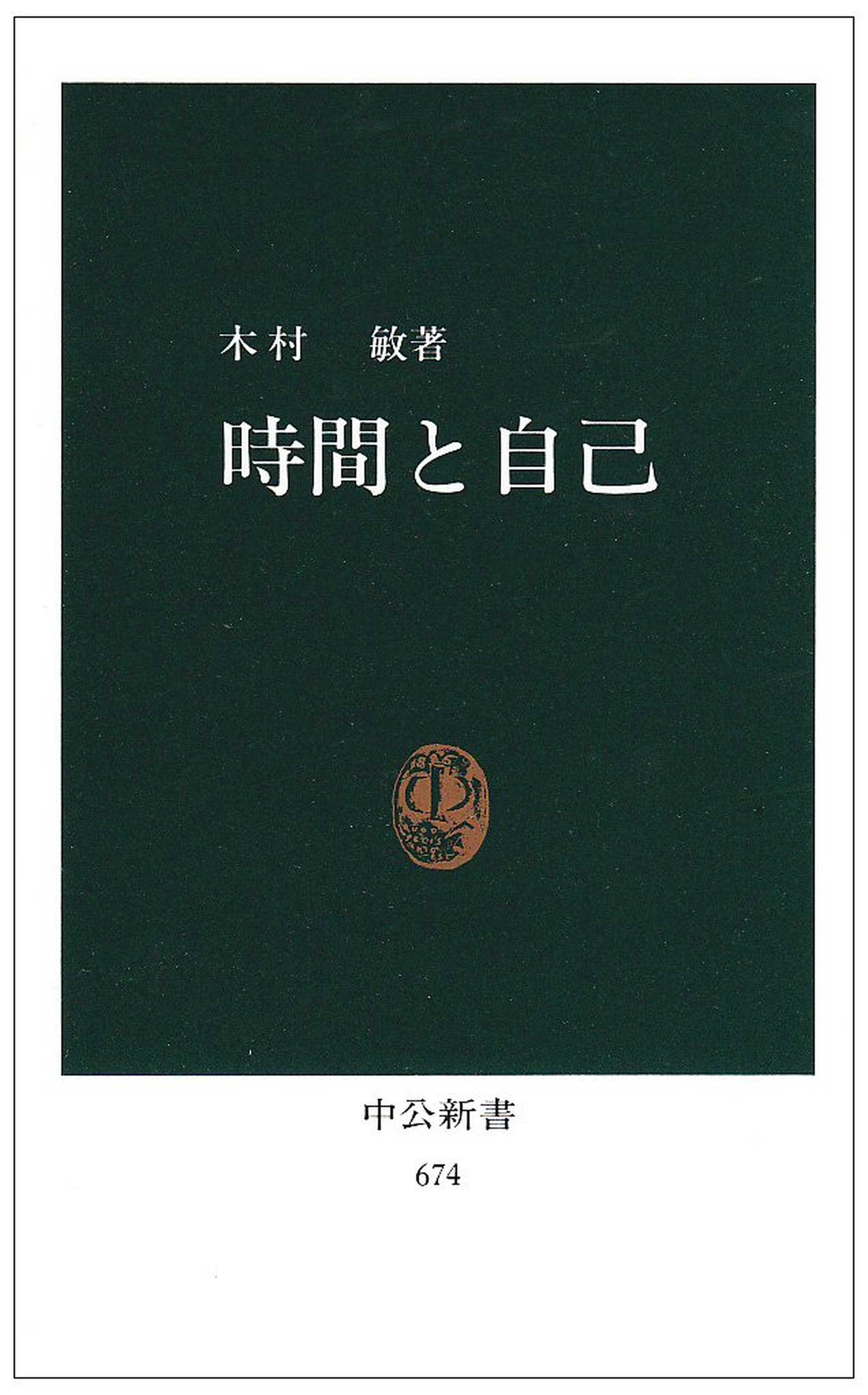人称代名詞を使わない日本語
「こと」という語のこうした不可思議なあり方と、もしかしたら関係があるかもしれない日本語の性質を、最後に指摘しましょう。
まずは、蓮實重彦の次のような体験談を引用したいと思います。フランス人の母親と蓮實とのあいだに生まれた、日本語とフランス語を話すバイリンガルの息子さんと、父親の蓮實との夕食時の会話です。
彼が五歳の誕生日を迎えてまもなくのことだったが、たまたま妻が外出していたので子供と二人で向かいあって夕食のテーブルについていた折に、不意に、子供が父親に対して「あなた」と呼びかけた瞬間である。たしか、「あなた、まだ、ごはんたべる?」といった疑問文の形式であったと思うが、これにはいささかの衝撃をおぼえたことを告白せねばならぬ。その証拠には、父親は、無意識のうちにその問いにフランス語で答えていたのであり、それを契機に、食事が終るまで、二人の会話はフランス語で続けられたのを憶えている。(『反=日本語論』蓮實重彦、ちくま学芸文庫、125頁)
日本語を母語とする者にとって、父親に対して「あなた」という呼びかけをするのは、ひじょうに特殊な場合だけでしょう。おそらく私は、去年亡くなった父親に対して、「あなた」という呼びかけをしたことは、生涯一度もありません。われわれは、通常の日本語の会話で、父親や母親を「あなた」とはけっして呼ばない。それどころか、親以外の場合でも、「あなた」や「君」などという二人称の代名詞を使う機会は、日本語の場合は、とても少ないのではないでしょうか。
すくなくとも私は、ある特殊な距離感のある相手に対して、ある特別な機会ででもないかぎり、「あなた」あるいは「君」とは呼びかけません。たとえば、ここ一年間を振り返っても、もしかしたら私は、一度も「あなた」や「君」という二人称の代名詞を使っていないかもしれません。しかも、余計な情報かもしれませんが、私は、それほど寡黙な人間ではありません。
ところが、フランス語だけではなく、インド=ヨーロッパ語に属する言語であれば、「あなた」という語は、日常会話では必須であり、誰もが誰に対しても日ごろから使っているのです。だからこそ蓮實重彦は、「衝撃をおぼえた」のです。このとんでもない違いは、どこからきているのでしょうか。
あるいは、蓮實は、つぎのような指摘もしています。
言語学者バンヴェニストは断言する。フランス語の人称代名詞の体系にあって、Nousは、いささかもJeの複数形ではありはしない、というのである。「ぼくたち」は「ぼく」の複数ではない。(中略)フランス語の「ぼくたち」Nousとは、「ぼく」の数倍化されたものではなく、この「ぼく」と「ぼく」ならざる他の人称の集合からなりたっていて、その構成要素相互のあいだには「排他的関係」が成立しているのだ。すなわち、「ぼくたち」Nousが主語となった場合には、「ぼく」Jeが、「きみ」Tuと「きみたち」Vous、「彼(または彼女)」Ilと「彼ら」Ilsに対して「優位」な地位を占める、ということである。(130-131頁)
これもかなり衝撃的な事実です。日本語で「われわれ」や「ぼくたち」あるいは「わたしたち」といえば、どこにもそれぞれは区別のない複数の「われ」や「ぼく」や「わたし」の集合(「ぼく」の数倍化)だと考えるでしょう。日本語で、「われわれ」といったときに、「われ」が最初に厳然とあって、その「われ」以外の他の人たち、とは絶対に考えません。こうした一人称複数である「ぼくたち」の特徴(「ぼく」と「ぼく」ならざる他の人称の集合)も、フランス語のみならず、インド=ヨーロッパ語族が有している特徴なのだとすれば、やはり、日本語を母語とする者にとっては、重く受けとめざるをえない違いだと言えるでしょう。
木村敏も、『人と人との間』(弘文堂)でつぎのように書いています。
西洋各国語は、それぞれただ一つの一人称代名詞しか持っていない。自分自身を代表させる代名詞は英語ではアイ、ドイツ語ではイッヒ、フランス語ではジュに限られている。しかもこれらの一人称代名詞は、特殊な場合以外にはけっして省略されることがないし、かりに省略されたとしても、それに属する動詞や助動詞の人称変化によって、人称代名詞は潜在的にはつねに表現されている。(133~134頁)
ヨーロッパ語では、一人称と二人称は、けっして省略されることはありません。「けっして」!省略されない。それに対して、日本語は、どうでしょう。先ほど言ったように、私などは、ここ一年間、「あなた」「きみ」を使った記憶は、まったくありません。それに対して、一人称の方は、こういった文章で書くこともありますし、もしかしたら日常会話でも、何か特別な場で、何度か使ったことがあるかもしれません。でも、「何度か」だと思います。自分のことを「私」などという場が、頻繁にあるような生活は、すくなくとも私はしていません。それに私は、「ぼく」という一人称が嫌いなので、あるときからけっして使っていません。(これは、余計な情報です)
こうしたヨーロッパ語と日本語との違いは、いったいどういうことでしょうか。
木村敏は、一人称について、いま引用した文章の直後で、つぎのように言います。
これに対して日本語においては、僕、おれ、おのれ、わし、おいら、てまえ、自分、わたし、わたくし、あたし、うち等々、一人称代名詞のかなりの使用頻度の高いものだけでも十指に余る。しかも、これらの代名詞は、日常の自然な会話においてはむしろ省略されることの方が多いし、省略された場合にこれに代って会話の主体を明示しうるような動詞、助動詞の人称変化も存在しない。(134頁)
さらに二人称についても、ヨーロッパ語と比較して、つぎのように言います。
これに対して、日本語の二人称代名詞は、一人称代名詞と同様に数も多く、また自然な日常会話においては、一人称よりもさらに省略されがちである。そもそも、先に述べたように、日本人は一般に二人称代名詞を使いたがらない傾向があり、これは特に目上の相手に対して著しい。(135頁)
このような日常使っている言語の根源的な違い、そして、おそらくその言語で、われわれが思考もしているのであれば、西洋語で書かれた文章を、日本語を母語とする者が読むということが、どのようなことを意味するのか、茫然としてしまいます。何もかも、最初の一歩から根本的に異なっているのかもしれない。西洋語と日本語の間には、けっして越えられない底なしの深淵があるのかもしれない、と思ってしまうからです。
この連載の最初で書いた「理性」という語のわかりにくさといったものも、こういう深淵にかかわっているのかもしれません。レヴィナスのいう「絶対的他者」という概念のわかりにくさそのものが、もしかしたら、レヴィナスのつかうフランス語と私の母語である日本語の根源的な違いに、その原因があるのかもしれません。つまり、そもそも「絶対的他者」などという概念がでてくる(われわれにとっての)「絶対的他者」的土壌は、われわれ日本語を母語とする者にとっては、絶対に理解できないのでは、といったようなことです。
ここから、三上章や湯川恭敏の「主語廃止論」につなげて、最後に西田幾多郎の「絶対無の場所」に強引に戻って大団円などと考えていたのですが、さすがに力尽きました。今回の連載は、このくらいで終わりにした方がいいのかもしれません。いま言ったような道を突き進むには、もっともっと準備が必要だからです。
実は、最近、大学の私の研究室の永久凍土のような書籍群を整理していたら、20年前の自分の文章にであいました。何と、そのタイトルは、「「主語廃止論」と「絶対無の場所」」(『中央評論』243、2003年)というものでした。20年前に考えていたことを、いまもまた同じように(ほとんど進歩なく?)考えているということなのでしょうか。そうなのかもしれませんし、もしかしたら、すこしは進歩しているのかもしれません。それは、誰にもわからない。
いずれにせよ、この問題には、再び挑戦したいと思っています。