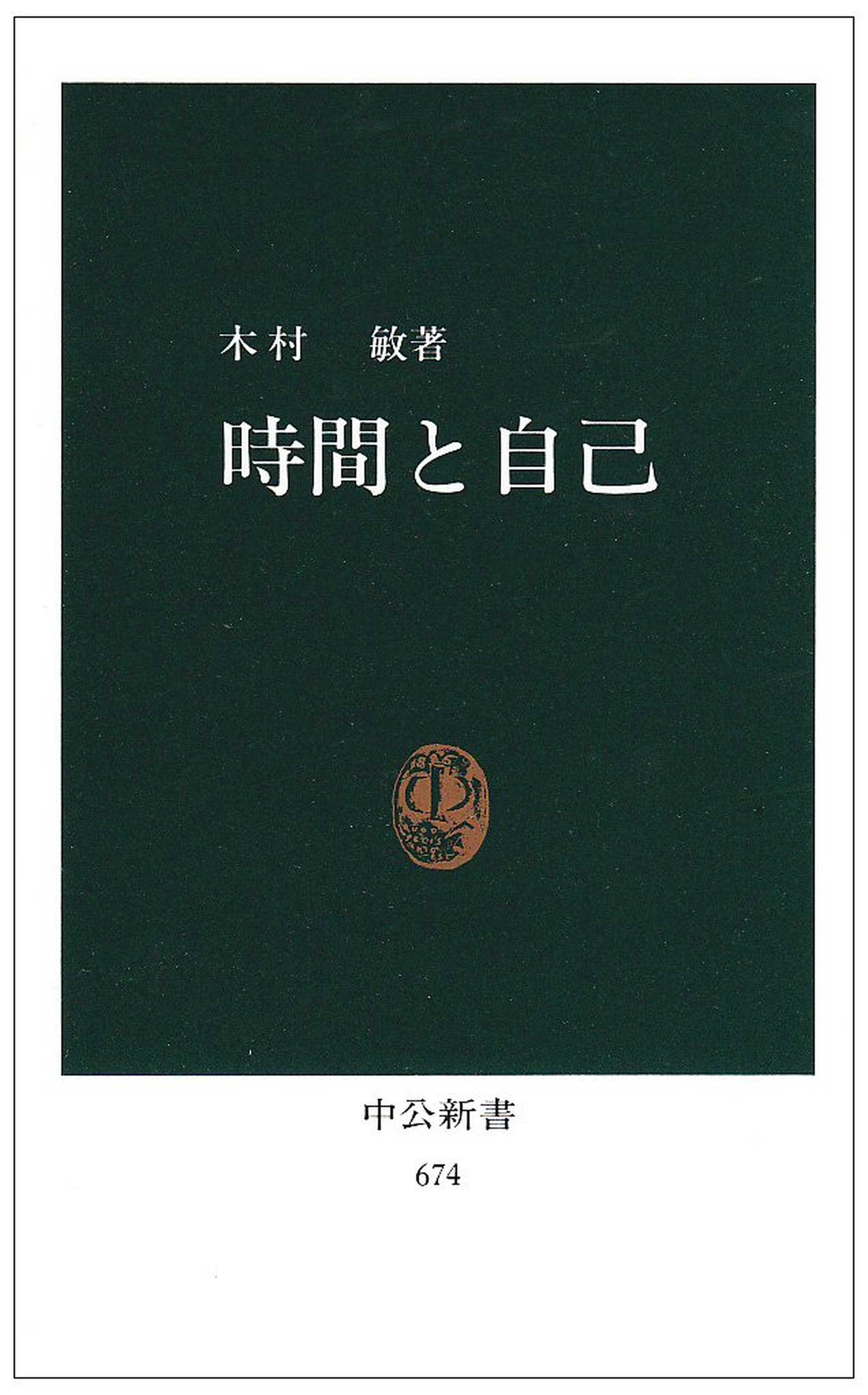さて、ここまで、「もの」と「こと」について考えてきましたが、最後に木村敏の「もの」と「こと」についての考察を見てお終いにしたいと思います。木村敏という人は、本当にすごい人で、私のような哲学をやっている人間から見ると、二つの点で、大きな足跡を残した人だと思います。
一つは、哲学の問題が、実は、人間の生に深くかかわっていることを、離人症の症状や統合失調症や鬱病や癲癇になった人たちのあり方から明らかにしたという点です。「存在」や「時間」や「自己」といった哲学の中心問題が、たんなる思弁によるものではなく、われわれの現実の存在そのものに本質的に食い込んでいることをはっきり示したのです。木村敏のおかげで、日本の哲学は、かなり豊饒で底知れず深いものになったと私は思います。ハイデガーや西田幾多郎が考えていた問題が、たんに頭で考えられただけのものではなく、われわれの存在そのものの根幹にかかわるものだった、ということがわかったわけですから。
もう一つは、今回のテーマでもある日本語で哲学をしたという点です。『時間と自己』や『人と人との間』における議論は、まさに日本語の特徴に焦点を当て、ヨーロッパ語の翻訳ではない(しかし、同時にヨーロッパ語も視野に入れた)、われわれが普段使っている言葉を使って、哲学の問題をじっくり考えていくという姿勢が貫かれました。これもまた、稀有なことだと思います。
視覚的な「もの」、聴覚的な「こと」
それでは改めて、木村敏の「もの」と「こと」という語についての見方を確認していきましょう。まずは、「もの」について、つぎのようにいいます。
外部空間のものとは、見るというはたらきの対象となるようなもののことである。(中略)外部的な眼で見るにしても内部的な眼で見るにしても、見るというはたらきが可能であるためには、ものとのあいだに距離がなければならない。見られるものとは或る距離をおかれて眼の前にあるもののことである。それが「対象」あるいは「客観」ということばの意味である。(『時間と自己』中公新書、5~6頁)
ここで言われている「もの」は、もっとも素朴な「もの」と考えていいでしょう。「物」と書くことができるような「もの」です。この「もの」は、われわれからは距離があり、それを視覚的にとらえることができる対象のことだと言えるでしょう。ただこの視覚による対象というのは、眼球を使って見ることができる物体を意味するものであると同時に、「内部的な眼で見る」ことができる対象(観念や想像)も意味しています。観察者や認識する者と距離のある対象ということになります。
そして、その対象は、われわれから距離があると同時に、固体的なもの(観念や想像で言えば、特定できるもの)でもある、ということになるでしょう。それが「対象」になるためには、流動的であったり、はっきりと指定できないものであったりしては困るからです。したがって、対象になるというのは、眼球で視覚的にとらえることができたり、内部的な眼で見ることができたりするものということなのです。つまり、「もの」という語と視覚とは、密接に関係していると言えるでしょう。
木村も次のように言います。
ものが眼の前に示されるものであり、眼で見られるものであるということは、外部空間に位置を占める可視的な物体について言われうるだけではない。個々の三角形として可視的なものとなる以前の、三角形のイデアのようなものも、肉眼によってではないにしても、なんらかの意味で見られるものであることに変りはない。(同書、15頁)
こうした視覚と切りはなせない「もの」に対して、「こと」は、どういう特徴をもっているのでしょうか。木村は、つぎのように説明します。
私がここにいるということ、私の前に机や原稿用紙があるということ、いま私がその上に字を書いているということ、私がもう長らく時間という問題について考えているということ、これらはすべてものではなくてことである。(中略)ことは、どうしてももののように客観的に固定することができない。色も形も大きさもないし、第一、場所を指定してやることができない。(8頁)
「もの」は、客観化でき固定化される対象であるのに対して、「こと」の方は、場所を指定することができず、客観的に固定することができないものということになるでしょう。そして、これは、前回の最後に引用した長谷川のつぎのような文章にも対応していると言えるかもしれません。
本当のところは、「もの」も「こと」も、どちらも「時間的」なのである。ただ、「こと」が時の到来し出現する、その「つぎつぎになりゆく」側面に目を向けているのに対して、「もの」は、出で来ったものが過ぎ去ってゆく、その後姿を眺めやっている。(『日本語の哲学へ』232頁)
たしかにここで長谷川は、同じ「時間的」なものの二つの様相といっていますが、明かにそのあり方は、「こと」の方が、いわゆる時間的なあり方(「つぎつぎになりゆく」側面)であるのに対して、「もの」の方は、時間的とはいっても、固定化される方向性(過ぎ去ってゆく、その後姿)をもつものといえるでしょう。
木村は、この「こと」のもつ時間的な側面を強調するために、「ことば」(事=言)のはたらきを「こと」に結びつけ、それをさらに聴覚という事態に結びつけることによって、「もの」とのちがいをより鮮明にします。つぎのように言います。
「この花は赤い」ということばを用いなかったならば、この花は赤いということを表現したり伝達したりすることは不可能である。ものはその実物を眼の前に示すことによって確認を求めることができるだろう。これに反して、ことは目に見えるように呈示することができない。ことはことばによって語り、それを聞くことによって理解する以外ないのである。(『時間と自己』14~15頁)
われわれは、「こと」という透明な箱で、この世界を切りとり、自分なりの「こと」を成立させます。もちろん、その「こと」は、この世界のあり方をそのまま掬い取ろうとしています。つまり、この世界の生成消滅しているあり方、「つぎつぎになりゆく」あり方、一刻も同じ状態であることはなく有機的に流動し持続しているあり方をありのままの形で写しとるために、「こと」という語を使っているわけです。
このような「こと」のあり方を、「もの」のあり方(視覚的なあり方)と比較して、木村は、つぎのように言います。
ものを見るというはたらきが一定の距離をおいてはじめて成立するのに対して、聞くということは―—肉声を聞く場合でも心の声を聞く場合でも―—私たち自身の間近で生起する。私たちは聞えてくる声に対して、いかなる距離をとることもできない。声は、私たち自身から限りなく近いところで聞かれる。さきにわれわれは、ものが客観の側にあるのに対してことは主観の側に、あるいは客観と主観のあいだにある、という言いかたをした。ことがなんらかの声として聞かれるのであるからには、この「あいだ」はそれ自身、限りなく自己に近いところに、自己それ自体と区別のつかぬような場所としてあるのに違いない。(同書、16頁)
視覚というのは、こちら側(見る主体)とは距離のあるものを対象として捉えるはたらきです。それに対して、聴覚は、聞こえる音(あるいはメロディー)に対して、こちら側(聞く主体)は、距離をとることはできません。音というのは、どんな音でも、じかに聞こえるのです。そして、音の流れ、メロディーは、途切れることなく「つぎつぎになりゆく」あり方で、聞いている主体のいる場所をじかに貫いて有機的に流れていきます。
つまり、図式的に言えば、「もの」は、視覚的な静止画のなかにある固定された対象であるのに対して、「こと」は、動的な聴覚印象の流れそのものだということができるでしょう。ベルクソン的な言い方をすれば、「もの」は、「空間」のなかの対象であり、「こと」は、「持続」(真の時間)そのものだということになります。
でも、もちろん、「こと」も「ことば」であるかぎり、固定的な語であり、リアルな流動とは、まるで異なっています。どれほど「こと」という語が、空っぽの箱であり、固定化される前の状態を表していると言っても、それが、あくまでも「ことば」であるかぎり、この試み(流動そのものの把捉)は成功しません。「こと」という語で切りとったとたんに、もともとは、気体的な空っぽの枠組だったもの(「こと」)が、言語の世界にからめとられ、どんどん「もの」の方に移行していって、対象となり固定化されてしまうからです。
木村も次のように説明します。
純粋のことの状態は発生期の元素のように不安定であって、すぐにもの的な対象として安定しようとする傾向をそなえている。「ある」ということはすぐ「存在」というもの的な姿をとりたがるし、「速い」ということは「速さ」というものとしてわれわれの意識の中で安定を見出そうとする。元来、われわれの意識はものを見出すためにあるのであって、意識によって見出されるかぎり、どのようなことでもすべてもの的な姿をおびることになるのだ、といってもよいだろう。(20頁)
そろそろ「もの」と「こと」についての話を終わりにしたいと思います。結論らしい結論は、でていませんが、しかし、やはり驚くべきことは、「こと」という語は、「ことば」でありながら、その「ことば」のもつ性質(「物質的で固体的なあり方」)とは根本から異なる事柄を示しているように思われることです。そういう「こと」という語を、日本語がもっているというのは、驚くべきことだと思います。しかも、「ことば」の「言」という同じ音だというのも、とても意味深く思われます。