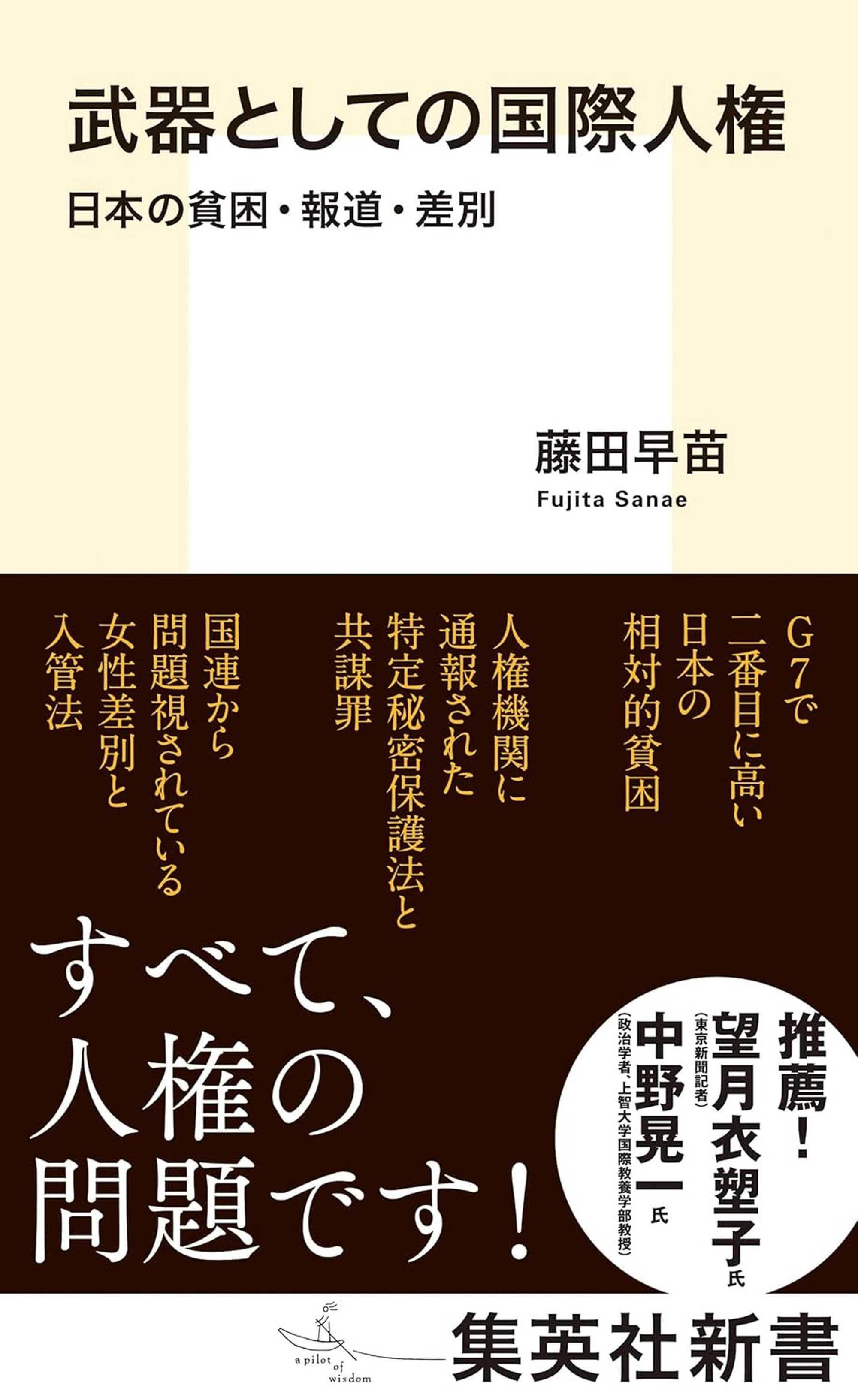メディアには、「権力の監視」のほかに、「声なき人の声を顕在化させる」という役割もあります。イギリスでは貧困問題や障害者の問題がよくメディアに取りあげられます。たとえば2018年に障害者権利条約の審査で出された勧告が実施されていない、と国内人権委員会が調査報告すると、BBCはそれを受けて特集を組み、政府に責任説明を迫りました。また、2023年には、駅の有人窓口を廃止して機械化する計画が発表されると、障害をもつ当事者がレポートし、「移動の自由を妨げる」と訴える動画がゴールデンタイムのニュースで流されています。
日本のメディアも人権問題を取りあげてはいますが、放っておけば埋もれてしまう弱い立場の人の声は十分に取り上げられていない感じです。
2023年7月に厚労省が発表した調査によると、日本の貧困率はアメリカと韓国に抜かれ、先進国で最悪となりました。それが国内にも海外にも見えにくいのは、メディアがそこに眼を向けていないことが大きな原因だと思います。
メディアは権力と市民の真ん中ではなく、市民、とりわけ弱者の側に立つべき、という点を認識していないと、日本政府にとってますます都合のいいことになってしまいます。
「電気」を使えるようにするために
ここまで取りあげてきた問題のほかにも、日本には数多くの人権問題が存在しています。その一つ一つに取り組みながら、早急に日本の人権状況全体を改善する仕組みづくりが必要です。具体的に言えば、先述した国内人権機関の設立と、「個人通報制度」を使えるようにすることです。
個人通報制度とは、人権侵害の訴えを国内の裁判所の最終判決で退けられたとき、個人が直接国連に救済を求められる制度です。この制度は人権条約本体の締約とは別の条約に批准して初めて使えるものですが、日本はこの条約に批准していません。欧州人権裁判所のような地域人権機関も同様の手続きを設けており、それらを含めると、先進国の中で個人通報制度が使えないのは日本だけで、これも国連で問題視され、再三勧告を受けています。
国内人権機関がなく、個人通報制度も使えない日本の状況は、本来、人権状況の向上のために利用できるはずのツールが極めて限定されています。まるで、世界中の大半の人が電気を利用して生活しているのに、日本だけがロウソクで暮らしているように私には思えます。
日本国内レベルで人権状況を改善するためには、裁判所を通した解決を目指す「司法アプローチ」と、政策によって人権の促進や擁護を促す「政策アプローチ」の2つが重要です。韓国では、通常各省庁の役人だけで構成される政府代表団に国会議員を加え、国連からの勧告の実施を促進しています。日本が即座に同様の取り組みを行うことは難しいと思いますが、2014年の自由権規約の日本報告書審査に野党議員が傍聴者として参加したように、同様のことがもっと行われるべきだと思います。
私が所属しているエセックス大学には2012年から、毎年一人か二人の日本人弁護士が国際人権法を学ぶために留学してきます。日本の司法試験では、国際人権法を含む国際公法を選択する受験者が少ないため、裁判官も弁護士も国際人権法をほとんど学んでいません。そのためエセックス大学ヒューマン・ライツ・センターと日弁連で協定を結び、留学を実現させたのです。
私はジュネーブで開催される国連人権機関の会議を2000年から傍聴し、2013年からは日本の人権問題を情報提供しています。2024年にはDV被害や共同親権、選択的夫婦別姓問題を訴える当事者や、彼女たちをサポートする弁護士とチームを組んで参加し、日本政府への勧告につなげました。
アカデミズムの役割
国際人権基準を国内で実施するためには、私たち研究者の役割や責任も大きいはずです。実際、机上の研究だけでなく、いま現在社会で起きている問題に直接関わる研究者たちに何人も出会ってきました。恩師であるエセックス大学のポール・ハント教授もその一人で、彼は自分を含め国連人権機関で委員などを務める友人たちを「アカデミック・アクティビスト」と呼んでいます。
日本にも人権問題の専門家が大勢いて、国際人権法学会という学会もありますが、アカデミック・アクティビストと呼べる研究者は極めて稀です。アカデミズムはアクティビズムと距離を取らなければいけない、と信じられているようです。特定秘密保護法の通報がなされたり、女性差別撤廃条約の勧告がなされた直後の国際人権学会で、それらの問題に触れることすらなかったのには驚きました。2023年、同学会でプレゼンテーションの機会を得たので、「もっと現実を見よう!」と訴えましたが、今後少しずつでも日本のアカデミック・アクティビストが増えていくことを願っています。
人権に関して日本の隅々に「電気」が灯るまでにはまだ時間がかかりますが、日々の生活のなかで私たちひとり一人にできることはあります。尊厳、平等、差別、透明性、説明責任などについて、「人権」という視点を通して見つめ直してみることです。そして、これらの問題について身近な人と話したり、できればSNS等で発信してみてください。
世界人権宣言の起草に重要な役割を果たしたエレノア・ルーズベルトは「普遍的な人権は、ごく小さな場所、世界のどんな地図でも見つけられないほど身近で小さな場所から始まるのです」という言葉を残しました。もしそれが本当なら、この国の人権状況を変えられるのは国会議事堂や内閣府、最高裁判所だけではありません。あなたが通っている学校や職場、家庭、町内、あるいは日々利用している電車やバスの中も、その場所なのです。
構成:浅野恵子