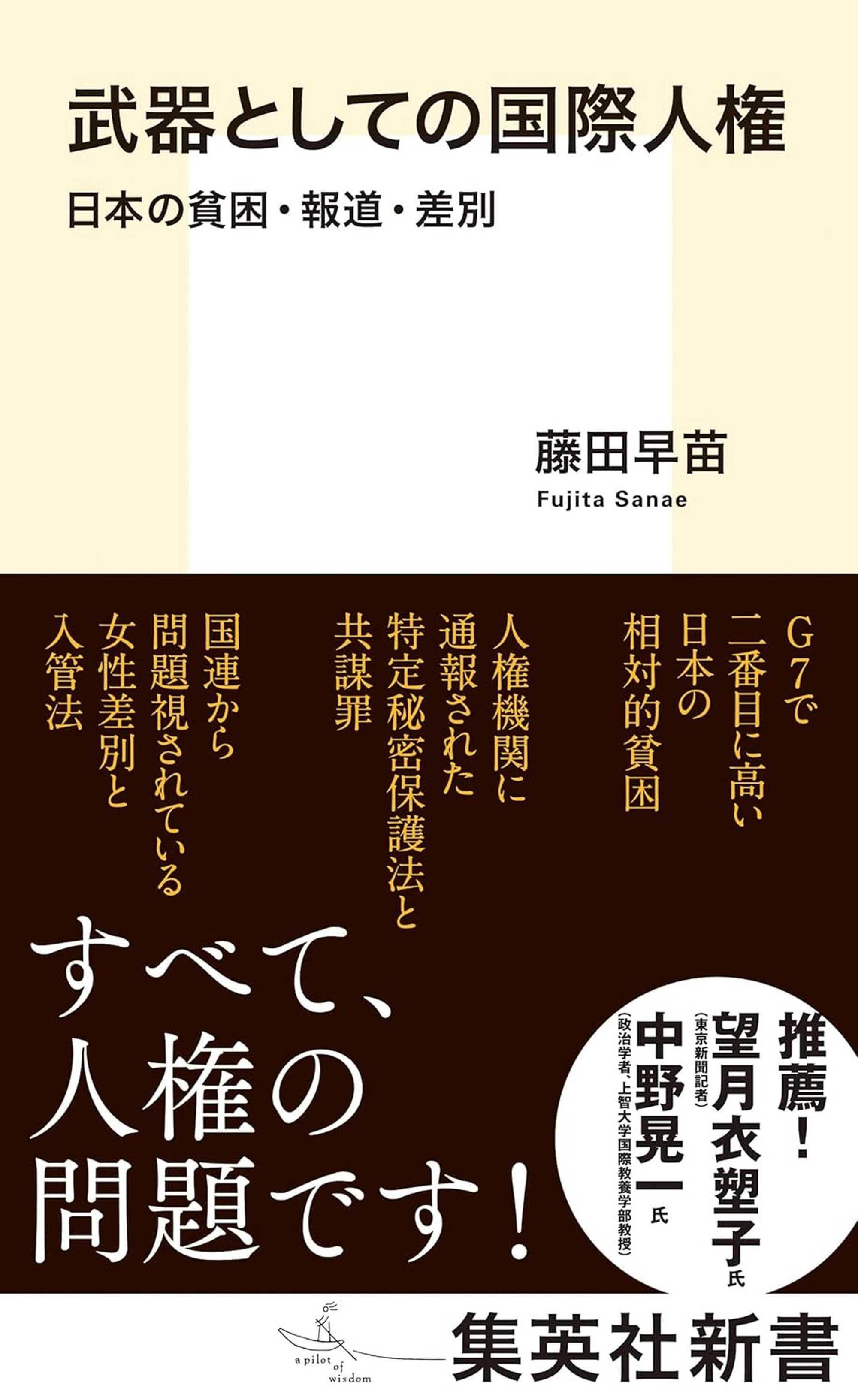こうした態度をとる人権条約締約国は極めて稀で、大半の国は特別報告者からの懸念や勧告を真摯に受け止め、改善に努めています。一つ例を示すと、2018年に先住民族女性に対する差別的な国内法の改正を求められたカナダ政府は、翌年にそれを反映した法改正を行いました。
勧告数で見れば、日本は2017年の審査で217の勧告を受け、145件を受け入れたものの、34件は受け入れ拒否、その他は留意などとしました。この年、韓国には218の勧告がなされましたが、「受け入れ」と「留意」の2通りで回答し、「拒否」は1件もしていません。このことだけを見ても、日本の受け入れ拒否の多さが際立ちます。
自らにとって耳の痛いことを忠告してくれる友人を英語で「クリティカル・フレンド」と言いますが、特別報告者はまさに過ちを正してくれる貴重な友人です。たとえば万引きをくり返している友人に「それは犯罪だからやめるべきだ」と手紙を送るのがクリティカル・フレンド(特別報告者)だとすれば、「そんな手紙に法的拘束力はない」と無視しているのが日本政府と言えます。世界の多くの国はクリティカル・フレンドの言葉を正面から受けて、建設的な対話をしながら改正に努めているのです。
最近知ったことですが、イギリスは特別報告者からの調査訪問の要請をすべて受け入れています。イギリスにも様々な人権問題はありますが、少なくともクリティカル・フレンドからの提言を受け止め、対話を尽くし、改正すべき点を探っているのです。対して日本は残念ながら大事な指摘を受け止める姿勢も、対話をする準備もしていないと言わざるを得ません。
権力に弱腰な日本メディア
特別報告者に対する日本政府の態度は人権理事会でも問題視されていますが、多くの日本人はそのことを知りません。何故なら日本のメディアは自国政府の発表だけを何の検証も批判もなしに、そのまま報じているだけだからです。
情報の自由は民主主義の土台です。国連はそのことを、早くから強調してきました。1946年の第1回国連総会において、「情報の自由は基本的人権であり(中略)、国連が擁護するすべての自由の試金石である」と語られています。
ところが、民主主義国家であるはずの日本のメディアは「圧力に抵抗する力が弱い」と特別報告者に指摘されているのです。メディアの役割は、英語でパブリック・ウォッチドッグ(監視犬)と言われます。権力が暴走するのを監視し、問題点を調査し、一般に知らしめるのがメディアの役割です。
選挙報道を例にとると、イギリスでは有権者の投票行動に必要な情報を伝えることに重きが置かれ、テレビ各局は首相や各党首のインタビュー番組を組みます。2024年7月の総選挙では、約6週間の選挙戦中、ジャーナリストは手加減なしに各政党の政策について耳の痛い質問を投げかけていました。
一方日本のメディアは、各政党や候補者の政策を詳細に伝えることには消極的で、投票後に一早く当選情報を報せることに時間と労力を費やしているようです。2014年11月には、政権与党・自民党から「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」と題された文書が各報道機関に送られました。これを受けて、各メディアは選挙報道自体を縮小してしまったのです。ジャーナリズムの倫理において公平性は重要ですが、「何が公平か」の判断は、政府ではなく独立した機関が行うべきものです。この点も特別報告者から指摘され、政府に公平の基準を決める権限を与えている放送法の改定を勧告されています。
ちなみに、欧米の学生たちに、政権与党がこうした文書をメディアに送ることはあり得るかと聞いたところ、どの国の学生も「あり得ない」との答えでした。万が一同じことが自国で起きたら、「政府からの圧力ととらえメディアは結束して対抗するだろう」というのが欧米の学生たちの見解です。
この「結束」も日本のメディアに欠けている要素の一つです。欧米のジャーナリストはたとえ組織に属していたとしても、基本は個人のジャーナリストであり、圧力がかかると結束して闘います。対して日本のジャーナリストは概して報道機関の一社員であり、上層部の指令や社の方針から離れた言動をすることはほぼありません。
「中立性」と「独立性」という観点で言えば、メディアに必要なのは前者よりも後者です。このことも日本ではあまり理解されていません――だからこそ政府からの「お願い」に当のメディアがあっさり屈してしまうのでしょう――。日本の大学の講義でボードに横線を引き、左端にA(権力側)、右端にC(市民側)、真ん中にBとだけ記し、メディアはどこに位置するべきかと問うと、どの大学でも八割の学生が「B」と答えます。このことが示すように、日本では一般に中立性や「公平かどうか」がメディアを判断する基準になっているようです。