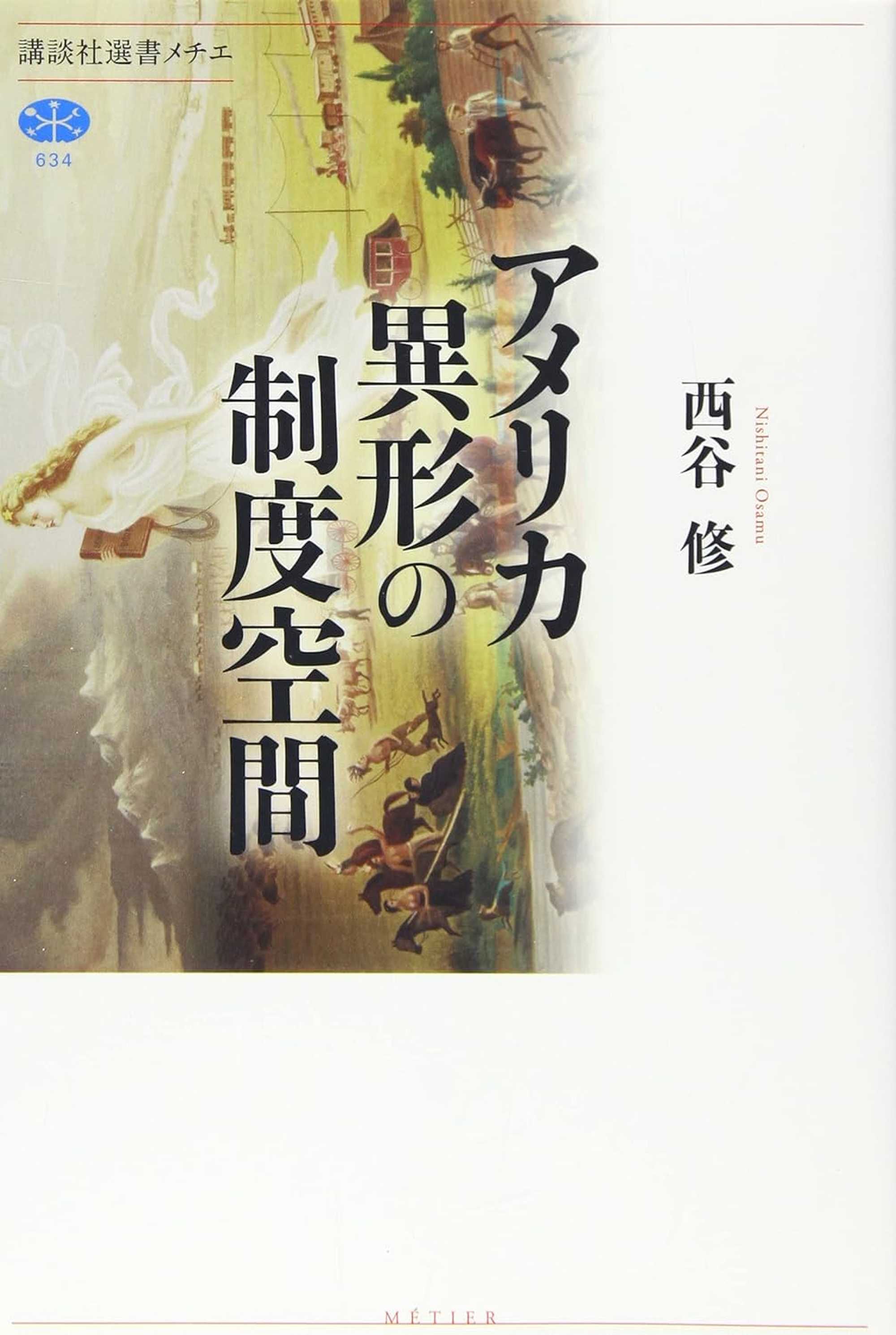政治案件の経済化――国家の変質
ベトナム戦争が国内でも不評になるなかで、フリードマンは早くから徴兵制の廃止を提言していたが、これがニクソン政権によって採用されることになる(一九七二年)。国民によるベトナム戦争への批判は徴兵拒否の問題を引き起こした。ベトナムの「解放」というアメリカの大義が、「汚い戦争」の実情によって蝕まれ、国内で厭戦気分が広まるとともに、折からの公民権運動の高揚もあって反戦意識も高まり、兵役拒否が続出したのだ。本来なら「国民の義務違反」とされる兵役拒否者は国際的にも広い支持を得てそれを支えるネットワークさえできた。昔から国家の戦争政策への「不服従」はあったが(たとえば幸徳秋水は日露戦争に反対した)、「自由の国アメリカ」で、国民がみずから国を守るために兵士となり戦争に行くのが当然という、いわば国民国家の神話が崩壊したのである。
フリードマンは戦争の是非というこの「政治」問題を、経済的に解消することを提案する。つまり、嫌がる国民を無理に戦争に動員することはない。強制的な「徴兵」ではなく任意の「雇用」の問題にすればいい。職を求める一定数の人間(失業者)や、居住権が欲しくて軍に応募する者たち、それに「戦う」ことが好きな連中にも事欠かないだろう。彼らは「自由に」選択してこの職業を選ぶ。そうして採用されれば、自分が選んだ「業務」を嫌がらずにこなす努力もするだろう。徴兵などよりも、その方が効果的に「業務」をこなす軍隊が組めるし、何より失業問題の解消にもなる、と。言いかえれば、国家の政策遂行に、政治批判(いわゆる良心)などというものの介入の余地をなくすのだ。
アメリカはこれを採用したが、事実上それは、国家を企業に見立てた軍隊の「傭兵化」である。そして国家の政策は、徴兵制といういわば国民との契約の束縛から解除されることになる。もちろん、政治代表が選挙で選ばれるというかぎりではそれは民主的な代表だといえるが、その政策(とりわけ戦争に関わる外交政策)は「国民」に負担をかけるものではなくなる。軍隊には「私人」が私的事情・動機で応募するのだから。
では、政府の性格はどうなるのか?アメリカでは株式会社の第一の責務は株主の利益を守ることだとされている。経営陣が担うのはまず株主に対する責任である(今ではそれが世界的な経営規範になっている)。政府のあり方もそれに似てくる。つまり政府は政党(政治家)に投票した有権者に対してではなく、見えない「出資者」たち(株式会社は英語ではjoint-stock corporationだが、フランス語では「無名会社」(sociéte anonyme)と言う)の利益に適うような「経営」を行う。「国民」とはその場合、この企業のたんなる「受益者」とみなされるにすぎない(そうなると、国家の「主権」とは何かということが問題になるが、それは「一票」の数に還元分解される)。ナオミ・クラインはこれを「コーポラティズム国家」と呼んでいる。「会社式国家」だ。その意味で、徴兵制廃止は近代型国家そのものの「民営化(privatization)」の第一歩だったとも言える。
戦争の「民営化」
冷戦後、この「民営化」はドラスティックに進む。冷戦の終結によって核軍縮も始まり、大きな「敵」の解体でアメリカも軍(三軍だけでなく諜報機関も)を縮小する。それは軍事費が膨れ上がった国家財政への対策上も必要なことだったが、それでは膨大な失業者が生まれてしまう。そこでアメリカ政府は退役軍人らにそれまでの「経歴」を生かした起業を促す。そうしてできたのが軍事関連企業、いわゆる「民間軍事会社(PMC, private military company)」だ。
そうした軍事会社は、冷戦後も資源利権をめぐって部族間対立が起こるなど混乱が続くアフリカ諸国に「市場」を見出し、「紛争解決のプロフェショナル」に育っていった。それはイスラエル、イギリス、国家崩壊を経たロシアなどでも有力な「ビジネス」になる。
従来から兵器や軍事物資を生産するいわゆる軍事関連産業はあった。だが、それに加えて石油・天然ガスの開発事業などを行っていた企業も、その世界展開の経歴を生かしてこの「ビジネス」に参入するようになる。ハリバートンはその代表格で、2011年のアフガン攻撃以降(つまり「テロとの戦争」の当初から)、米陸軍の向こう10年間の兵站全般の事業(兵舎設営、食堂、その他駐屯に関わるさまざまな事業)を政府から請け負った(これには、湾岸戦争後に国防長官からハリバートンに天下ったディック・チェイニーが、ブッシュ政権で副大統領になって戦争政策決定に直接関わるなど、他国なら大問題になることが、アメリカではふつうである(「回転ドア」と呼ばれる政・財界移動)というアメリカの特殊事情も関わっている)。それだけでなく、戦争(作戦)の遂行そのものを、特定業務として請け負う会社ができるようになったのだ。これが狭義で言われるいわゆる戦争の民営化である。これまでの戦争が国家の専権業務だったとするなら、その内実が営利を求めて自由に活動する「私企業」によって担われるようになったということだ。
とりわけ「テロとの戦争」以後、アメリカ軍は多くの「戦争業務」をそうした民間軍事企業に「外部委託(アウトソーシング)」するようになる。国家はある政策を立てる。軍はそれに従って作戦を立て、戦争を遂行する。その限りで軍は「公的」な責任のもとに動くのだが、作戦の一部を「私企業」に委託すると、その業務内容について軍は関わらなくていい。「私企業」は委託業務を確実に遂行することで収益を得る。そうなると私企業の業務内容は「公的」なプロセスの中ではブラック・ボックスに入ることになる。
イラク戦争では、ファルージャという町の境の高い橋梁に、アメリカの「民間人」4人が怒り狂った民衆に殺害されて吊るされるという「事件」があった(2004年4月)。この「民間人」こそ、今では名前を変えた悪名高い戦争請負会社ブラック・ウォーターの「社員」だったのだ。彼らの果たした「業務」は推して知るべしである。だが、この事件をアメリカ人に対する許し難い残虐行為として、米軍は直後にファルージャを包囲攻撃し、その後大統領選と絡めて人口30万と言われたこの町の殲滅作戦を敢行した(このときコフィ・アナン国連事務総長が強く中止を訴えたにもかかわらず)。
ネオコンとネオリベの同行
戦争の「民営化」について最初に強い警告を発したのはP・W・シンガー『戦争請負会社』(2004年)だったが、日本でも本山美彦『民営化される戦争、21世紀の民族紛争と企業』(2004年)などの多角的な研究がある。
具体的な事態の詳細についてはそれらを参照してもらうとして、ここで強調したいのは、21世紀にはいる前後から(冷戦後)国家のあり方が経済主体(企業体)との関係で様変わりし、それに伴って戦争の内実も「型崩れ」しているということである。グローバル経済の成立とともに『市場対国家』(D・ヤーギン/J・スタニスロー)が議論され、国家の衰退(後景化)が語られたが、そのこととも関係している。しかし、グローバル経済の共通ルール(公正な自由貿易)のためにそれぞれの国家主権は制限されなければならないという議論のなかで、アメリカだけはその制約を受けることがなかった。というのは、この市場ルールはアメリカ自身が作りだしてきた弱肉強食のルールだからだ。
この場合アメリカとは、コーポラリズム国家としてのアメリカであり、その「株主」(ステークホルダー)とは、軍需産業その他グローバル企業の複合体、とりわけ現代ではIT企業群である。この態勢をあらためて合理化しているのが、私的営利追及の解放のためにあらゆる社会的束縛の一掃を求める「新自由主義」である。そしてそれが国家の変容に伴って戦争のあり方そのものを深く変質させている。そのことを示すために、「戦争の民営化」について一章をさいた。
ただ、もちろんそれでアメリカ国家が解消されるわけではまったくない。むしろ、他国に制約を課しながら(国際法)、みずからはそのルールの守護者として「法外」に君臨し、世界の戦争を結局のところ管理する立場を維持し続けている。では、アメリカ国家はアメリカ国民を民主的に代表しているのかといえば、その「民」は生活する人々ではなくいつの間にかプライベート・セクター(民間部門)と置き換えられ、この「世界帝国」は「大株主」たちの神輿(乗り物)になっているのである(それがナオミ・クラインの言っていることだ)。
「ネオ・リベラリズム」は「自由」を標榜する。一方「ネオ・コンサーバティヴ」は「保守」だとみなされている。「自由」は解放の運動を含んでいるようにみえる。一方「保守」は「解放」による変化は求めない。しかし奇妙なことに、現代アメリカのこの二つの傾向は奇妙に反りが合うようだ。それもそのはず、アメリカ国家の掲げる「自由」は、他者(他国・他地域)のもたらす「他」であるがゆえの障害を突き崩し、「他」を解消してゆく「自由」であり、その「解放」の運動を維持し続けることこそが、世界におけるアメリカの地位を確保し「保守」し続ける道なのだから。