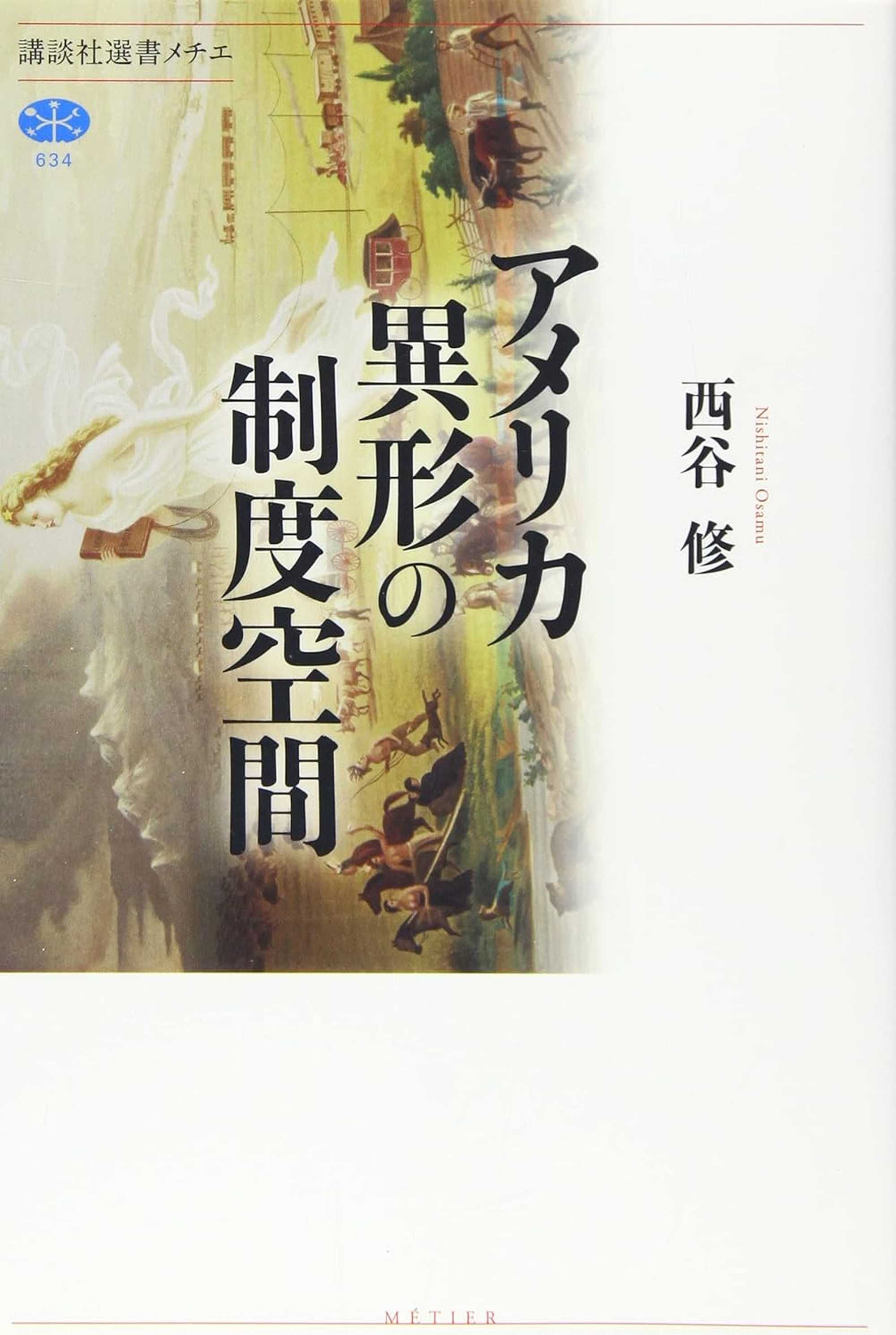新たな「正義の戦争」
「テロとの戦争」とは、それまでの国家間戦争の枠組みを壊し、戦後の国際法秩序を宙吊りにするものだった。当時のラムズフェルド国防長官は「ウェストファリア体制はもう古い」と言ったが、それはアメリカの危機の時にあって国家間秩序・国際法体制は無視されるという宣言でもあった。アメリカの危機は世界の危機であり、その「非常事態」にあって、米大統領は「決断者」として振舞うという、カール・シュミットの例外状況論を超国家的に地で行くような発言であり、振舞いだった。
「戦争」とは基本的に対称的行為である。国と国とが戦争をする。そこが対等だからこそ、相互責任論が成り立つ。市民と戦闘員の区別とか、捕虜の虐待禁止とか、停戦交渉なども。ところがこの「戦争」は「非対称的」だと言われる。アメリカ政府筋がそう言い、メディアがそう伝え、多くの学者たちもがこぞってそれを解説しだした。
まず国家対国家の抗争ではない。国家に対する「攻撃」(9.11)はあったが、それに対して国家(超国家)が不確定の「敵」を「テロリスト」と呼び、その「見えない敵」に対して戦争を宣言する(ブッシュはまず「これは戦争だ!」と言明した)。だが、この宣言は同時に「敵」からこの戦争の責任を担う「当事者能力」を奪っている。敵は不法な「犯罪者」と断定されているのだから。だからこの場合、国家の行う戦争行為が「正義(裁き)」の執行だということになる。
じつはウェストファリア体制は「正義の戦争」を排除していた。戦争に善悪はない、決着は戦争が下す。だからこそ「戦争は政治の延長」(クラウゼヴィッツ)であり、後の交渉も成り立つ。それを「無差別戦争観」と言うが、これは宗教戦争が「神の正義」の名の下で戦争の暴力と破壊を無制約化していたことに対する反省から生まれた知恵でもあった。「人類の敵」などを作ると、戦争の暴力と破壊には歯止めがなくなってしまうからだ。
だが、この戦争における「敵」の断罪は、すでに司法上の「判決」となり、それに対する戦争の発動は刑の「執行」としての意味をもつ。「テロリスト」という断定は「徹底的掃討」ないし「抹消」という判決であり、戦争はその抹消を行為として遂行する。
では、誰が「テロリスト」と判定するのか?それは「テロリスト」を敵として戦争を遂行する国家である、ということになる。このレジームでは、いわば裁きの「第三項」は排除されて、司法と行政とは一体化し、その一体化が立法を不要にしている。それは他でもない独裁や全体主義体制の特徴である(だからこの時代にアメリカは「帝国」と呼ばれた)。
このとき、米大統領ブッシュは国際社会に対して「我々につくか、敵につくか」と二者択一を迫った。それは国際社会における「第三項」の排除であり、米大統領は国連に代表される社会の前で、アメリカの「非常時」を世界の「例外状況」であると宣言して、世界の「主権者」としてふるまったことになる(各国は、アメリカの被災とパニック状態に同情して「テロとの戦争」を受け入れた)。
「非対称性」の中身
「非対称性」は戦争の内実にも表れる。一方は超権力を背景に、超法規的暴力を最強の軍備とともに行使し、他方は貧弱な装備や武器で応戦しながら虫けらのように掃討され潰されてゆく。だから「戦果」は一方にしかないが、それもシンガポール陥落とかカンダハル奪取とかではなく、「テロリスト○○人殺害」として公表される。ともかく、人間とはみなされない「敵」を皆殺しにするのがこの「戦争」の目的であること、それがもはや隠されもしないのだ。そしてその「殺害」のためには「コストはつきもの」で、一人の「テロリスト」を殺すためには百人の巻き添えや純然たる「誤爆」があっても仕方がない(米軍用語では「コラテラル・ダメージ」と言う)とされる。さらには、ジャーナリストであれ住民であれ、攻撃の邪魔になるものはテロリストを守る「人間の楯」だと言われ、そこにいること自体が犯罪視される。
また、この「戦争」は、やればやるほど人間の地獄を生み出し、焦土と化し非人間的に荒廃した地域(戦地)から、一層の憎悪と復讐心に満ちた新たな「テロリスト」を生み出すことになる(9.11以後、「テロリズム」は世界に拡散したが、それは成功体験への追随というより、「テロとの戦争」の暴虐が引き起こしたものだ)。するとそれがまた「テロとの戦争」を正当化し継続する理由にされるのだ。だから「この戦争は長く続く」(ブッシュ)。
この異常な「戦争」概念が、国際関係や政治学・戦争関係の論者たちによって、現にある事象として当然のことのように追認されてきたというのは驚くべきことだ。彼らはそこまで「強者の論理(無理)」を無批判に受け入れている。
彼らは「テロリスト」が世界の安全を脅かす、そんな国際状況の変化があるからだという。だから現代の「戦争」はこのような「非対称的」な形をとる、と。だが、そんな「戦争」が事実としてあるのではなく、あったのはいわゆる「イスラーム過激派」と呼ばれる武装集団による、アメリカの中枢に対する「自爆攻撃」である。なぜ、そんな前代未聞の事件が起きたのか?その「なぜ」を一切問うことなく――むしろそれを問うこと自体を、「テロ」を肯定するとか、「テロリストの肩をもつ」と非難して禁圧する――、不確かな敵に対して国際法も吹き飛ばして国家的暴力を発動するという超大国アメリカの強弁と独断を、そのまま起きている事態として受け容れて得々と「非対称的」戦争を語り出す。そこには、「強者の無理」への無批判な順応、とほうもない知的怠慢や無思考がまかり通っていると言わざるをえない。
「テロリスト」とはどういう概念なのか?
ところで、「テロリスト」とは何なのか?生まれながらの「テロリスト」などというのはいない(いると思うのはアメリカ人やイスラエル人だけだろう)。殺人犯と同じで、いわゆる「テロ行為」を犯した者が「テロリスト」と呼ばれる。しかしこれを本質概念とすることで、国家(既成秩序)の側は大きな手段を手に入れることになる。
現在の用法によれば、「テロリスト」とは万人に恐怖を与える秩序の敵、だから社会から排除し抹消しなければならない存在ということになっている。この「テロリスト」という用語にはじつははっきりした歴史的由来があるが(フランス革命以来)、それについてはここでは詳述しない(丸善『地政学事典』の項目を参照されたい)。一方で「テロリズム」とは近年に昇格した犯罪学の用語である。動機の胡乱[うろん]な集団殺人や無差別殺傷などの事件が起こるようになり、そうした事件を理由や背景を問わずその形式で裁くために用語化された(アメリカのユナボーマ事件や日本のオウム真理教の地下鉄サリン事件など)。その「なぜ」を問うのを省略する犯罪学用語が、90年代から徐々に、そして9.11以後公然と、国際政治用語に「昇格」したのだ(国際政治の場合、「なぜ」を問い始めると事件を一方的に断罪できなくなるから)。
このことを踏まえると、「テロリスト」とはつまり、問答無用で排除すべき極悪人、世界に生存を許されない異物(エーリアン)、あらゆる人権を剥奪された「法外」の存在(むしろ非存在)ということになる。これは国家(超国家)にとってはきわめて都合のよい概念だ。というのは、世界戦争(第二次世界大戦)以後、アウシュヴィッツやヒロシマという無差別の大量殺戮を見て(それだけではないが)、あらゆる人間には生きる基本的な権利、存在する権利があるということが、国家を超えた「普遍的人権」として認められるようになった(「世界人権宣言」)。けれどもそこで打ち出され肯定される人権・生存権・尊厳などは、戦争をしたい国家にとってはやっかいな制約になってきた。戦闘員は除外されるとしても、それ以外の人間は、殺しても、虐待しても、拷問で苦しめても、ましてや大量殺戮の対象にしてはいけないのだ。それは戦争犯罪になる。
だが「テロリスト」と規定すれば、「敵」はあらゆる人権保護の埒外に放り出される。国家はあらゆる手段を用いてそれを駆逐できる。「テロリスト」は「殺しても罰されない」(アガンベンの言うローマ法のもとの「ホモ・サケル」)どころか、むしろ「殺害」することが推奨され、義務とさえされる(そう疑われるだけでも、同等の扱いを受ける)。「テロリスト」と指定することによって、国家は「望ましからぬ存在」をそのように扱う権限を手にする。逆にいえば、みずからの暴力の発動(戦争)に関するあらゆる制約から解放されることになるのだ。
「テロリスト」指定の裏側
では、誰が「テロリスト」と認定(断罪)するのか?
それはまず事実上アメリカ国家である(それに一部の「国際社会」とメディアがすぐに追従する)。逆に、誰かがアメリカを「テロ国家」と呼んでも、何の実効性ももたない。アメリカが「テロリスト」と認定するから、他国もその認定にならうのだ。今でもアメリカは世界各地の特定の人物や勢力を「テロリスト認定」しており、それにならっていくつかの国家も独自の「テロリスト認定」をしている。そしてそのリストに乗ると、場合によっては懸賞金をかけて追及され、「殺害」が推奨される。あるいはテロ組織と認定された集団も解体と抹消の対象となる。
「テロとの戦争」とは彼らを対象とした戦争行為だ。だからその戦争は、国際法(国家間関係法)の埒外にあり、「テロリスト」掃討や殺害のためにはあらゆる手段が可能になる。要するに「敵」はいかなる法にも守られない、人間ともみなされない存在(哲学では「絶対悪」という)で、あらゆる法的保護の埒外に置かれるのだ。
アメリカはこの概念を国際政治用語として認めさせ通用させることで、実際の潜在的標的がアラブ・イスラーム世界というアメリカにとっての「無秩序地帯」とそこに蠢く人びとだという、人種的・文明的差別的偏見をも「中性化」することに成功した。つまりこの時代、「テロリズム」という用語の背後には「イスラーム過激派」という用語が隠されていた。だから、同じくイスラーム系の民族問題を抱えた国々(ロシア、中国その他)もすぐにこの語を援用した。
また、「テロリズム」という用語が犯罪学では形式規定だったにもかかわらず、何かそれらしい無差別殺傷事件が起こるたびに、「政治的背景」のあるなしで、それが「テロ」(日本語独特の表現だが)であるかどうかを判断するというという矛盾も、この用語使用のはじめからの恣意性のためである。
ただ、この用語に最初に飛びついたのがインティファーダ(編注:パレスチナ人による対イスラエル抵抗運動)の制圧にかかっていたイスラエルのアリエル・シャロン首相だったことも思い出しておこう。インティファーダは、パレスチナの抵抗運動がイスラーム化したことを象徴する出来事だった(前回参照)。
そしてもうひとつ、「テロリスト」の頭目とみなされたウサマ・ビンラディン殺害作戦のとき、彼に付されたコード・ネームが、アメリカ合衆国政府に最後まで抵抗したアパッチ族のリーダー「ジェロニモ」だったということも。ジェロニモひとりではない。最初の誤解からそう呼ばれることが習わしになった「インディアン」とされたアメリカの先住民、それがじつは「人権の埒外に置かれた存在」の最初のケースだったと言っていい。彼らはそこにいること自体が「不法」だとみなされ、抵抗したために「殲滅」されることになったのだ。
*「存在と非存在」についての注記
西洋哲学の用語としては、存在(在る)と非存在(無い)は善(肯定される)と悪(否定される)との価値判断と結びついている。在ることが善い(肯定される)のであって、非存在(無)は単に存在しないというのではなく、存在を蝕む「悪(病)」だということになる。いや、「非存在もある意味では存在する」(プロティノス)などと言うと、撞着語法だとか神秘主義だとの誹りを受ける。それは、「在るものが在る、のであって無いものを在ると言うことはできない」(パルメニデス)という、存在と言述の合致を原理とする哲学的(西洋的)言説の宿命でもある。
「テロリスト」が「恐怖を引き起こす因」だとするなら、それこそは「絶対悪」(能動的に秩序を破壊する)であり、「存在してはならない」ということになる。だから「敵」を「テロリスト」と規定することは、すでにして殲滅戦を肯定することになる。だが、誰に「恐怖」をもたらすのか?「敵」は自分の敵ではあっても、全人類の敵ではない(宗主国に対する植民地解放の戦い、奴隷制に対する奴隷の叛乱.、帝国的支配に対する化外の民の叛乱 etc.)。つまり「自己」を相対化すること、それが戦争の場合も全面化を制約する大前提なのだが、「テロリスト」という用語の規範化でこの制約が外されることになった。カール・シュミットが「ゲリラ戦」に関して同様のことを述べている(『パルチザンの理論』)。