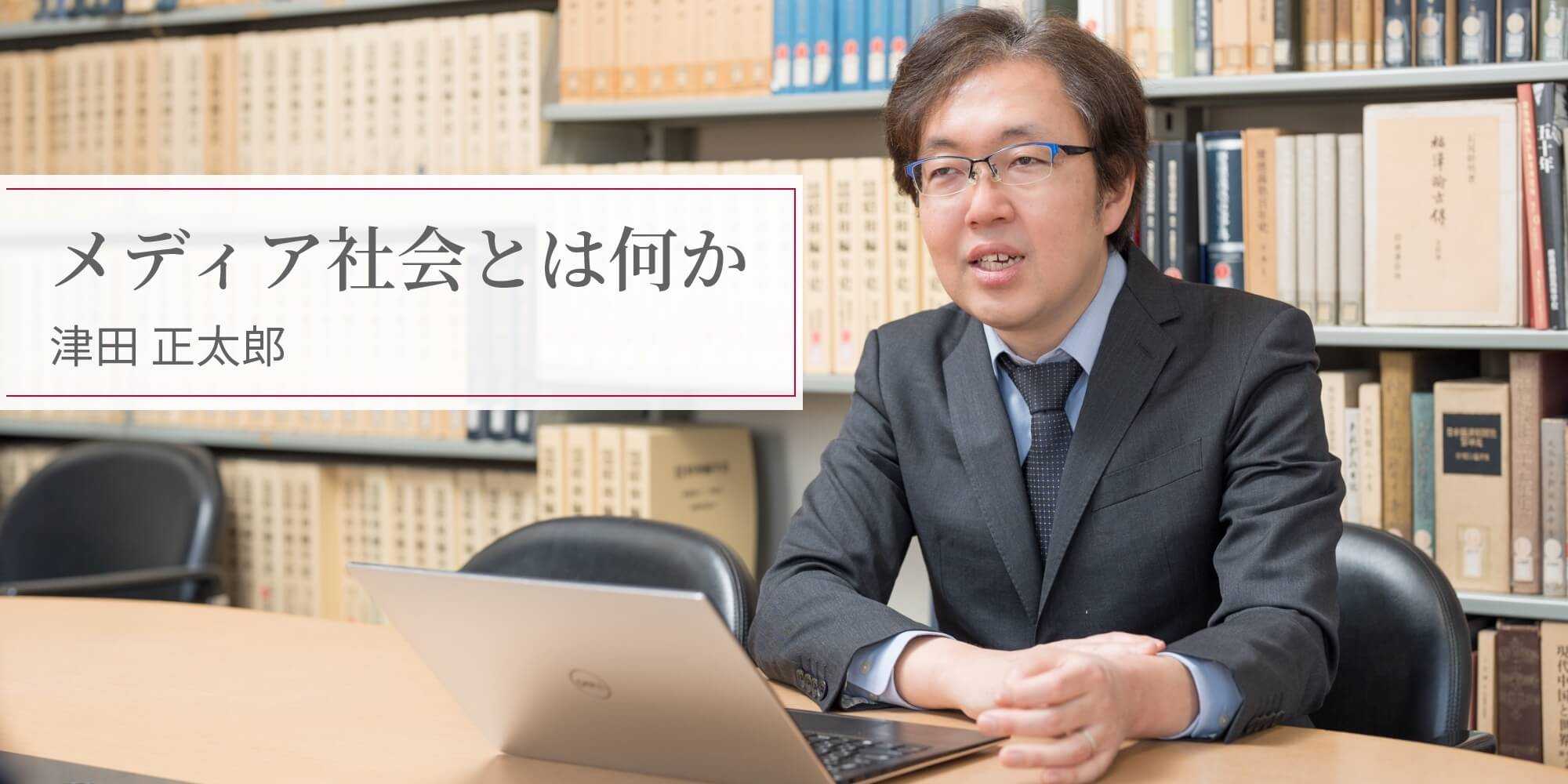中立報道とビジネスの論理
――マスメディアの報道が特定の政治性を帯びていること、いわゆる「偏向報道」への批判はいまもよく見聞きします。なかったことをあったことにしたり、逆に不都合な事実を隠蔽したりするのは論外ですが、新聞社にしてもテレビ局にしても独立した組織である以上、それぞれの主義・主張があるのはむしろ当然だと個人的には思うのですが、マスメディは中立であるべきだという風潮が生まれたのはなぜなんでしょうか。
それは時代によるところが大きいですね。明治の初めごろ、政治的なことがらを扱う新聞は、政党ごとに系列化されていました。つまりもともとは、世の中に向けて言いたいことのある人たちが、自分たちの主張を伝えるためのメディアだったわけです。しかしそれが産業化し、だんだんと成長していく中で、特定の主張に偏るよりも、色を出さずに広くアピールした方が、部数が増えて儲かるぞと。つまり、客観性や中立性と商売の論理がうまくかみ合ったわけです。
そういうモデルで新聞はずっとやってきたわけですが、ここ20~30年でそれが急速に通用しなくなってきています。YouTubeなどを見るとよくわかりますが、いまは広く浅くアピールするよりも、狭く深くの方がユーザーを獲得できるし収益にも結び付く。大手新聞の発行部数はご存知の通り右肩下がりで、一説では、全国紙と呼べるのは既に読売新聞だけではないかとも言われています。
――そもそも、全国紙と呼ばれるものが5紙(朝日、毎日、読売、日経、産経)もあること自体がすごいことだとも思うのですが、それは日本の新聞が宅配制度をとっていることと関係してそうですね。
それはあるでしょうね。海外では新聞は駅で買うのが普通なので、全国紙のネットワークがこれだけあるというのは世界的に見ても特殊です。宅配制度には「押し紙」だったり、勧誘がしつこいといった問題もあるのですが、いい面もあります。私は調査でよくイギリスに行くんですけど、イギリスの新聞は見出しでものすごくあおるんですよ。そういう見出しじゃないと手に取ってもらえないから。日本でも駅やコンビニで買うスポーツ新聞はそうですよね。

見出しだけじゃなく、記事の内容も扇情的というか、人びとを不安に陥れるようなものが多いと感じます。「ブレグジット」ってあったじゃないですか。私はちょうどあの前に2年ほどイギリスにいたんですけど、当時の新聞の論調は、このままだとイギリスは移民に乗っ取られる。この国に移民が多いのはEUに加盟しているからだ。だから、われわれはEUを脱退しなければいけない、といった感じでした。実際にはEU脱退後に移民はむしろ増えており、今では脱退は間違いだったと考える人の割合が正しかったとする人のそれを大幅に上回っているのですが、こんな新聞を毎日読んでいたらEUを抜けたくなるのも無理はないなと思ったものです。
しかし、宅配制度であれば常に一定の売り上げが見込めるので、あおる必要も、極端なことを言う必要もありません。それが日本のマスメディアに、ある程度の「客観性」や「中立性」をもたらしてきたということが言えると思います。
――あおりと言えばネットメディアでもひどいのがありますよね。中身を読むと、見出しに関係あるのって最後の1,2行だけじゃんみたいな。クリックされないとどうしようもないというのはわかるんですけど……。
そうなんですよね。さっきも言った通りスポーツ新聞や週刊誌はずっとそうだったわけですが、最近はそれが全体的な傾向になってきている感じがします。
陰謀論が広まるしくみ
――偏向報道は時に陰謀論的な文脈で語られることもありますが、マスメディアと陰謀論の関係についてはどのようなことが言えますか。
陰謀論においてマスメディアは非常に重要な要素です。というのも、世の中が陰謀に支配されているのは、マスメディアが人びとをそのように誘導しているからだというのが陰謀論者の「論理」だからです。ヒトラーの『我が闘争』には、ユダヤ系の資本がマスメディアを牛耳っているといった話が出てくるんですけど、最近のSNSの言説もこれと同じようなものが多いですよね。
このことからもわかるように、陰謀論にはお決まりのパターンみたいなのがあって、だいたいぜんぶ似てるんですよ。固有名詞を変えればいくらでも応用が利くというか、ユダヤ人のところがフリーメイソンでも、イルミナティでも、在日コリアンでも成り立ってしまう。実は、陰謀論が広がるために重要なのは話として「面白い」ということなんです。マスメディアを操りながら社会を陰で動かしている連中がいるという設定は、いかにもドラマにありそうで面白いじゃないですか。そして、陰謀の主とされることが多いのは、差別されていたり、多くの人びとから反発を買っている集団ですね。
――裏幕とか影のボスとかって、ドラマやゲームなんかだと必ずといっていいほど出てきますよね。
そういったテレビドラマ的なフィクションと陰謀論には相通じるところがあります。ただ、注意しないといけないのは、陰謀論を構成している要素自体は必ずしもフィクションではないという点です。一見関係のない事柄同士が実は裏でつながっていたというのが陰謀論の基本的な論法なので、一つひとつの要素見ると事実(の断片)だったりするんですけど、それが全体として図式化されると、まさに荒唐無稽としかいいようのない話になるわけです。
――それこそテレビや映画でフィクションとして楽しむ分にはいいんですけど、それを真に受けてしまうのはなぜなんでしょうか。
自分が不利な立場にいるときとか、過度なストレスを感じているときには陰謀論の魅力が上がってしまうんですよ。自分は正しい言動をしているのに、なぜ思うようにいかないのか。それは世の中が○○の陰謀によって動いているからだという説明に、どうしても吸い寄せられてしまう。コロナの時に陰謀論がすごく流行ったのも、なんで自分がこんな目に遭わなきゃいけないんだという心理状態が陰謀論の枠組みにうまくはまってしまったのが原因の一つだと思います。
――ウイルスは謀略だとか、ワクチンにはマイクロチップが入っているとか、いろいろありましたね。
ひとつ付け加えておくと、陰謀そのものは実際に存在します。世の中をこういう風に動かしてやろうという企みや試みは、至る所に実在している。しかし、陰謀があるということと、それが機能しているというのは別の話です。

第二次大戦当時の政府や軍の資料を見ると、さまざまな謀略や心理戦の方法が熱心に研究されていたことがわかります。この通りに世の中が動いていれば、まさに陰謀論が正しいわけですが、実際にはその多くが失敗に終わっているわけです。謀略や心理戦はあくまで補助的な手段なので、それ自体で戦略や政策の失敗を逆転できるわけではありません。なので、陰謀があるからといって、世の中がその陰謀によって動いているということはできません。
――ご著書『メディアは社会を変えるのか』では「第三者効果」について触れておられますが、メディアが自分ではなく他人に影響を及ぼすと考えるこの議論は、陰謀論を考える上でも有効だなと思いました。
そうですね。陰謀論が広まっていく要因の一つに、自分はメディアが垂れ流す陰謀なんかには騙されないけど、他人は騙されて乗せられてしまうという心理があるのは確かだと思います。
第三者効果はいろいろな理論と組み合わせることができるのですが、たとえば「沈黙の螺旋[らせん]理論」もその一つです。これは、自分が少数派だと認識すると人は意見を言わなくなり、逆に多数派だと認識すると雄弁に語るようになるというものです。要するに、空気を読むということですね。
これと第三者効果を組み合わせると、メディアがAのことを報道したから、他人はそれに乗せられてBという意見を支持するようになるに違いない。すると自分は少数派になるので、人前では自分の意見を言わないようにしよう。あるいは、多数派になるから言っても大丈夫だ、ということになるわけです。
――その結果、少数派の声はより小さく、多数派の声はより大きくなると。
そういうことです。現実社会ではそう言えると思うんですけど、ネット社会ではそれが逆になっているんじゃないかと考えていて。つまり、ネットでは過激なものの方が(面白半分も含めて)シェアされやすいので、極端な意見を持った少数派の声がすごい勢いで広まり、穏当な意見の多数派がそれに気圧されて黙る、といったことが起きているように思います。
――いわゆるサイレントマジョリティーですね。
はい。ただ、沈黙するのが少数派か多数派かという違いはあるものの、「空気を読む」という点では現実社会もネット社会も共通しています。日本では特に、空気を読むことが重要視される風潮がありますが、民主主義の健全さは実は空気を読めない、あるいはあえて読まない人の存在にかかっています。人びとの多様性を認め、自由な思想や言論によって社会をつくっていくことこそが民主主義の基本だからです。
「大きな声」に対して声をあげたり、攻撃されるとわかっていて自分の考えを表明するのは簡単ではありませんが、異論が出ない社会はやがてそれを許さない社会に、それこそナチスのような全体主義に陥ってしまう危険性があることは、常に意識しておくべきではないでしょうか。