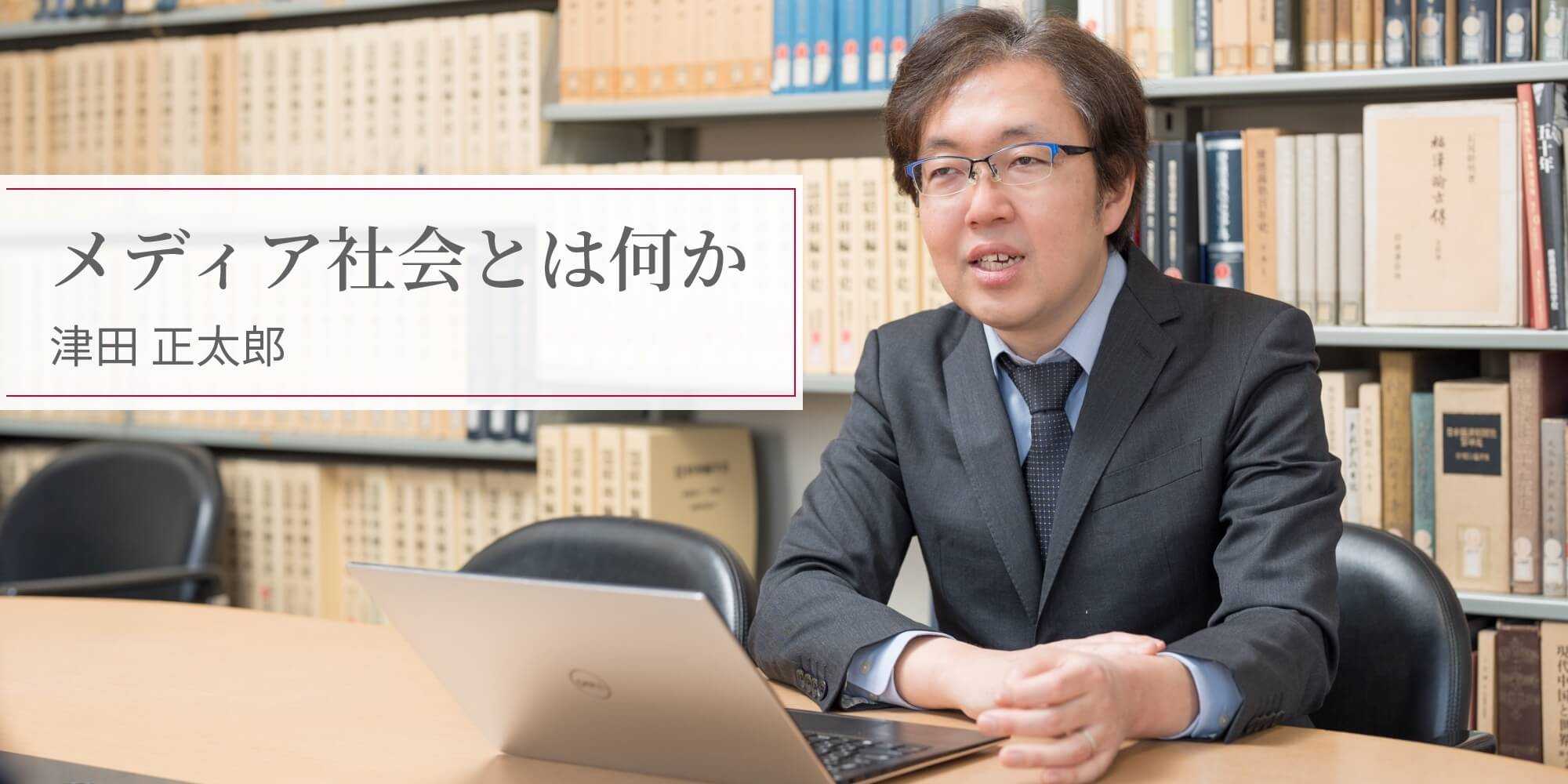希薄化するマスメディア
――マスメディアが抱える問題の一つとして、スポンサーや利害関係者に対する遠慮や忖度というものがあると思います。昨年(2023年)BBCに報道されるまで、ジャニー喜多川氏による性加害が60年もの間ほとんど触れられてこなかったのはその一例ですが、こうした問題に対してわれわれ民衆はどのように対処すればいいのでしょうか。
民間のマスメディアが広告収入で成り立っている以上、広告主からの経済的圧力に弱いのは間違いありません。実際に圧力をかけられたわけじゃなくても、いま言われたように、自分から忖度して報道を差し止めるということもあるでしょう。他方、民間メディアは国に対しては利害関係がないので、わりと好きなことが言える。これに対して、公共メディアの場合は国に予算と事業計画の認可を握られているので、政府に対してはもごもごしちゃうんだけど、例外はあったにせよ一般企業にはそれほど忖度する必要がない。
といったように、複数のメディアが存在することで報道のバランスが保たれるということが言えると思います。逆に言えば、戦時中の国営放送のように、特定のメディアしかなくなってしまうのは非常に危険です。
――ということは、受け手側も一つではなく、いろいろなメディアに接していく姿勢が重要になるわけですね。
その通りではあるんですけど、そこがちょっと悩ましいところで……。というのも、ネットではもう、自分がどこのメディアの記事を読んでいるかなんて考えてないですよね。SNSで流れて来たり、ポータルサイトの見出しをクリックしているだけなので、それが朝日なのか読売なのか、それとも文春なのかは、ほとんどの人が意識していない。課題で出したレポートにスポーツ新聞の記事を引用してくる学生が時々いますが、そうしたことからも、メディアに対する最低限のリテラシーが衰えてきていると感じます。
――たしかに、Yahoo!なんかで気になるタイトルをクリックして、読み始めてみたらどこどこの記事だったということはあっても、そのメディアの記事を意識して読むということはあまりないですね。
そうなんですよ。こういった状況では、いろいろなメディアを見比べてリテラシーを養うことは難しい。とはいえ、じゃあもう一度新聞に加入しましょうと言っても、受け入れられるとは思えない。そうなったときにジャーナリズムやメディア自体の足腰が弱ってしまうというのが非常に大きな問題で、このままいくと10年後にはNHKと読売新聞しか残らない、といったことになりかねません。なので、個々の企業や組織ではなく、業界全体でどうやってジャーナリズムを守っていくかを考える必要があると思います。

――いまは新聞だけではなくテレビ離れも深刻ですよね。
以前、北海道の中学生から、若者のテレビ離れをどうすれば止められるかというテーマで取材を受けたことがあります。その子に「テレビは見てますか?」と聞いたら「いや、見てないです」と。「なんで見ないの?」って聞いたら、「ネトフリの韓国ドラマとかYouTubeの方が面白いから」というので、答えはそこにあるんじゃないのって伝えたんですけど。
――なるほど(笑)
私の家にも子どもが二人いますが、地上波はほとんど見ないですね。われわれの世代より上はまだ見ていると思いますが、各種調査でも示されているように若者のマスメディア離れが進むなかで、これまでと同じようなやり方でジャーナリズムを維持していくのは、基本的には不可能だと思います。なので、さっきも言いましたが、メディア業界全体が、たとえばYahoo!ならYahoo!が音頭をとって、存続可能なジャーナリズムのあり方を模索することが必要ではないでしょうか。
自己責任と同調圧力
――今のお話をお聞きしてちょっと思ったんですけど、マスメディアの存在感が薄くなっていく中で、そのマスメディアが結びつけてきた「想像の共同体」としての国民意識はどう変化するのかなって。普通に考えれば、マスメディアの衰退とともに国民意識も薄れていきそうなものですが、実際にはナショナリスティックな発想や物言いはむしろ増えていると感じます。
人びとの意識や世論、あるいは世間の「常識」といったものは、一つの方向に向かって一斉に進んでいくというより、同時進行的に正反対の方向に向かっていくという面があります。
一方において、個人化はすごく進んでいる。家族でテレビを見るのではなく、自分の部屋でスマホやタブレットを見るといったこともそうでですが、どんな仕事に就くのかとか、結婚するかしないかといった人生に関わるような選択が個々の判断に委ねられ、それがもたらす結果はすべて自己責任だとする風潮が強くなっている。
他方で、社会で何かが起きたときには、みんなと同じ行動をとることが実質的に強いられるということがあります。コロナ禍のマスクや自粛なんかはその典型ですね。つまり、普段はそれぞれがバラバラの方向を向いているんだけど、非常時にはそこに強烈な同調圧力が働き、従わない人は全体から攻撃されるということが起こる。その最たるものが戦争で、たとえばウクライナではロシアとの戦争がはじまったことで、国民意識の形成が加速度的に進んだということが指摘されています。
――普段は個人がバラバラに生きているんだけど、災害の発生や外敵の出現といった非常時においては短期的に国民意識が高まり、ナショナリズムが高揚すると。
国民国家というコミュニティとしての実態は消えかかっていて、たとえば誰もが見ている番組だったり、知っている音楽だったりというのはどんどんなくなっているんだけど、同調圧力だけは水面下に滞留している。「私」という意識だけでなく「みんな」という意識もあることはあるんだけど、その「みんな」は仲間意識だとか、所属に基づく安心感を与えてくれることはなく、ただ何かがあったときに噴出して、「私」に有無を言わせない圧力をかけてくる。そういった状況なのではないでしょうか。

――X(旧ツイッター)なんかを見ていると、それを介してつながるというより、気にくわない意見をつぶすものになっていると感じることがあります。
ネットの言論というのは両極化する傾向がありますからね。AとBという意見があったとして、心情的にはAを応援したいなと思っていても、完全に一致していなければ受けて入れてもらえない。二者択一を迫られるというか、AとBの間にいてどちらかというとA寄り、といったことが許されないんですよね。
――それについては、表現の形式も関連しているのではないでしょうか。140文字制限のXはもちろんですが、ヤフコメなんかも短い方が読まれやすいので、その中で情理を尽くして説明するというのはどうしても難しい。発言の恣意的な「切り抜き」もよく問題になりますが、注目を集めようとして、過度に単純化された、歯切れのいい言説が出回った結果、言論が極端化していくという面があるように思います。
それはあるかもしれませんね。とりわけ日本では、他のソーシャルメディアから炎上しそうな「素材」が集まってきて、発火する起点になるのがXという状況だと思います。あの拡散しやすく、140文字という限られた文字数で構成される言論空間自体が、なにか暴力的なものを孕んでいるのかもしれません。
メディアと時間感覚
――それに、Yahoo! を見ていて思うんですけど、あのトップページってすごくシリアスなニュースと、それこそスポーツ新聞が取り上げるようなゴシップが同列に並ぶじゃないですか。それがちょっとどうなんだろうと。先ほどもPVのお話がありましたが、パレスチナ・イスラエル戦争のような報道と、大谷翔平の通訳がどうのこうのみたいなのが同列に並んだら、複雑なうえに読んだら暗い気持ちになるような前者より、気楽に読める後者をクリックしてしまうだろうなと。その結果、ゴシップや娯楽ばかりが消費され、誰もが考えるべき問題がなおざりにされていく危険性を感じます。
メディアのそういった「節操のなさ」というのは今に始まったことではなく、たとえばテレビのニュースでも、深刻な報道のすぐ後にプロ野球のダイジェストやお気楽なCMが流れたりしますよね。これに対する疑問の声は昔からありました。ただ、テレビの場合はそれでも番組という枠や、スポーツコーナーといった枠があるんですけど、ネットの場合はそれがありません。Yahoo!のトップで目に付いたものだったり、たまたまSNSに流れてきたものを、そのときの気分でクリックするだけ。こういう体系性を欠いたメディア接触のみになると、出来事を連続として捉えることが難しくなってしまう可能性はあると思います。

――枠がなくなっているというのはおっしゃる通りですね。私が子どもの頃は、たとえば5時からアニメを見て、6時代はニュースだからその間に宿題をして、7時から夕飯を食べながらプロ野球を見るみたいに、テレビがある種の区切りになるというか、テレビと生活のスケジュールがリンクしていましたが、ネットは「いつでもどこでも」好きなものが見れるので、そういうことがないんですよね。
もちろん便利ではあるんですけど、時間と場所の制限がなくなったことにより、個々のコンテンツとの接し方というか、気分の切り替えがしづらくなっているように思います。アニメを見る気分とニュースを見る気分というのはやはり違うと思うのですが、ネットではその切り替えが(するかどうかということも含めて)受け手に委ねられている。そうなるとどうしても、精神的な負荷の軽い方、めんどくさくない方に流れてしまうのかなと。
メディアと時間感覚は、これ自体が重要な研究テーマの一つです。ネットの登場や、それ以前のビデオデッキの普及といったことによって、それまでメディアに規定されていた生活リズムが、良く言えば多様化したのですが、悪く言えば非常にごちゃごちゃになってしまった。その結果として、いま言われたように、「6時だからニュースを見るか」といった意識を持ちづらくなったということはあるかもしれません。
もう一つ注目したいのは、現代のメディア接触がすきま時間で行われているといことです。電車やエレベーターを待っている数分間だけ記事を読み、来たらすぐにやめる。こうした断片化がわれわれの時間感覚や情報摂取の仕方にどのような影響を及ぼしているのかは、今後重要な研究テーマになってくるのではないでしょうか。
(取材日:2024年3月19日)