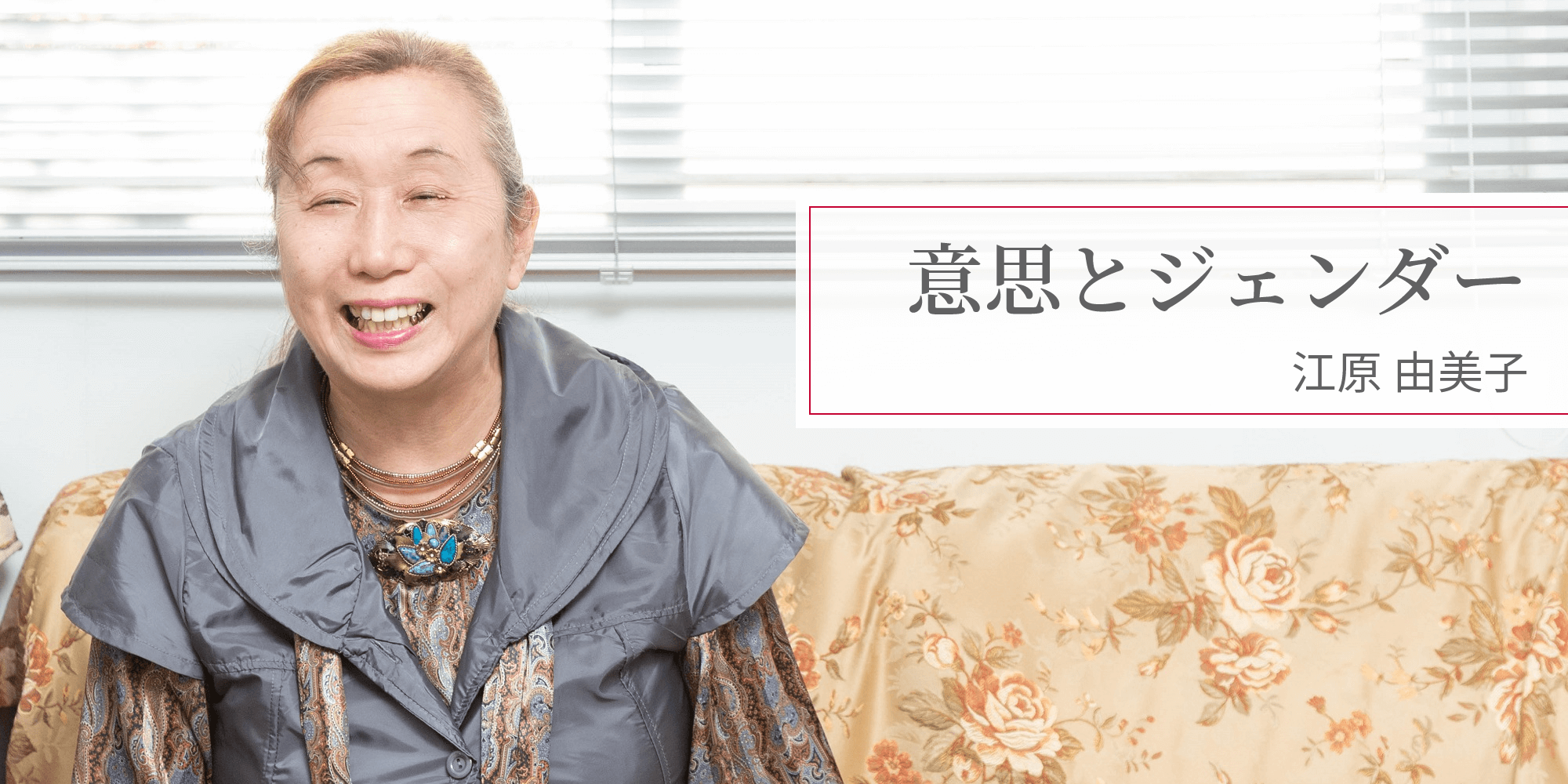――ご著書『自己決定権とジェンダー』で書かれていた、妊娠して子どもを産むか産まないかという「女性の自己決定権」を、「身体の自己所有」という論理で正当化するのではなく、できる限り社会的文脈の中に戻していくべきだという議論にはすごく納得させられました。私たちは今当たり前のように「自分の身体は自分のものだ」と思っていますけど、この発想はそもそもどこで生まれたんですか。
これは個人の自由を重視するリベラリズムと深く関わっています。市民革命以降のヨーロッパやアメリカ社会における「人権」の基本になっているのが、「自分の身体は自分のものとする」という考え方なんです。なぜならそれが、奴隷じゃないことの証だから。そこから、「自分の身体がつくり出したものも自分のものだ」となり、それが「私有権の尊重」という考え方につながっていくんです。
――なるほど。自分の身体は自分のものだっていうのは、それこそ家父長制における女性や子どものように、他人の所有物ではないということなんですね。
そうです。自分の身体は自分の意志によって動かすのであって、誰か別な人の意思によって動かされてはならない。他人の意思に従わざるを得ないような人間は、自由な主体ではない。つまり、自分の行動に「責任」を取れない存在だということになる。
家父長制では、女性や子供には理性がないから、自分の行為に責任を持てないということで、男性に従うべき存在とされた。でも面白いことに、このような「身体の自由」という考え方が、さらには、「自分で働いて得たものは自分のもの」という、貴族制を否定するような近代思想をも喚起したことです。市民革命を導いた思想の中には、確実にこの要素があって、「自分で働きもしない貴族が民衆から生産物やお金を収奪してのうのうと暮らしていることはおかしい」という告発があったわけです。

このような「身体の自由」を根拠にした思想は、さらには、社会主義思想をも生み出していきます。「自分の身体を使って生産したモノは、その生産者のモノ」だということが、社会的平等を志向することにつながっていった。
でも、もし男女平等だとすると、この「自分の身体を使って生産したものは、その生産者のもの」という主張には矛盾があることに気付くはずなんです。女性は、「自分の身体を使って」、人間を生み出すわけですから、同じように考えれば、すべての人間は母親のものだってことになるでしょう。もちろん父親も関与はしたけど、主要な「労働」は母親がやったんだから。そうしたら、誰のものでもない「自由な人間」はいなくなってしまう。
――たしかにそうなりますね。
それなのに、当時の啓蒙思想もその後においても、その矛盾を認めることは、ほとんどなかった。社会的平等を主張しながら、男女平等だけは認めなかった。認めてしまうと、おそらく主張自体が成り立たないから、女性には市民権を与えなかったのかもしれないですね。
もし「女性の身体は女性のもの」だという「身体の自由」を女性にも認めた場合、近代社会が成り立たない。子どもを産み育てることは、女性が行う生物学的行為で、平等とか自由とかの「社会的正義」とは関わりのないことなんだとしておかないと、家事や育児がなぜ女性によって無償でなされなければならないのか説明できない。
だから、婦人参政権が成立した後も、「女性の身体は女性のもの」といったとたんに、女性たちには、「わがままだ、そんな勝手が許されていいのか」というような非難が浴びせられてきたわけです。でも、問題は根本ですよね。「自分の身体は自分のもの」という考え方自体が、はたして無制限に成り立つのかどうか。それが本当の問題だと思いますね。
――私たちが自明だと思っているそのことにこそ、疑いの目を向けるべきだと。
私は「子どもは女性のもの」だなんていうつもりは毛頭ありません。誰のものなのかといえば、啓蒙思想的には当然、胎児も、自分の身体を持っている主体であり、ひとりの人間であることは、認めます。でもそれは、当然女性にもあてはまる。ならば、人工妊娠中絶の問題では、このふたつの主体が対立していると考えることになる。そしてこれが啓蒙思想を引き継いだリベラリズムの主流の考え方になっている。けれども、本当にそういう話なのかなって、私は思うんですよ。
リベラリズムにおいては、「自由」というのが一番大事だと考えます。なので、その自由を侵害しない限り、他人に対する責任はないと考える。人に危害を加えるのは罪だけど、加害しない限り責任はない。基本的には、社会正義は、他者に対する責任を含まない形で、整理されている。
この考えを基盤とする場合、人工妊娠中絶は、胎児を「女性の身体の一部」として見るのか、「独立した別の主体」として見るのかが問題になります。前者の場合は「女性の身体の一部」なのだから「女性の身体の自由」という理由によって人工妊娠中絶が正義にかなうとされ、後者の場合は、独立した人格なのだから人工妊娠中絶は「殺人」となります。
――他人に迷惑をかけなければなにをするのも、あるいはしないのも自由だ、というリベラリズムの考え方からは、そういう問題が生じてしまうわけですね。
人間はそれぞれ独立で「自由」だという前提から出発すると、他人を支える義務はないということになる。でも、「妊娠した女性と胎児」って、それぞれ独立した対等な個人としての関係じゃないですよね。女性は自分の身体を通じて育てている、支えているんですよ、子どもを。
人工妊娠中絶というのはそれをやめることですけど、リベラリズムが前提にしているような論理でいえば、それを「殺人」とはいえないですよね。だって、女性は加害したのではなく、支えるのをやめただけなんだから。
けれど、その結果胎児は死ぬことになる。でも相互独立という考え方からすれば、他人を支えないことと、殺すことは一緒ではない。リベラリズムで考えるんだったら、「自分の身体は自分のもの」なので、それを他人に使わせるかどうかは、当然、自分で決めていい。
臓器移植だってそうですよね。自分の身体の一部を自分の意思で他の人にあげるのであって、本人が嫌だといっているのに取っちゃうというのはあり得ない。使わせないっていってるのに、あなたの心臓はこちらの方に使わせてもらいます、手はあちらの方にあげてくださいっていわれたらみんな怒りますよね。
――それはそうですね。誰もそんなことを他人に決められる筋合いはないと、一般的には考えると思います。
だから「自分の身体は自分のもの」だとすると、同じ論理で、「産むか産まないかの決定権」は女性に与えられてしかるべき、ということになりますよね。リベラリズムを前提として、「胎児は独立した人格なんだから、人工妊娠中絶は殺人だ」という人たちは、その前に,女性には「独立した人格である胎児の生育に、自分の身体を使用させるどうか」という意思決定を行う権利があるということを、問題としなければならないはずです。

なのに、そこにはなんの関心も払わない。そして、「胎児が独立した人格である」という考え方を、女性の人工妊娠中絶だけに適用するという、論理的におかしなことをやってるんです。
それが今の政治哲学の主流派で、それをずっと問題にしてきているのがフェミニズムなんです。フェミニズムの基本になっているのは、人というのは「他人に加害しなければ自由」なのではなく、「相互にケアし合う責務を負っている存在」として定義すべきじゃないかってことなんですね。
であるならば、ケアを必要とする子どもの命をどのように育てていくかという責任は、女性だけでなく、関係者全員に生じるはずですよね。それを前提として、女性の希望と、夫や周りの人の希望と、子どもの命との関わり合いの中で意思決定がされていく。そういうふうに考えていくしか、解決のしようがないんだと思います。
――リベラリズムがよって立つ、他人に加害しない限りは自由だ、という前提自体への問い直しが必要だと。
そうです。「他人に加害しない限り自由」「自分の身体は自分のもの」という考え方だけで行くと、怖いことが起きる可能性もあります。
今普及しつつある新型出生前診断みたいなものがどんどん進んで、デザイナーズベビーみたいになってくると、子どもをどういうふうに産むか、どういう子が欲しいかということまでが、あたかも女性の、あるいは親の自己決定権だとされる危険性がある。「自分の身体を使って子どもをつくる」とすれば、「いい子」だけを産みたい、それがなぜ悪い、親にはそういう選択権があるという議論を引き寄せる。私はそれには反対なんです。子どもを選択する権利は、親にはないんじゃないかと思う。
でも、だからといって、子どもを妊娠したら女性には産むか産まないかを決める権利はないとは思わない。誰もが一定の範囲で、「身体の自由」という権利を持っているから。 ここでいう「一定の範囲」というのは、「人間は相互にケアし合う責務がある」ということからくる制限です。だからたとえば、自分が病気で、その子を産むと死ぬかもしれないというときに、人工妊娠中絶は当然認められるべきです。
でも、頭のよくない子は嫌だとか、顔の悪い子はいらないみたいに、子どもを勝手に選んでつくる権利までは、「女性の自己決定権」の中に含まれないと思うんです。答えはその間にある。
アイデンティティとしての子ども
――母親と子どもの関係ということでいうと、「東大生を育てた母親」とかって、テレビや本なんかでよく見かけますよね。
なんなんでしょうね、自分の子どもが入学した大学名とかを、母親の業績であるかのように言うことは、私は好きじゃないです。
――でも、「自分の子どもは自分のものだ」って考えていくと、ああいう表現が出てくるのはわかる気がします。
子どもによる達成を、当たり前のように、母親の「手柄」にしちゃってるんですよね。でも、それはやっぱりおかしいでしょう。どう考えたって、ほかの人間を自分のアイデンティティにすべきじゃないですよ。
――「空の巣症候群」でしたっけ? あれなんかも、子どもが自分のアイデンティティになっちゃってるってことですよね。
子どもに入れ込みすぎちゃうんですよね、結局。昔の人はよく女性に、「犠牲になりなさい」といういい方をしていました。母親なら子どもの犠牲になって、自分のことは我慢するべきだって。それで母親の方も、「私は子どものためにすべてを犠牲にしました」といっていばってる。
犠牲になるというのは怖いことでもあって、そう思った途端に、子どもになにかを要求したくなるんですよ。まさかお金は取らないでしょうけど、気持ちの上で、「あなたのために犠牲になった私を認めなさい」といいたくなってしまう。それはむしろ子どもに重荷を負わせることでしょうし、やがて子どもが離れていくと、自分自身がいなくなったように感じてしまう。
――それが「空の巣症候群」になってしまうパターンですね。
でも、犠牲になるって、今はあんまりいわないでしょう。そういわないために「自分の人生も」ってことで、みんな頑張っていますよね。
子どもを育てるのはもちろん大切で、産んだ以上その責任は果たさなきゃいけないし、それが楽しいと思う自分もいる。その調整の中で生きていくということを、一人ひとりが自覚するってことでしょうね。
――子どもを持つか持たないかも含めて、自分がどう生きるかを決めるのが自己決定ですもんね。
その時に一番難しい決断というのは、さっきも少しお話しましたけど、出生前診断で障害を持つリスクがあるといわれた子どもを産むのか、産まないのかだと思うんです。これは誰にも「正解」は出せない、本当に難しい問題です。
このような場合、90%以上の人は人工妊娠中絶をしているのが現状です。実際はそうなんです。女性は、未来が見えない、自分がどれだけの負担を背負うのかわからない中で決断を迫られる。そういうときに、周りのみんな、少なくとも夫とは話し合いながら考えることができたら、自分ひとりの苦しさではなくなるはずなんです。
そういう話ができるような環境が整ってほしいと思うし、産むにせよ、産まないにせよ、社会もその意思決定の重みを一緒に背負っていくべきだと思います。