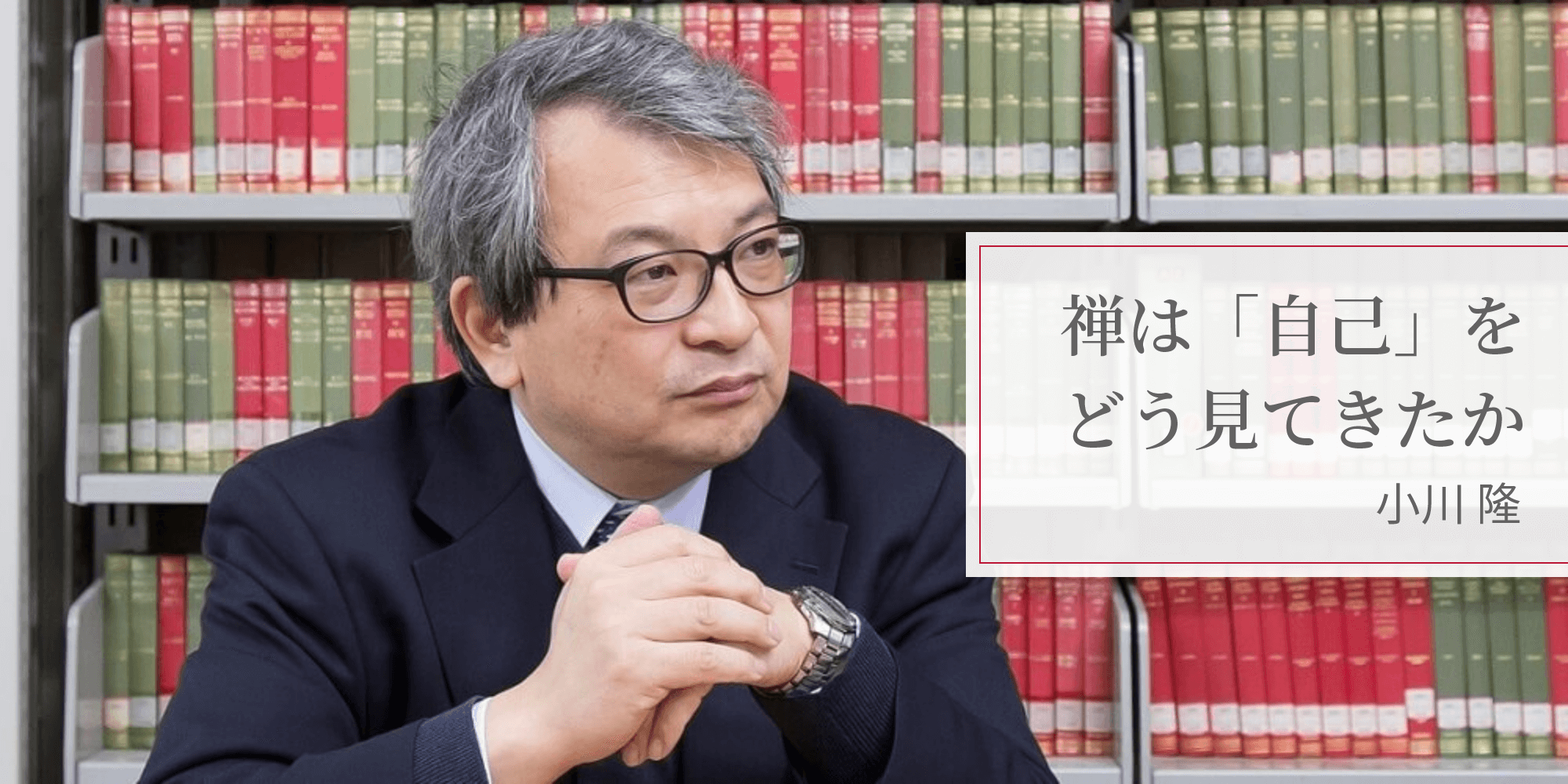――禅宗というと「坐禅をして悟りを開く宗教」というイメージが一般的ですね。でも、先生はそうではないとおっしゃっています。まず、そのあたりから教えていただけますか。
坐禅は禅宗が生まれる以前から行(ぎょう)として実践されていました。禅宗独自のものでなく、通仏教的な行であり、さらには仏教独自のものでさえもない。ですから、坐禅がいくら重要であろうと、それをもって禅宗の特徴とすることはできません。禅そのものの生命を定義するのは無理として――如何なる定義にもはめこまれないというのが禅の生命ですから――中国の歴史上に存在した現実の禅宗の、他とは違うハッキリした外見的特徴として挙げることができるのは、次の3点だと思います。すなわち、①系譜の宗教、②清規(しんぎ)の宗教、③問答の宗教。
詳しいことは『「禅の語録」導読』(筑摩書房・禅の語録20)という拙著に書いてありますので、今、第一の「系譜の宗教」という点についてのみ申しますと、それは教祖と聖典を持たないということを意味しています。私たちがふつう想像する宗教は、教祖や開祖がいて、その著作である聖典があって、これを真理の源泉と考えるというものが多いと思います。少なくとも教科書に載っているような宗教は、そういう形で整理されてますよね。私はこれを「テレビ型の宗教」と言っています。教祖という電波塔の頂点から教えが放射状に発射されて、信者たちがそれを受信するという構図です。
でも中国の禅宗には、教祖もいないし聖典もない。禅宗は達磨(だるま)から始まったということになっていますが、達磨はインドからお釈迦さまの教えを伝えた人であって、教えを始めた人ではない。じゃあ、お釈迦さまが初めかというと、お釈迦さまも起点ではなくて、「過去七仏」という歴代の仏陀たちの一人にすぎない。じゃあその「過去七仏」の一番目は誰なんだとききたくなるかも知れませんけど、それは意味がありません。「過去七仏」っていうのは、真理が始原なき無限の過去から伝えられてきたということを、象徴的に示したものだと思うからです。
禅宗における真理は、誰かから始まったものではなく、無限の過去からずっと続いているもので、それをみんなが駅伝のようにリレーしているんです。正法(しょうぼう)という栄光の「たすき」をリレーした人々、これを禅宗では「祖師」(そし)とか「仏祖」(ぶっそ)と呼びます。禅宗にいるのは教祖でも開祖でもなく、正法を以心伝心でリレーしてきた無数の祖師たち。だから、禅宗の人々が信奉し共有しているのは、その祖師たちの系譜の総体であり、そして、やがては自分もその系譜の一部になることが目標なんです。
さきほどの「テレビ型」に対比して言うと、これは「インターネット」に似ていると思います。中心も頂点もなく、あるのは果てしないネットワークの広がりだけ。そのなかの一つの端末にアクセスすると――つまり系譜に連なる一人の師から法をつぐと――そのまま自分もそのネットワーク全体の一部となり、自らもまた双方向の受信・発信の主体となるわけです。
――特定の誰かではなく、いまここに至るまでのつながりのすべてを信奉しているわけですね。
そういうことです。そして聖典がないから、無数の祖師たちの言葉(語録)がどんどん残っていくわけです。「禅宗は不立文字(ふりゅうもんじ)といいながら、やたらたくさんの書物があるじゃないか」なんて鬼の首をとったみたいに揶揄する人もいますけど、それは分かってない。不立文字だからこそ――聖典を押し立てず、金科玉条を定立しないからこそーー各人が場面場面で、その瞬間瞬間に、自分の言葉で真実を言いとめていかなければいけない。だから、その言葉が無数に蓄積されていくわけです。
――それが、達磨がインドからやってきたときからはじまったと。
それもちょっと違います。禅宗の歴史がはじまったのは、「達磨がやってきたとき」ではなく、「達磨を祖とする系譜意識を共有する人が出てきたとき」と考えるべきでしょう。その系譜を最初に標榜したのが、後に「北宗」と呼ばれるようになる人たちです。彼らが歴史の表面に出てきたのは唐の初め、則天武后の時代。底流となるものはそれ以前からあったようですけど、はっきりと形を持って出てきたのはそのときですね。
――禅宗の教えというか、考え方というのはどのようなものなんですか。
大乗仏教では、すべての衆生に仏としての本性が具わっていると説きます。禅宗でもそれが前提です。バージョンアップしたり、改造したり、欠けているものを補ったりして「仏じゃないものが仏になる」という発想は、一貫してありません。人はもともと仏である、これが大前提です。

でも、現実に生身の人間として生きている以上は煩悩がある、迷いもあれば悩みもある。その迷いや悩みを持っている生身の人間と、本来仏であるという本質、その両者をどう関係づけるか。それによって禅宗史上の時代区分や系統の分岐というものが生じたのではないかと、私は考えています。
――もともと仏であるという本質と、現に迷い悩んでいるという現実を、一つの身の上でどう整合させるかと。
最初期の「北宗」ではそれを太陽と雲の比喩で語っています。仏としての本性「仏性」(ぶっしょう)はもとから完全無欠な形で備わっている。だけど、迷妄の雲がそれを覆い隠している。逆からいうと、雲の下にいる人は真っ暗闇の中で生きていると思っているけれども、それは太陽が隠されているに過ぎない。坐禅修行によってその迷いの雲を取り除いていけば、そこには悟りの太陽が、実は初めから完全無欠な形で無限の光を放っていたのだった。これが「北宗」禅の悟りのイメージです。
――シンプルでわかりやすいですね。
その言い換えとして出てくるのが、鏡とほこり。仏性(ぶっしょう)というのは澄んだ鏡のようなもので、これが自分の心の本質です。でも、そこに煩悩の、チリ、ホコリがたまって、鏡を見えなくしている。だから、坐禅修行によって、その、チリ、ホコリを拭き清めていくと、その下にはもとから完全無欠な澄んだ鏡があったのでした、と。構造としてはいっしょですね。
「北宗」禅の悟りは、おにぎりで言えば「梅干しおにぎり」です。仏性が梅干しだと思ってください。おにぎりの中に梅干しが入っている。外から見たらご飯だけの白いおにぎりと同じように見えるけど、実は違う。中には必ず仏性としての悟りの梅干しがある。ご飯を煩悩にたとえるのは、バチアタリな感じがして、ちょっと気が引けるんですけど……
――はい(笑)
申し訳ないと思うけど、まあ、たとえ話だから、そこは大目に見てください。で、坐禅修行によってご飯を全部食べていくと、中にはもとから完全無欠な悟りの梅干しが光り輝いていたのでした――これが最初期の禅の悟りのイメージでした。