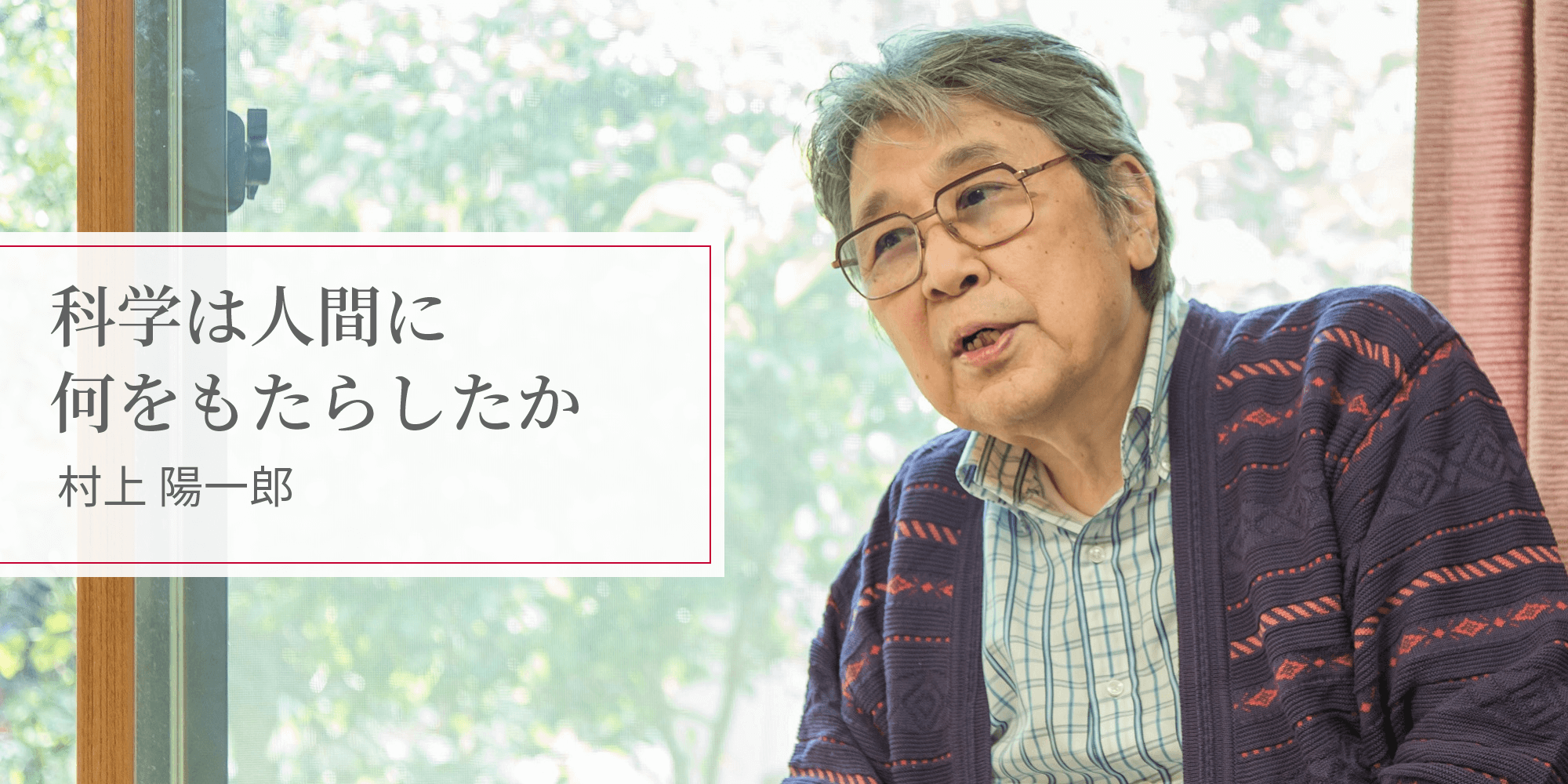――個人的にですが、いまの世の中って科学的なものの見方が絶対視されているというか、科学的に証明されているものだけが真実でそうじゃないものはインチキだ、という風潮が強すぎるのではないかと思っています。特に日本がそうなんじゃないかという印象を持っているのですが、今日はそうした「科学絶対主義」がどのように醸成されてきたのか、ということについてお聞きできればと思います。
初めに、科学的である、あるいは科学的に考えるとはそもそもどういうことなのか、といった点について教えていただけますか。
いろいろな定義があると思いますが、私は「デカルト流に考える」ということだと思っています。一般的によく知られてることですが、デカルトは心身二元論というのを組織的な形で提案した、恐らく近代最初の人物だと思います。つまり、彼が立てた理論においては、物と心が全く違うカテゴリーとして定義されています。
デカルトは『方法序説』の中では、<extentio>というラテン語――これは「伸びる」、「広がる」という動詞の名詞形ですが――を使って、「もの」とは空間の中に広がりを持つ存在だと言っています。私はこれに補足して、空間的だけではなく、時間的にも広がってないといけないと思います。一瞬だけ空間に広がりを持つ何かがあったとしても、われわれは多分それを「もの」とは言わないでしょうから。
――たしかにそうですね。
つまり、「もの」は時・空の中に、ある形で広がっている。そして何らかの感覚を持つ存在なら(別に人間ではなくてもかまいません)誰もがそれを確かめることができる。ここでは、取りあえずはわれわれとしておきますが、われわれがその存在を触覚や視覚、聴覚といった感覚によって確認できるもの、デカルトはそういう概念として「もの」を定立しました。

ですので、先ほどのご質問に答えるとすれば、科学とは「もの」と「こころ」を切り離し、「こころ」の方はそっちのけにして、時間と空間の中に広がりを持っている存在、つまり「もの」がどのように振る舞うかを記述していく立場である。そう考えて、それほど間違ってはいないと思います。
――物と心のうち、物だけを扱うのが科学なわけですね。デカルトは心についてはどう言っているんですか。
デカルトが心について絶対的に、明晰・判明に確証できたのは、この世の中の何もかもを疑ったとしても、その疑っているという状態自体を疑うことは不可能だということです。その疑っているという働きそのものは自分の身体、すなわち物としての身体がなくてさえ、確かめるまでもなく存在している。
デカルトはそこから、少なくとも『方法序説』の中では、たとえどんな人間でも、人間である限りは誰でも心と身体というまったく違うカテゴリーの存在を備えていると言っています。
――物は感覚によってその存在を確かめるしかないけど、心の方は、この世のすべてを疑っている心自体は、確かめるまでもなく、明らかに存在しているというわけですね。
ただ、デカルトが確実に存在しているというのは、結局は「私の心」だけなんです。よく<cogito>というラテン語で言われます――もっとも、彼は『方法序説』をもともとは、フランス語で書いたので、実際には<Je pense, donc je suis>という言葉を使いました――。ここで大事なのは、これが第一人称単数現在なのだ、ということです。
<cogito>としての存在だけは、そのあり方だけは、どんなことがあっても疑い得ない。私の身体とはおよそ関係なく、<cogito>はある。ここまでは非常にはっきりしている。では、他人の心はどうか。
デカルトの親しい友達にメルセンヌという人がいますが、「メルセンヌが考えている」をラテン語で言うと、<Mersenne cogitat>とならなければならない、三人称単数現在ですから。当然これは<cogito>とは別物です。だとすれば、メルセンヌの <cogitat>に関しては、デカルトは疑わなければならないはずなのです。つまり、その存在は一向に明晰でも判明でもないことになります。
――私の心は確かにあるけど、他人の心はあるかどうかわからない。
そのことが非常に深刻だったのは、たとえば心理学が科学的に心を扱おうとするときです。さっきの私流の科学の定義を当てはめれば、それは本来的に不可能になります。
行動と心
アメリカにJ.B.ワトソン(1878~1958)という心理学者がます。彼は「心理学を科学にする方法が一つだけある。それは心理学が心の学問であることを諦めることだ」と考えました。では、心理学は何を扱うのかというと、心ではなく、<behaviour>、行動であると。
――行動であれば、物と同じように感覚で捉えられるからというわけですね。
ここで、日本語というものも、なかなかばかにできないなと思い当たります。たとえば誰かが悲しんでいると言うとき、私たちは「彼は悲しい」、「あの人は哀しい」とは決して言いませんよね。「彼は痛い」とさえ言わない。「彼は悲しそうだ」、「あの人は痛そうだ」と言います。
彼は悲しい、彼は痛いという言葉遣いは、詩人ならするかもしれませんが、これは極めて異例の日本語です。必ず「そうだ」を付け加えるというのは、彼が本当に悲しんでいるのか、痛んでいるのかは、本人以外の誰にも体験できないからです。私が彼の悲しみを、彼の痛みを体験することはできないわけです。
私たちが「彼は悲しそうだ」と言うときは、彼の様子や彼の言葉、「彼はうずくまっている」、「涙を流している」、「悲しいという言葉を発している」、そういう彼の「もの」としての身体に現れた現象を感知するだけです。それをワトソンは、広い意味で「行動」と言いました。
われわれが二人称以上の人の「こころ」について語るとき、実際にやっていることは、その人の「行動」について語っているだけなのだということになります。
――なるほど。
ここに、デカルトが一人称の心しか明確に言い立てることができなかったという問題の、深刻な遺産が現れています。われわれはどれほど愛している相手であっても、その心を見ることも、聞くことも、触れることもできない。この永遠の、ある種の地獄みたいなものが、ワトソンの心理学において結果的に立証されてしまった。
――いわゆる独我論的な状況ですね。
ワトソンの心理学は「S-R心理学」と言われることがあります。SはStimulus(刺激)でRはResponse(反応)です。つまり、ある人に何らかの刺激が与えられると、それに対してその人は何らかの反応をする(反応がまったくないというのも反応の一つです)。
ある刺激に対してどのような反応があるか、を調べることは、人間でもネズミでも細菌でも、あるいはボールでも、地球でも、あらゆる「もの」に対して可能になります。まさに科学は、そういうやり方で、物事を探求していくわけです。たとえば、物体に力を加えると加速度が生じるという。これもまさに物体に加えられた刺激に対する、物体の反応ですね。
ワトソンのような考え方は「ビヘヴィアリズム」(行動主義)と言われますが、彼はこのような方法によって心理学を科学として成立させることに成功したわけです。
――まさに心は「そっちのけ」にして、物の振る舞いだけを見ると。
はい。もっとも、ワトソンの前に「内省心理学」という言葉を発明したヴント(1842~1910)という心理学者がいました。
彼は、デカルトに従えば、「私の心」については明晰・判明に分かるのだから、その「私の心」を掘り下げていって、そこで何が起きているのか、ある刺激に対してどのように感じたのかも含めて、それを見ていこうとした。その結果を他人に対して利用することは――多分他人も同じようになるだろうという推測は認めるにしても――、基本的には出来ないことは承知の上で。このような内省によって、心理学は心の学問として成り立つ余地があると考えたわけです。