
さらに状況が緊迫している。国境を歩いて越えようとする人の数が、もっと増えている。多くはインド人である。これまでインド人学生を乗せた避難バスを何台も見かけたが、徒歩の学生たちはどうして避難バスに呼ばれなかったのだろう。その答えはわからない。多くの留学生が付近にやって来て、国境まで歩いている。また、小さな子どもに大きな荷物を抱えた家族たちが、行き先の見つからぬまま、歩いている。義理の両親はいつになったら到着できるだろうか。だが、できることは、待つことだけである。
わたしはパネトーネ(イタリアのクリスマスケーキ。不敬な者は巨大マフィンと呼ぶ)があまり好きではないが、以前に空港の女性に売りつけられて、一個買っていた。クリスマス後には半額で売りに出される。わたしが買ったのは豪華版で、ピスタチオのクリームが使われていて、ケーキの上面にはピスタチオの粒が乗っている。このケーキは、先月にイタリアで買ってからずっと持っていたもので、わたしの移動に忠実に同行している。いまが食べどきだ。ナイフを探し、ブルガリア人の友人とその娘をパネトーネ・パーティーに招く。わたしの下の息子もやって来る。新しい友人たちと一緒に公園に行き、そのケーキを切り、水とペプシコーラを飲む。

義理の両親の車が、やっと国境付近まで着いた。わたしたちは作戦会議をはじめる。二匹の猫、子どもたち、一匹の犬、現金、義理の父が被るかもしれないリスクを最小限に抑え、全員が確実に国境を越えるためには、どのように三つの集団に分かれるべきか。義理の父(59歳で、失効した身分証明書は家に忘れて来た)が国境で拘束されるならば、そのまま戦地に送られるかもしれない。60歳以下の男性は、戦うことが求められているからだ。
作戦は決まった。わたしは下の息子と一緒に歩いて通過する。義理の父は上の息子と二人で向かい、検問所では、この子を国外に連れ出せる身内が彼しかいないことを主張する。そうすることで、国境警備隊の心を揺さぶり、彼が「若い」年齢であるにもかかわらず通過できることを期待しよう。祖母はひとりで歩いて通過する。そして、元妻が、彼女の夫と猫二匹を乗せて、通行が認められた段階で、最後に車で国境を越える。
わたしは国境まで歩きはじめる。涙が頬をつたう。わたしは確実に国境を通過できるだろう。それは間違いない。わたしは容易だ。問題は、家族の他の者たちだ。
わたしと息子は、兵士が警備する数メートル手前で家族と別れ、ゲートに向かう。状況は散々だ。列はかたちを成していない。何百人もの留学生のかたまりのなかに、ウクライナ人の女性と子どもが加わっている。わずかな望みを持って、わたしは、子ども連れの親に専用の列があるかどうかを聞いてみる。そんなものはない、ということだった。特別列は存在しないのだ。肘でやり合いながら、通り抜けるしかない。
数分間、小競り合いを繰り返しているうちに、ウクライナ人の女性たちが見慣れない人たちと交渉している場面に出くわす。見慣れない人たちは、ルーマニア語を話していて、子連れの女性(わたしの場合は男性)を国境の向こうまで安全に案内すると言っている。交渉するまでもない。その10分後、わたしは待機列の先頭で、そのルーマニア語を話す人びとが運転するアウディのSUVに自分の荷物を積み込む。わたしは、国境を越えることだけでなく、別のことを心配しはじめる。国境通過を手助けする輸送業があることは知っているが、その場合、通常は有料である。この人たちは、お金は要らないと言っている。ならば、かれらは何のためにやっているのか?ほとんどの人身売買のルートは無料ではない。絶望的状況に追い込まれている人間——わたしのような——への無償の支援だろうか? わたしはその車のナンバーを写真に撮り、ルーマニア人の友人全員に送る。これが正しい判断だったのか、考えなおしている。

国境越えまで待てば待つほど、周りの車の人たちとの会話が増えていく。少し緊張はするが、夜行列車の旅の雰囲気が戻ってくる。やはり天使は存在するのかもしれない。留学生たちが、外に出させてもらえないので、ゲートを強引に突破しようとした。すると警備隊は、国境を封鎖した。もし、いま通過し損ねたらどうなるのだろう?どこに行けばいいのだろう?何をすればいいのだろう?
運転手がわたしの荷物をスペアホイールの下に置きなおしたので、わたしは驚いた。生後一ヶ月の赤ちゃんを連れた女性が、新たに乗ることになったという。わたしは荷物を積んだリアシートに移動するように求められる。そこでは足を伸ばすこともできない。これで大人5人、子ども3人になった。国境はまだ閉鎖されたままだ。
眠るしかない。こんな緊迫した場面で言うのも変だが、わたしは睡眠不足で疲れ果てていた。目をつむれば1分もあれば眠ってしまう。何度か目を覚ましながら眠っているうちに、ついに車が動き出す。運転手に対する疑念は、全面的な称賛へと変わる。
アンジェリカ——運転手の名前——は攻める。彼女は、3つの言語で叫び、交渉相手には相手の母語を使って適切に話をする。国境警備隊にも、追い越そうとする他のずるい車にも、歩いている人たちにも、大声で話す。「この車には3人の子どもが乗っています。どいてください」。この三日間で、はじめて、わたしは護られていると感じた。彼女は車で経路に割って入り、乗員全員分のパスポートを集め、警備隊に手渡した。警備隊は、わたしたちに降りるよう命じることすらせず、車を通過させた。国境を抜けた。
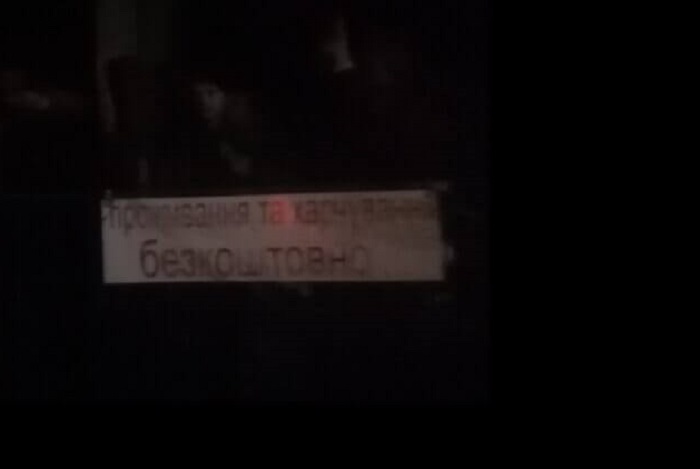
ルーマニアに入ると緊張が解ける。アンジェリカは、わたしをからかいはじめる。ルーマニア側の警備隊に向かって、彼女は「真のイタリア人」(トト・クツグノの1983年の曲の題名:いまでも世界の一部で人気がある)を乗せていると言っている。同乗者全員がにぎやかにジョークを言いはじめる。ついにルーマニアに来た。もう深夜で、あたりは真っ暗だ。にもかかわらず、何十人ものボランティアの人びとが、みんなに食べ物と飲み物を配っているのが見える。ただ人を助けるためだけに、一晩中、かれらはそこで待っているのだ。右手には“kharchuvaniya i zhitlo bezplatno”(ウクライナ語で“無料の食事と宿泊”)と書かれた看板が出ている。目に涙が溢れてくる。何日もの間、わたしたちは、まずミンチ肉のように、その後は、獣のように扱われてきた。ついに、わたしたちを、やさしく気にかけてくれる人びとがいたのだ。
幸運なことに、昔の同居人の母親が、このあたりに住んでいた。彼女は、兄弟が所有する誰も使っていない部屋を貸してくれた。何日かはここでお世話になろう。彼女は毎日食べ物を持って来てくれて、家族の他の者と連絡を取れるようにSIMカードもくれた。息子をショッピングモールに連れ行ってくれて、ケーキを買ってくれた。
どこに行っても彼女は、わたしたちをウクライナ難民として紹介した。それを聞いて、わたしは自分の気持ちと向き合った。現在、難民であることは、あらゆることの鍵である。難民であれば、行列に並ぶことを免除され、ショッピングモールにグリーンパス(ワクチン接種証明)なしで入場でき、駅や食料品店では食べ物を無料でもらえる。でも、その一方で、難民として扱われることを、本人が心良く思っているかどうかは別だ。さらには、どこにも行くところがなく、ほとんどのものをキエフに置いてきたまま——わたしの子どもや、わたしのまわりの人びとが、そうであるように——ならば、かれらがどんなふうにいまの難民状況を感じているのか、想いをめぐらせてみる必要がある。
家族の別の者たちも到着した。これで部屋には5人の人間と、慣れない環境に萎縮した2匹の猫がいる。話し合いがはじまる。これからどこに行くのか、子どもたちの学校はどうするのか、生活に必要なものをどう手配するのか。特に、子どもたちの今後について、しっかり考えなければならない。こんな状況で、子どもたちはどのように生きていけばよいのだろう。上の子はいつもどおり無口で、下の子はこれまでの旅行のときと同じようにはしゃいでいる。下の子は、後になって、ルーマニアでの時間は、戦争避難ではなく、いつものお父さんとの旅行のようなものだったと、わたしに言うに違いない。この数年間、子どもたちを連れて、アジアやアフリカやヨーロッパを旅行して来たことの良い効果とも言える。
息子のスーツケースを開けて、持ってきたものを確認する。息子が使う、伸縮性のあるトランポリン用の靴下を見つける。木曜日、息子はトランポリンの練習の日で、わたしもそこに一緒に行くはずだった。息子はトランポリンが大好きだ。彼の次回の練習は、いつに(そして、どこに)なるだろう。
(石岡丈昇 訳)

