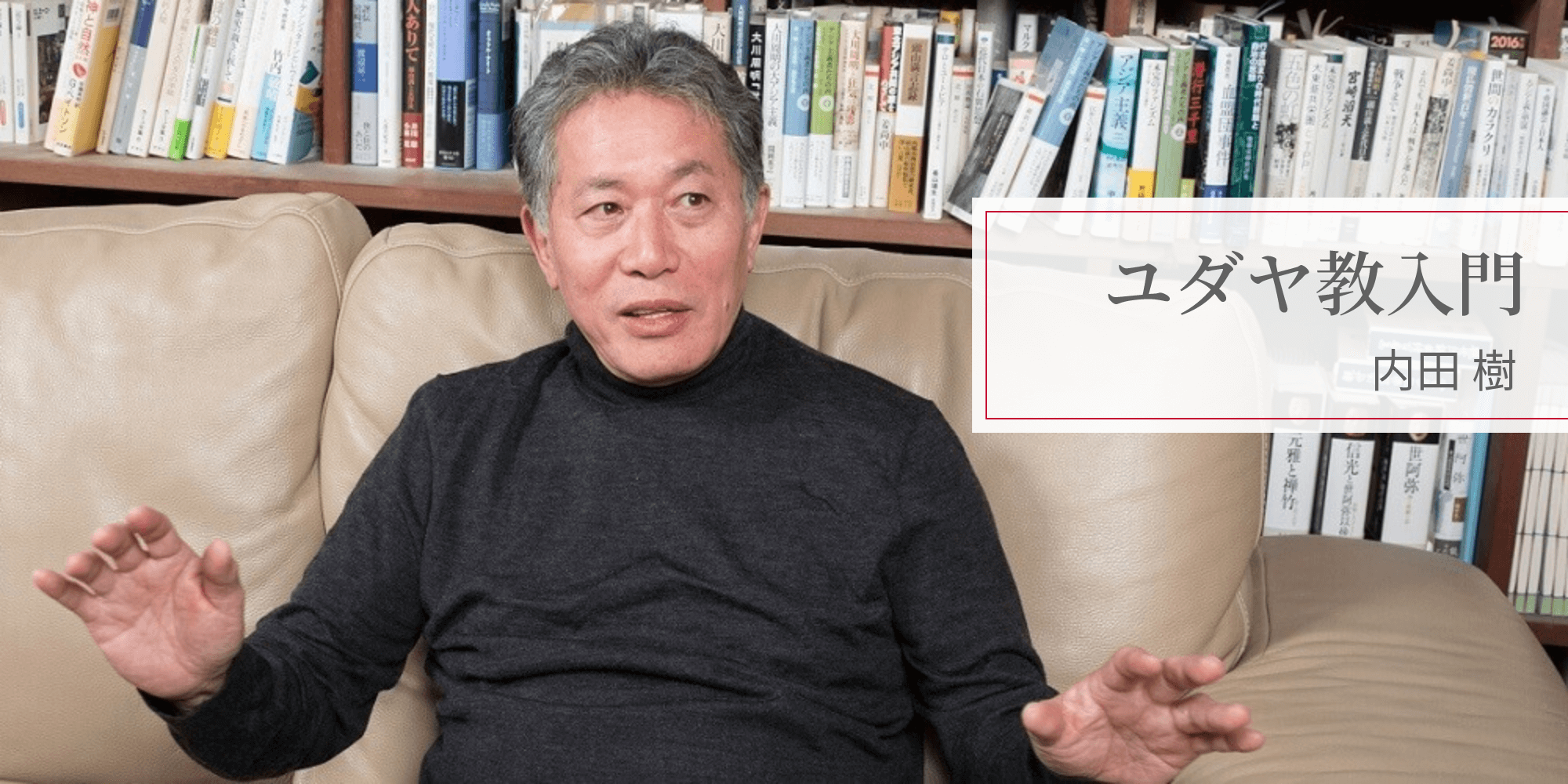――ユダヤ教には旧約聖書の他にもタルムードという経典があって、これがまたちょっと変わってるんですよね。
決定版がないのです。いまも増補版がどんどん足されて増殖している。むかし、東京にいたころには渋谷のJCC(Jewish Community Center)にラビがいらしたので、いろいろユダヤ教について尋ねてゆきました。その時にタルムードはどうやって編集しているのかというような基本的なことさえ知らなかったので、「増補版がいまも追加されていると聞きますけれど、それって、『世界タルムード編集委員会』みたいな組織があって、そこがエディションを決定してるんですか?」って聞いたら、「そんなもんないです」って言う。
「じゃあ、どうやって決めるんですか」って聞いたら、「自然に決まる」って。まさか自然には決まらないだろうと思ったんですけど、「増補版に書き加えられているのはだいたい200年ぐらい前のものだから」って言ってました。広く人口に膾炙して、200年間残るくらいのものなら、タルムードに加えてもいいだろう、と。
――200年! 200年前の何が書き足されているんですか。
もともとユダヤ教は口伝なんです。古代からの律法学者たちの議論の中で非常に卓越したものがあると、人々の間で「ラビなんとかはこう言った」と口伝えで広がる。口伝のタルムードが最初に文字化されたのは紀元2世紀のことです。アブラハムから数えると2000年くらい口伝だけだったことになります。
それまでエルサレムがローマ帝国に占領され、教学と祭祀の中心だった神殿が破壊されて、ユダヤ民族は離散状態(ディアスポラ)を強いられるわけですけれど、その時代にラビ・ユダ・ハ・ナシーという律法学者が口伝の散逸を恐れて、それまで口伝されてきた教説を書籍化したのがタルムードです。でも、当時のラビたちはこの書籍化に猛然と反対したそうです。本来ユダヤ教は口伝のものであって、文字化したのでは教えのもっともたいせつな「生命」が枯渇してしまう、と。いまでも、タルムードは文字のまま読んでも意味がなくて、必ず律法の導師に就いて、口伝でその解釈を学ばなければならないことになっています。
――そこまで口伝にこだわる理由は何なんでしょう。
口伝するためには、本文・解釈を含めて暗誦できなければならない。耳で聞いて、身体の奥深くに収蔵する。口伝の時代でしたら、そのアーカイブする仕事を一人一人の信者が行うわけです。だから、身体にしみ込む言葉は残るし、しみ込まないものは消えてゆく。身体の奥深くにしみ込んだ教えだけが生き残る。
ラビたちはすべての時代を通じて、タルムード解釈について絶え間ない論争をしています。ですから、それぞれの時代には必ず偉大なラビが二人登場して、激しい論争を展開する。ヒッレルとシャンマイ、ラビ・アキバとラビ・タルフォン、ラヴとシュムエル、ラヴ・フナとラヴ・ヒスダ……ユダヤ教史において大学者は必ず「ペア」で出現することになっています。そして、タルムードはこのラビたちの終わりなき論争で埋め尽くされています。論争が熾烈なのは、この論争の目的が「論争を終わらせないこと」にあるからです。

聖句の解釈は、永遠に開放状態に、永遠に未決状態に保持されなければならない。だから、教義にかかわる論争に終止符を打つための「公会議」が存在しないのです。あらゆる時代の大ラビたちの言葉が記憶され、語り継がれ、タルムードに収録される。被言及回数の少ない教えは、仮にどれほど整合的でも、どれほど学識豊かなものでも、伝承されずに消えてゆく。このユダヤ人信仰共同体の歴史的「淘汰圧」に耐えたものだけが教えとして残される、そういう仕組みです。
――経典自体が変化していくなんて、キリスト教や仏教では考えられないですね。
根本経典そのものが今も新たに形成されつつあるというのは、他の大宗教では見られないことだと思います。
――2000年間文字にしなかったというのは、意味をそこで確定させない、固定化することを許さないということなんでしょうか。
ユダヤ教の聖句はラビたちの論争を通じて生命を与えられるものです。だから、この聖句のこの部分はどういう意味だという問いに対して一意的で最終的な「解」というのは与えられないし、与えてはならない。
――「正解」を出しちゃダメだと。
レヴィナスも書いてますけども、聖なる書物というのはそれだけでは乾燥して、仮死状態にある。それに生命を吹き込むのがラビたちの論争なんです。乾燥して、水気のなくなったテクストに解釈者が自分の生きてきた全人生をかけた解釈を加え、いわば、自らの血と汗と涙でテクストを活性化する。それに対して、別のラビがまた彼の全人生をかけた解釈をぶつけてくる。その対立が鋭ければ鋭いほど、テクストは生命力を増す。
――すごく生々しいですね。
一人一人の解釈者が、自分の実存をかけて解釈するんです。
顔
――レヴィナスによると、こちらに向けられている顔は「汝殺す勿(なか)れ」と告げているそうですが、これはどういう意味なんでしょう。初めて読んだときにギョッとしたのですが。
レヴィナスが「顔」(visage)と書いているものは、普通の哲学者だったら「精神」とか「心」といった言葉にしそうなもののことなんだと思います。それをあえて「顔」という生活言語で語っている。それは、その生々しさを伝えようとしているからだと思います。
人間の顔、特に目にはその人の内心がはっきり表れる。でも、目はナイフを突き立てたり、指を突っ込んで、それを破壊することができる。「精神」とか「心」は言葉で傷つけることができますけれど、目を潰すような仕方で具体的に破壊することはできないと思われている。「身体は売っても心は売らない」とか言いますからね。でも、レヴィナスは人間の「精神」や「心」や「意識」はしばしば具体的な暴力によって破壊され、機能停止にされると考えている。だから、あえて「顔」という具体語を用いているのだと思います。
心とか精神とか意識はどこにあるのかよくわかりませんね。脳内のシナプスの信号の組み合わせの中にあるのかも知れないけれど、「ここにあります」というふうには定位できない。でも、顔は目の前に現にあるわけです。face to face で自分と向き合っている。後頭部を見ても、あるいは手先や足先を見ても、「顔をみつめている」とは言いません。

でも、人間と向き合うというのは、まさに「顔をみつめる」ことです。こちらが見つめているように、あちらもこちらを見つめ返している。ふつうはしませんけれど、しようと思えば、指を突き立てて相手の目を潰すことだってできる。でも、まっすぐにこちらを見つめてくる目は「もの」ではなくて、あきらかに「主体」として、そこにある。いかなる暴力にも決して屈服しない他者がそこにいることを宣言している。
具体的な生き物なのだから、「殺そうと思えば殺すことができる」ということと、私とは別の、私と等格のものが、まっすぐ私を見つめ返しているときに、私はそれを「殺すことができない」ということ、殺すことの可能性と不可能性が分かちがたく混じり合っている状態のことをレヴィナスは「顔」という言葉で伝えようとしているのです。
だから、「レヴィナスの言う『顔』って、どういう概念ですか?」という問いの答えを書物のうちに探してもなかなか見つからないと思うんです。自分自身が他者との対面状況で経験した「傷つけたい、でも傷つけられない」「壊したい、でも壊せない」という生々しい実感に裏づけられないと「顔」の含意はなかなかわからない
――なるほど。さきほどの口伝のお話ともつながりますね。
生身の人間と人間の、一対一の関係の中でしか本質的な物事は起こらない。「事件は現場で起きてるんだ」ってことですよ。
――現場を離れた抽象的な概念とか思想みたいなものではダメだと。
もちろん抽象的にも語ることはできるんですよ。でも、それは「死物」である。生きていない。だから、身体にしみ込んでこないし、口伝されることもない。真の人間的出来事は、生身と生身の、一対一の、顔と顔を向き合わせた状況でしか起きないんです。
――なんかわかった気がします。いや、わかっちゃいけないんでしょうけど。
それは禅なんかでもそうですよね。『南泉斬猫』という禅の公案があります。南泉が猫を斬り殺した話を後で聞いた趙州が履を脱いで頭に載せて出て行った……という話ですけれど、そういうのって、その場限りの出来事なわけです。一般性がないし、教訓もない。誰かがそれを真似してやっても、「馬鹿かお前は」って言われるだけです。対面的状況というのはそういうものです。一回しか起きない。