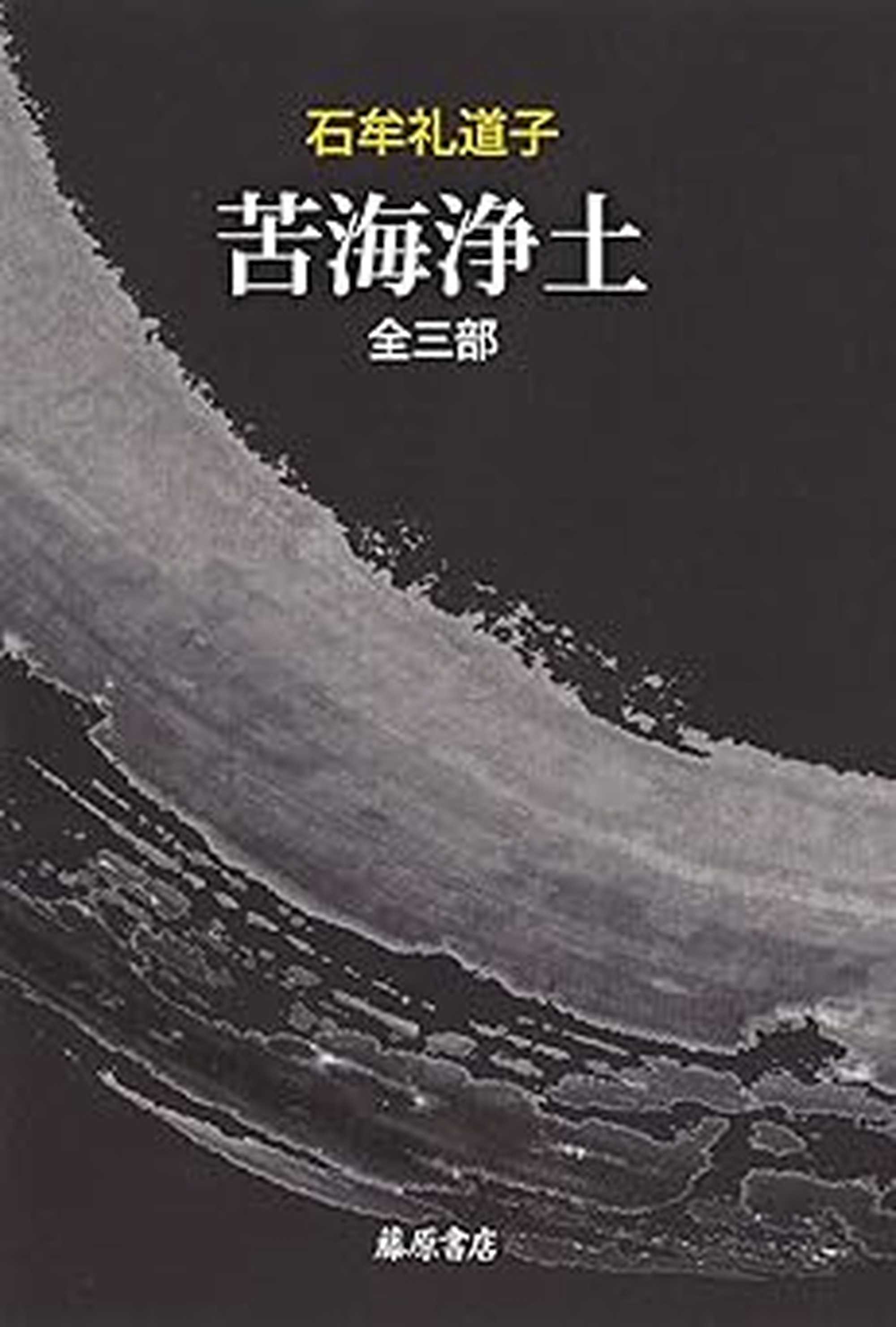近代化に逆行する大国?
近代化を経て、逆転することのない進歩と考えて来たものがくつがえるような事態があいつぎ、近代化とは何だったのか、見失いかねない事態が広範に生じている。ロシアのプーチン大統領は政敵を殺害し隣国に侵攻するなど、法による支配や第二次世界大戦後の国際秩序の理念を覆すような行動をとっている。米国のトランプ大統領はイスラエルによるガザ侵攻を支持するのみならず、それを批判する人物を国外追放するとか、大学においてそのような言説を行うことを妨げるような措置をとっている。
国連の安全保障理事会の常任理事国である国々が、近代がもたらした人類社会の進歩と見なされてきたものを踏みにじるような事態が生じているのだ。そしてその背後に、ロシアにおけるロシア正教、米国における福音派キリスト教のような宗教勢力が小さくはない役割を果たしていることが気になる。これはこの両大国だけではない。世界各地における攻撃的なイスラーム勢力やヒンドゥーナショナリズムなどの伸長も平和を脅かす動向として懸念の対象となっている。
すべての人々を人間として尊び、そのような社会のあり方のための制度を前進させる。人権を尊び、特定の人たちの専横が行われないようにする。真実を尊び、そのために誰もが教育を享受し、精神や表現の自由を保障する。そのために法による支配を上位に置き、立憲政治を行う。少数者の支配を退けて、普遍的な人権を保障して民主主義の制度化を進める。また、法による支配を国際関係にまで広げていき、公正な国際秩序と世界平和へと前進する。宗教はこうした人類社会の進歩と見えたものを支持するものと考えられていた。
人道的な社会生活を推し進める方向でのこうした変化は、二〇世紀の二つの大戦の時代を経て、前進していくと考えられ、その認識は多数の人々によって共有されてきた。ところが二一世紀に入ってそのような認識がもはや維持できない事態が進行している。だが、このような大国の専横や政治家及び富者による力任せの政治というのも、近代化の一つの帰結というようにも見なくてはならないだろう。
二〇世紀には膨大な数の人命が失われる世界大戦が行われ、ホロコーストや原爆による大規模な虐殺、スターリンによる政敵や批判者の殺害や強制収容、ポルポトによる大量虐殺など人道に著しく背くような事態も進行した。東西冷戦の時代には核が用いられる新たな世界大戦の危機が恐れられ、それを防ぐための安全保障という名目で軍備の増強や抑圧的支配も進行した。一九八九年のベルリンの壁の崩壊によって東西冷戦は解消したが、その後も戦争は続き、軍備増強も続いている。二一世紀に入って事態はさらに悪化し、先進国の中でも先頭を走っているように見なされてきた米国において、基本的人権や良心の自由、学問の自由が脅かされるような事態が目立つようになっている。
日本の戦後と苦難
第二次世界大戦後の日本は、戦時中と敗戦直後の苦難を乗り越え、高度経済成長を経て比較的豊かで安定した社会に転じていく。この時期の日本は近代化の利点を享受していくように考えられ、近代化を肯定的に受け止める人が多かった。それまでの時期と比べても、戦争で多くの人命が失なわれた時代は過去のものとなり、大きな地震の記憶も遠ざかっていった。台風や感染病は次々やってきたが、食生活や衛生環境は改善され、苦難は減少していくように見えた。収入が増え、道路や電気などの生活インフラが次々と整っていき、病気は治療できる例が増えていった。経済的な生活水準の向上とともに、教育機会も著しく改善されていった。
これを苦難という側面から見ていくと、生きるうえでの苦難が見えにくくなり、苦難に向き合うことが意識されにくい社会になったと言ってもよいだろう。苦難が個人個人でそれぞれ異なるもののように感じられてきて、苦難を分かち合い、ともに超えて行こうとする気持ちが薄れていったように思える。そのわかりやすい表れは、死が軽んじられていったこと、人間が死すべき存在であることを自覚する姿勢が後退していったことだろう
しかし、苦難が見えなくなる、見えにくくなるということは、苦難がなくなったことを意味するわけではない。見えない、見えにくいということは、精神の衰弱であるかもしれない。苦難に向き合ってこそ見える大切なものもまた、見えなくなってしまうからだ。ここで、近代化の進行とともに宗教がその影響力を失っていくという事態について考え直してみたい。近代化によって宗教の影響力が後退していくという事態は世界各地で進行した。近代化の先頭を進んでいるように見えた西洋社会では、一九世紀の半ば以降、多くの人々が宗教離れを経験し、社会が世俗化していくと感じるようになった。
世俗主義の広がり
分かりやすい例としてしばしば引かれるのはフリードリッヒ・ニーチェ(1844―2000)の「神は死んだ」という言葉である。これは、キリスト教の信仰の拠り所と考えられていた聖書の信憑性が疑われる事態とも対応していた。チャールズ・ダーウィンの『種の起源』が刊行されたのは1859年であるが、そこで述べられている進化論は神がすべての生物種を創造したという聖書の創世記の記述とまっこうから対立するものと受け止められた。地球球体説や地動説が科学者の間で受け入れられていき、聖書的な世界観を相対化する動向は十七世紀の科学革命の時代から進行していた。だが、社会的な影響力という点では、進化論の影響が格段に大きかった。
これは識字率の増大と世俗的教育の普及という社会構造の大きな変化が関わっている。以後、科学的な世界観が広まり、宗教的な世界観が後退していくという動向が顕著になった。確かに世俗的な知が普及し、宗教的な世界観の信憑性が薄らいでいくという事態は進行した。それを是とし、さらに押し進めていこうとする考え方が世俗主義であり、資本主義や社会主義と結びついて影響力を拡大していった。
だが、こうした変化によって宗教が決定的に無力化したと見ることは妥当ではない。米国の場合を見ると、この時期に聖書に基づくキリスト教の信仰を再建しようとする根本主義という潮流が現れ、20世紀を通じて支持基盤を広げていき、20世紀後半には福音派とよばれて勢力を拡張し、1980年代のレーガン大統領の時代以降、次第に政治的影響力を強めて来ている。
世俗主義によって見失われたもの
ここで省みるべきことの一つは、世俗主義の広がりの中で見失われたものは何かということである。とりわけ苦難に向き合う姿勢の後退ということを取り上げる。そして、ここで石牟礼道子の『苦海浄土』(1969年〜2008年)という作品の意義について考えてみたい。この作品は日本が高度経済成長を遂げ、近代化がますます進むと思われた時期に、その中で見失われようとしているものに目を向けた作品と言えるからである。
『苦海浄土』は近代がもたらした経済発展の裏面としての、公害や環境破壊という負の側面を描き出しているという点に注目すべき点があるのは確かである。近代化とは何だったのかを振り返る上で重要な作品であることの理由はまずそこにある。だが、それだけではない。『苦海浄土』は近代が忘れがちであった人々の苦難がもつ精神的な意義を示そうとしている。その側面について述べていきたい。
『苦海浄土』を読むことによって、人々は水俣病のために辛い生を送った人々の苦難を、如実に知って胸を痛める。しかしそれと同時に、痛みを負って生きる人たちが痛みを超えて願っているもの、支えとしているものにも触れることになる。呻きとも言えるような重く激しい苦難の語りと、苦難を超えるものへの願い、あるいは祈りの双方が読者の心を動かす。読者はそこに、生きるうえで忘れてはならない何かがあると感じるのかもしれない。
全集が「不知火(しらぬい)」と題されていることからも知れるように、石牟礼道子は熊本県にある不知火海とともに生きてきた人である。両親は天草の出身で天草に強い愛着を抱いていたが、子どものころからその対岸の水俣で過ごしている。作家は水俣病の苦難が露わになる過程で、その推移を見守りながら、「奇病」に苦しむ人びとと接し、被害を食い止め少しでもやわらげるべく、被害者らとともに行動した。そして苦難を負う人びとの魂の声音(こわね)を伝えようとした。それが『苦海浄土』三部作だ。ここでは、1969年に刊行された第一作『苦海浄土(くがいじょうど)――わが水俣病』を取り上げる。
「苦海」と「浄土」
この物語には宗教的な要素が色濃く漂っていることに気づく読者も多いことだろう。そもそも表題に用いられている「苦海」や「浄土」という言葉は仏教用語である。「苦海」は「苦の海となった不知火海」とも読めるが、仏教用語の「苦海」に親しみがある人にとってはそちらが先に思い浮かぶはずだ。
『岩波仏教辞典』では、「苦海」とは「〈くがい〉とも読む。苦しみの海の意。衆生(しゅじょう)が住むこの現実世界を〈苦界〉、すなわち苦しみの世界とみなし、それを海に喩えたもの」とされている。『法華経』や『華厳経』の用例が引かれ、仏が苦海に沈む衆生を救うという意味で用いられると書かれている。また、解脱坊貞慶(げだつぼうじょうけい)(1155〜1213)が著した『愚迷発心集(ぐめいほっしんしゅう)』の「むなしく苦海に溺(おぼ)れんよりは、急ぎて彼岸を欣(ねが)ふべし」という一節が引かれてもいる。
『苦海浄土』は七章で構成されているが、第一章「椿の海」だけに以下のようなエピグラフがついている。
「繋(つな)がぬ沖の捨小舟(すておぶね) 生死(しょうじ)の苦海(くがい)果(はて)もなし」
これはそれほど古くない「弘法大師和讃」からで、御詠歌講(ごえいかこう)で歌われるものだ。では「苦海浄土」という表題において、「苦海」と「浄土」はどのような関係にあるのか。「生死の苦海」を超えると「浄土」があるはずだ。ところが『苦海浄土』はもっぱら人々の苦難を描いているようにも見える。この書物は「浄土」をどう描いているのだろうか。すでに作者自身に答えがあるかもしれないが、私なりに考えてみたい。
「ゆき女きき書」
第三章「ゆき女きき書」に即して見ていこう。これは作品群の中でももっとも早い段階で執筆されたもので、読者の心を深く揺さぶる章である。『苦海浄土』は水俣病の歴史を生きる人々の個別物語、つまりエピソードを積み重ねた長編叙事詩、あるいは複合的な歴史物語と言えるものだが、この「ゆき女きき書」はこうした複合物語である『苦海浄土』を代表する個別物語と言える。ひとりひとりの苦難の物語を丁寧にたどり、魂の響きを伝える方法を作家が見出したという点で、「ゆき女きき書」は『苦海浄土』という歴史物語の方法論を確立したと言える章である。
坂上ゆきとその夫は息の合った夫婦だった。どちらも配偶者と死別して再婚した身で、漁に出ると見事に支え合っていたようである。ゆきは「魚の寄る瀬をよくこころえて」いて、そこまでくると深い藻のしげみをのぞき入って「ほーい、ほい、きょうもまた来たぞい」と魚をよぶ、「天草女の彼女のいいぶりにはひとしお、ほがらかな情がこもっていた」と、元気なときの様子が描かれている。そんなゆきが全身を痙攣(けいれん)させ、意識を失って入院してしまう。不知火の海との豊かな交流は永遠に失われてしまった。
あの昼も夜もわからない痙攣が起きてから、彼女を起点に親しくつながっていた森羅万象(しんらばんしょう)、魚たちも人間も空も窓も彼女の視点と身体からはなれ去り、それでいて切なく小刻みに近寄ったりする。
絶えまない小きざみなふるえの中で、彼女は健康な頃いつもそうしていたように、にっこりと感じのいい笑顔をつくろうとするのであった。もはや四十を越えてやせおとろえている彼女の、心に沁みるような人なつこいその笑顔は、しかしいつも唇のはしの方から消失してしまうのである。
孤独の深さと魂の輝き
これほどの病状でも、ゆきはおどけて見せる心意気を持っていた。しかし、その後のゆきの「心ぼそか。世の中から一人引き離されてゆきよるごたる。うちゃ寂しゅうして、どげん寂しかか、あんたにゃわかるみゃ」という言葉からもわかるように、心の中では深い孤独に沈んでいたことが描かれてもいる。入院中に流産を余儀なくされた悲しさも思い起こされる。
あんときのこともおかしか。
なんさま外はもう暗うなっとるようじゃった。お膳に、魚の一匹ついてきとったもん。うちゃそんとき流産させなはった後じゃったけん、ひょくっとその魚が、赤子(やや)が死んで還ってきたとおもうた。頭に血の上るちゅうとじゃろ、ほんにああいうときの気持ちというものはおかしかなあ。
うちにゃは赤子見せらっさんじゃった。あたまに障るちゅうて。
ゆきは赤ん坊のことを方言で「やや」と呼んでいる。水俣病のために「やや」を流産せざるをえなかった悲しい経験の語りを通して、ゆきの孤独の深さが語られていく。
また、作者は度々「ぐらしか」という方言を用いている。作者は別のある文章の中で、この言葉は「哀れでならぬ」という意味だと説明している(「亡国のうた」)。水俣病で苦しむ子供を世話する年寄りが、子どもの体に触れながら「ぐらしか、ぐらしか」と言う。それは「自分の魂をあやすよう」でもあると述べている。ここでも、流産した赤ん坊の魂と自分の魂の双方をあやすような音調が感じられる。
このようなゆきの語りの中では、さながら不知火の海は浄土のようだ。そこでは人の魂が輝いている。海は有機水銀による汚染で苦海を象徴する空間になった。それでもゆきにとっての海は、魂の尊厳を証する場であり続けているようである。いや、理不尽な苦難を受けた人びとが、その苦しみ、悲しみの中でこそ苦海に浄土をあらわす力を持つ。少なくとも作品の中では、そのような神秘的な変容が起きているように感じられる。
地域の宗教性の再活性化
この作品が描き出す人々の宗教性は、不知火海沿岸の人々の間で分け持たれてきた神仏や霊魂の信仰と深い関わりがある。その信仰とは、煩悩や浄土や苦海という言葉に表されるような仏教が一方にあり、他方に死者の霊や自然万物の霊との交流を尊ぶ伝統的な民間信仰、あるいはアニミズムとよばれるような信仰がある。両者が混じり合ったような信仰世界に作家は愛着を持ち、意図的にそうした信仰世界を前面に押し出してもいる。
また、作家は魂という言葉にこだわりをもっている。釜鶴松という老人の死と向き合う場面からも分かるで述べたように、作家は浄土に往生できない死者の魂魄(こんぱく)に、自身を通して言葉を発せしめている。それは生者においても同様であり、作家は死者にしろ生者にしろ、人々の魂の声音を伝えることを自らの使命と見なしている。石牟礼道子は現代の知的なシャーマンだと評する人もいるが、それは当たっているだろう。しかし、それはある特定の宗教の教えを分かち持つことによって、ともに苦難を超えようという道を目指すものではない。その意味で、キリスト教や仏教のような救済宗教の伝統とは距離をとるものである。
『苦海浄土』では水俣病という同じ社会的要因によってこうむった苦難に抗いつつも、政治的・社会的行動によっては表現しつくせないような祈りや念願が、ひとりひとりの魂の響きを通して表現されていく。この祈りや念願は宗教的なものであると作家も考えており、多くの読者もそう感じるのではないか。作者は作品を通して、私たちの心の底にある宗教的感性を目ざめさせようとしているかのようでもある。
『苦海浄土』から見た近代化
石牟礼道子の『苦海浄土』が示唆しているのは、近代化のなかで忘れられたり、軽視されがちだったある種の経験の次元である。苦難はないにこしたことはない。それは一面の真実であるが、しかし、苦難は避けがたくおとずれるものであり、また、その経験からこそ得られるものもある。死に直面することも、死別をはじめとする重い喪失による悲しみも苦難の一部であり、そこからこそ見えてくるものがある。
こうした視点は、かつて宗教が育んできたものであった。宗教においては、人間の弱さ、苦しみ、悲しみの経験を尊び、そこを通して見えてくるような何かが尊ばれていた。哲学者のカール・ヤスパースはそれを「実存」という言葉と結びつけて考えた。人間は死や苦痛、他者との葛藤や負い目のような限界状況に向き合い、それを通して、いかに生きていくかの核心的な問いに向き合う。そこでこそ、この世の欲望や快楽を超えた何かの意義と出会うと考えた。
近代化には生産力や効率性の重視がつきまとってきた。資本主義的な競争と結果主義、またそれと結びついて合理的な知的能力を重視する価値観がこうした社会のあり方と結びつている。こうした社会のあり方に対する不満や違和感が、現代世界では近代化に伴う進歩の側面に対立するような方向を後押ししている。ある時期、根本主義や原理主義とよばれたような宗教的な動向は、このような思想動向と歩調を合わせているところがある。
近代とある種の宗教的な動向とのこうした分断状況が、近代化の展開の後に人類社会が直面している困難の一つの大きな要因と考えることもできる。この隘路(あいろ)を脱していくために、石牟礼道子の『苦海浄土』が示したような洞察は一つのヒントを提示しているように思う。