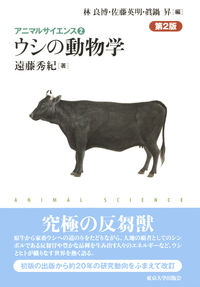――つぎは家畜についてお聞きしたいのですが、家畜(=人間が交配をコントロールする動物)というものはいつ頃生まれたんですか。
時間をたどると、図抜けて古い家畜はイヌになります。イヌはオオカミの家畜化ですね。他の四足歩行の家畜はさかのぼっても1万年くらいですが、イヌは3万年以上前だと思います。ただ、イヌは人間が生きていくための営みをサポートしてくれる助っ人だったので、他の家畜とはちょっと切り分けた方がいいかもしれません。
いまでも、たとえばイノシシ猟なんかにはイヌを使います。イノシシは人間がいくら追いかけても逃げちゃうだけなんですけど、イヌがいれば人間の都合のいいところに追い詰めてくれるんですよ。なんせ原種がオオカミなので、狩猟能力に非常に長けているわけです。このどう猛な獣をどう手なずけたのかというのは問題ですけど、とりあえず、ヒトの暮らしを物理的に助けてくれるという役どころだったと思います。
――なるほど。
本格的な家畜化は1万年前くらいからで、それこそイノシシからブタをつくったり、ヤギやヒツジの野生原種を品種改良して飼うようになりました。ちょっと遅れてウシですけど、ウシでも9000年から1万年くらい前には家畜化していたと考えられます。
家畜化の理由はいくつかに分けられるんですけど、初期から必ず食べてはいたと思います。ウシ、ヤギ、ヒツジは交配すればミルクも採れます。つまり個体を殺さなくても、スーパーマーケットじゃないですけど、栄養物が手に入るわけです。それと畜力ですね。ウシやウマ――ウマはだいぶ最近になりますけど――は重いものを運んだりするのに役立ったでしょうから、そういう動機で飼い始めたのでしょう。
――人間が生きていくための糧になったり、糧を得るのに役立ったりという即物的な存在だったわけですね。
なのですが、意外に早く、それには当てはまらない関係も成立していた可能性が高いんですよ。たとえばエジプトなんかだと、イヌもネコもウシも宗教的な対象になっていて、異界と人間界を結ぶ神の使いだとされていました。もっと時代をさかのぼってメソポタミアよりさらに前には、ウシは豊かさや子だくさんの象徴として称えられていたのではないかと言われています。牛の角が三日月の形をしているので、月ということで女性にたとえられていたと推測する人もいます。ただ、これは文字の残っていない時代の話なのでわからないこともいっぱいあるんですけど。

イヌも、現代のような愛玩犬はいませんが、狩猟を助けるイヌと人間の間には心のつながりができていたはずです。いまでも、猟犬を飼っている人たちは、時にとても厳しい態度でイヌと接しますよね。しっかりと手なずけ、躾けることで、自分たちの世界の中に受け入れていく。ペットショップでお金だけ払って連れてくるのではなく、そういう関係づくりをずっと真剣にやってきたわけです。
――まさに物心両面での関係が早くからあったと。
一気に時代が下りますけど、それが産業革命後になると、宗教的対象としてはおろか、もう畜力としてさえ必要なくなってくる。現れるのは資本主義です。いかに肉を効率的につくるか、いかにミルクを、卵を手に入れて、二次産業、三次産業に従事する人びとに食糧として売るか、という価値観へと移っていきました。一方、そうやって社会が物的に豊かになっていくのと並行して、さまざまな動物をペットとして育種するようになります。

江戸時代の日本は世界的にも類を見ないほど、豊かなニワトリの育種をやっていました。同様のことがヨーロッパではイヌで起きていて、愛玩犬というものが多様に生み出されます。その過程には、たとえばヒツジを管理する牧羊犬のように、実務的な役割をもったイヌがいたと思うんですけども、やがてそういった目的のためではなく、ただ楽しみとして動物を飼うということが行われるようになりました。家畜化の理由の最後が、この愛玩です。ただ、さっきも言ったように、動物が人の心の潤いになるということ自体は、文明の誕生よりも前からあったんじゃないかと思います。
宗教と動物
――動物を宗教的な対象としても見ていたということは、肉にしたり、乳や卵を採るためではなく、たとえば何らかの儀礼のために家畜化していた、ということもあり得ますか?
諸説ありますけれど、文明が生まれたばかりの頃に、宗教儀礼のためだけに育種したっていうのはちょっと考えにくいですね。時代が下って闘犬なんかになると――闘犬は宗教儀礼ではなく娯楽ですけど――、気性の激しいイヌ同士を掛け合わせるということをやっていたと思います。ニワトリの場合は闘鶏といいますけど、これは多くの場面でギャンブルですね。日本では平安時代の頃から、ヨーロッパではもっと前から成立しています。闘犬や闘鶏はいまで言うと相撲やプロレスみたいなものだったはずなので、吠え声が激しいイヌをつくるとか、見た目が精悍なニワトリをつくるといったことは当然やっていたと思うんですよね。
話を宗教に戻すと、特定の宗教儀礼のための品種をつくるというのはなかったと思いますが、そこで飼われている動物を信仰の対象にするということは多かったと思います。エジプトのネコへの思い入れなんかはすごくて、ミイラを作ったりしていますよ。あの自分勝手さと、何だかよく分からない動きが、神様っぽく見えたのかもしれませんね。
――わかる気がします(笑)
その後、新しい宗教ができてくると、イスラムがブタを食べないとか、ヒンズーがウシを殺すことを禁止するといった、いろんなタブーが生まれます。そういったこととも絡んでくるので、家畜は思想・信条としても面白い研究対象だと思います。
――イスラームでブタが禁止されていたことで、多くのムスリムがブタの寄生虫の感染症にかからずにすんだというのは今回はじめて知りました。
教義上のタブーが食べ物に向かっているケースって、本当の起源が分からないんですよ。それくらい古くからあるし、そもそも、タブーにした理由について語られていない。手品の種明かしと同じで、理由を言っちゃうとありがたみがなくなるのかもしれません。だって、神がブタを禁止したのは寄生虫がいて危ないからだって言っちゃったら、それを理由に人々は求心・結束なんてしないじゃないですか。だからうやむやになるんだと思うんですけども、宗教上の食のタブーは、ほぼすべて、法律がなかった時代の公衆衛生の規範として考えることができます。
――面白いですね。
昔、日本の学問にもう少し余裕があった頃には、そういう研究をする人が多少はいたんですよ。宗教の教義と公衆衛生みたいなテーマを本気で研究している人たちが。私が社会に出る頃から日本の学問はどんどん貧しくなって、すぐ成果を出せとか特許を取れとか経済に貢献しろとか管理するようになって、学問の中身がつまらなくなってしまいました……。