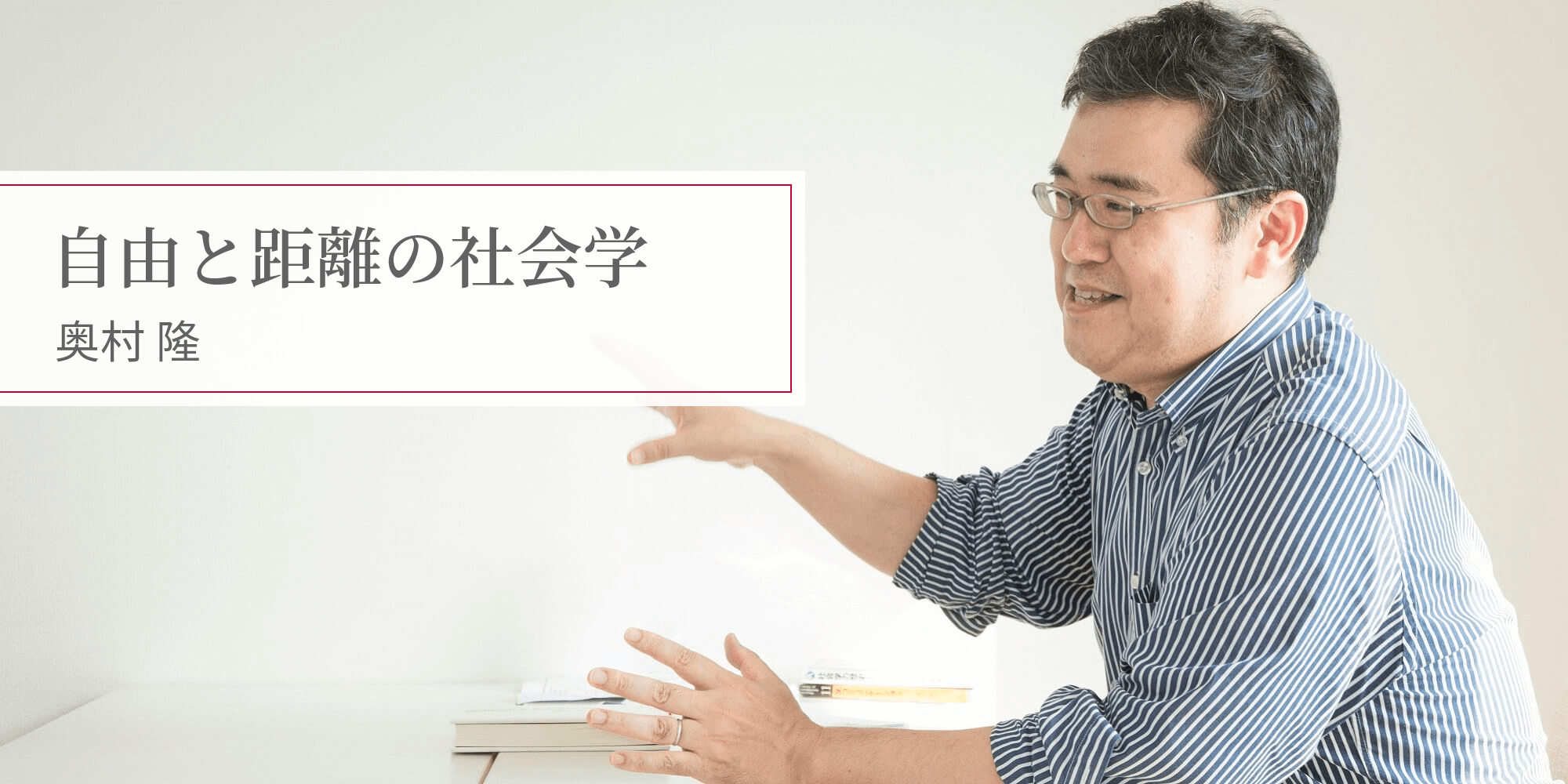――同情によって人びとが同じになることをめざしたフランス革命に対し、アメリカ独立戦争は違う人同士が距離を取って話し合うことで合意点を探っていった。人間は一つになれるというフランス革命の思想はたしかに魅力的ですけど、独立戦争の方が現実的と言うか、コミュニケーションとして実践的だなって思いました。
それに関連して言うと、社会学の中でコミュニケーションを扱う端緒を開いた人物にゲオルク・ジンメル(1858-1918)という人がいます。ジンメルはユダヤ人で、ベルリンの人でした。裕福な実業家の家庭に育った、素晴らしく教養のある人だったようです。
ジンメル自身はすごく優秀だったんですけど、大学での専任職につくことができたのは死ぬ前の数年間だけで、あとはずっとベルリン大学で、私講師っていうのかな、一般の人を相手に講義をして講義料を取るという生活をしていたようです。すごく優秀なユダヤ人なのに、いや、優秀だからこそですね、教授になれなかったっていう人です。
――ユダヤ人ということで差別されていたわけですね。
彼は1903年の「大都市と精神生活」という講演の中で、コミュニケーションにかかわる距離の話をしています。都市の人間関係は、一見、解体しているように見える。人と人とは深く分かり合わない。とても距離があり、このままだとばらばらになってしまうんじゃないかと思われる。それに対して、地方都市や田舎ではみんながお互いに知り合いで、感情的にもすごく近いところがある。
――いわゆるムラ社会的な関係性ですよね。
そっちの方が人間的でいいように思えるんですけど、その田舎の態度をもってベルリンのような大都市に来たらどうなるか。大都市にはさまざまな刺激があり、出自も考え方も全然違う人たちがいる。そういう人たちと田舎や小都市のような態度で接していると、すぐに疲れ切って付き合えなくなり、やがて互いに嫌悪するようになる。すると、暴力的なことが起きてしまうかもしれない。

それに対して、人と人が深く関わり合わない大都市の関係はどうか。「よく分からないやつだ」という、かすかな嫌悪や反発はそこにもある。でも、それは激しい憎悪にまではならない。「こいつ、なんか違うな」「いけすかないな」と思ったら近づこうとしないから、逆に一緒にいることができる。距離を取るからこそ、違う習慣や違う考えを持っていても、大都市という場所を一緒につくっていくことができる。ここにもしも田舎の態度を持ち込んだら、嫌悪と、憎悪と、完全な無関心に支配されて、大都市は完全に崩壊してしまうだろう。そんなふうにジンメルは言うんですね。
――現代の東京にも当てはまりそうな話です。
ジンメルは、大都市の人は感情的に接するのではなく、知性で接するという言い方をしています。そうすることによって、冷たいんだけど、いろんな違う人と一緒にいられる。田舎ではみんなと同じじゃないと排除されたりするけれど、ベルリンではドイツの田舎から来た人も、ロシアから来た人も、ポーランドから来た人も、ベルリンにずっといる人も、ユダヤ人も、それぞれの個性を持ったままでいられる。ジンメルは「個人的自由」という言い方をしていますが、それぞれの人が自由を持って生きていくことできる。ベルリンのそういう点を彼はすごく評価しています。
――ユダヤ人だということで差別を受けながらも、大都市の希薄な人間関係を評価していたんですね。
それがなければ逆に生きていけないっていうか。ベルリンのような大都市でマイノリティーとして暮らすには、冷淡かもしれないけど、他者との距離を持つことが生きるすべになる。そういう生活経験が、恐らく、彼の中に蓄積されていったんだと思います。
貨幣と仮面
コミュニケーションというと多くの場合は、近づけば近づくほど、結びつけば結びつくほどいいんだっていう感じを持つと思うんですけど、ジンメルの言うように、結びつくことによって逆に決定的な亀裂が生じてしまうということもあると思うんです。反対に、分離しているからこそ、距離を取るからこそ、結合することができる場合もある。都市のかすかな嫌悪は、逆に人を結びつけている。距離を取るということが、普通なら結びつかない人同士を結びつかせることができるんだと、ジンメルは考えていたように思います。
――違う人同士であっても、距離をとることによって、決定的な分裂やそこから生じる暴力を避けることができると。
その考えはジンメルの貨幣論からも窺うことができます。
――貨幣、ですか?
貨幣というものがあることで、たとえばある本をその著者に会わなくても手に入れることができる。もしも貨幣がなくて物々交換だったら、本を手に入れるために直接会うことで「こんな人が書いたのか」といった、余計なことまで知ってしまうことになりますよね。この人のこと嫌いだから読まない、逆に、こいつにはこの本渡さないみたいなことも起こりうる。
でも、貨幣で取引すれば、商品はつくり手の人格とは切り離される。たとえばデザインした洋服がかわいいとか、育てた野菜がおいしいといったように、つくった人の人格とは関係なく結びつくことができる。貨幣という仲立ちがあるから、テーブルが間にあるのと同じように、距離をとって、全然違う人同士でも結びつくことができるわけです。

これも一般には、人格と人格が結びつくのが一番いいと考えると思うんですけど、そうすると結びつき得る人の範囲がものすごく狭まってしまう。人格と人格を結びつけようとすると、知れば知るほど嫌悪してしまうということも起こる。貨幣による結びつき、それはすごく淡い関係ですけど、淡い関係だからこそ多くの人を結びつけ、しかも、結びつくことによる嫌悪や決定的な亀裂を防ぐことができる。
――なるほど。
ジンメルは「秘密」についても言及しています。相手のことを知らないということが、人と人を結びつける。私たちはお互いを知らないからこそ一緒にいられる。あるいは、知らないからこそ魅力的になる。相手のことを全部知ってしまったら、多分もう一緒にはいられない。こんな嫌なところがあるんだとか、なんだこの人この程度の人だったのかって。
その例としてジンメルは「社交」をとりあげています。楽しいおしゃべりをしようというときに、その人の持っている深刻な悩みとか、財産がある、こんな地位にいる、仕事ができるといった自慢なんかが入ってくると社交は台無しになってしまう。だから人々は、個々の人格は取っておいて、お互いにただの人間として、もしかしたら仮面を付けて、おしゃべりを楽しむ。そのときに人は、違うもの同士として一緒にいられると。
――社交で仮面をつけるのはそういう理由だったんですね。その人の属性というか、外見や地位といったアイデンティティに関わるようなものを隠して、ただの出席者同士として交流する。
彼は「平等であるかのよう」な「お芝居の民主主義」という言い方をしていますけど、たとえフィクションであっても、そこでは違う人同士が関係を結び、対等に社会をつくっていくことできる。そこには自由もあるし、個性もある。そういう社会の姿を想像するわけです。
フランス革命が目指したようにみんなが一つになるべきだとか、人と人の距離は近い方がいいんだっていうのは、わりと普通の考え方だと思うんです。それに対してジンメルは、むしろ距離をとり、関係が希薄になるからこそできることがあると考えた。逆にそっちの方が、一人ひとり違ったままで、一つの社会をつくることができる。差異を持ったまま一緒にいられるというところに、より自由な社会の姿を見ていたんじゃないかと思います。