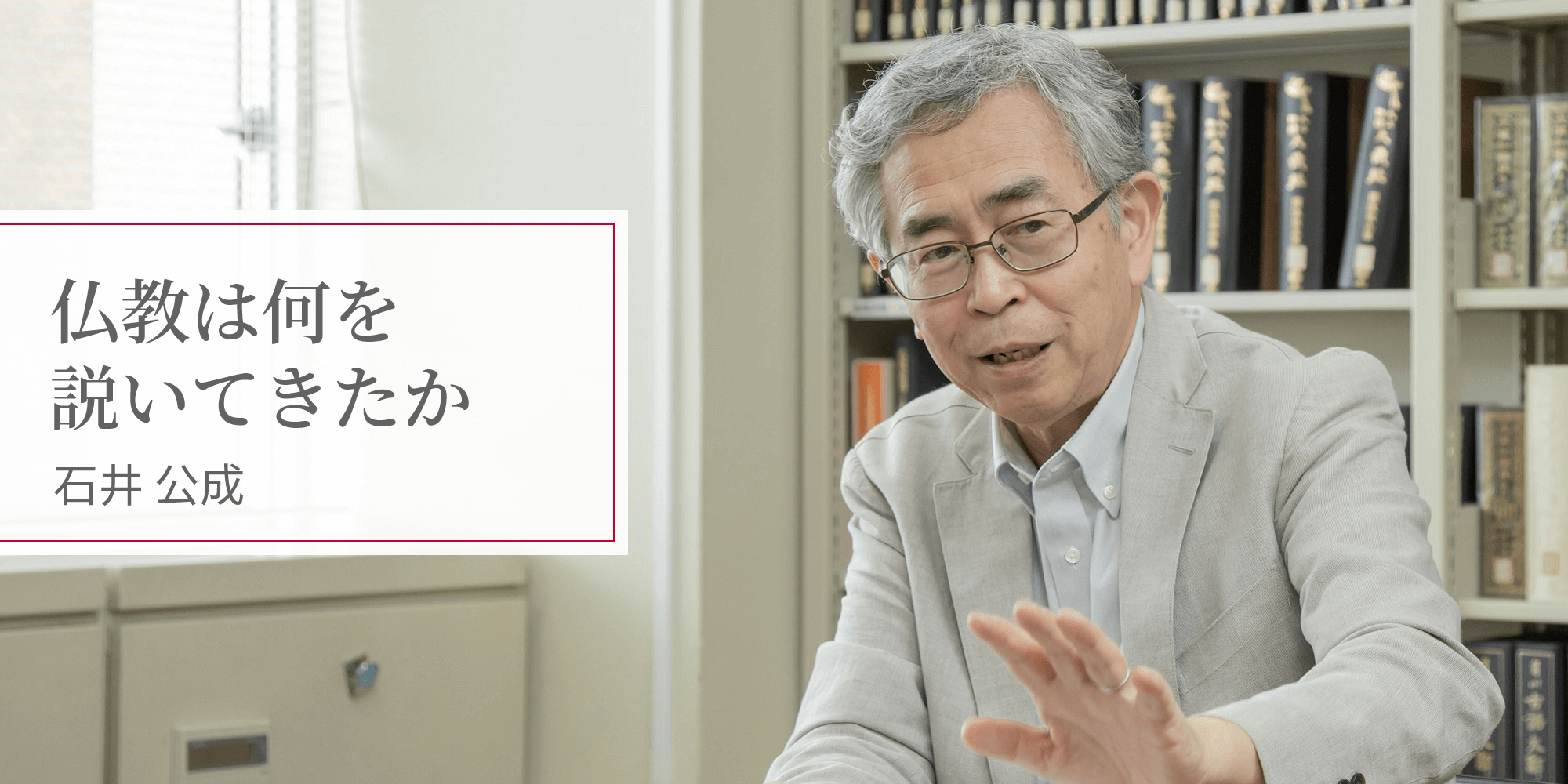――まずは当時のインドの宗教事情といいますか、仏教がどういう状況の中で生まれてきたのか、といったあたりから教えていただけますか。
インドにはもともと土着のいろいろな民族がいたわけですが、そこにアーリア民族と呼ばれる人びとがカスピ海の方からやって来るんですね。この人たちは『ヴェーダ』を聖典とする宗教、いわゆるバラモン教を信仰していました。
バラモン教ではバラモンと呼ばれる司祭者が呪文を唱えたり神にささげものをしたりする儀礼によって、死後の生天その他の願いがすべて保障されるんです。ところが、世の中が少しずつ豊かになり商品経済が盛んになると、そんな儀礼が本当に効くのかという疑問をもつ人が現れてくる。
ちょうどその頃に、生きとし生けるものはすべて無限に生まれ変わるという輪廻の思想が発達してきます。日本人はその恐ろしさがあまり分かっていないから、商店街で「サンサーラ(編注:輪廻という意味のサンスクリット語)」という名前の美容室を見かけたりしますけど。たまたま今回は大金持ちの美男子として生まれたとしても、来世はゴキブリかもしれない。これが永遠に繰り返されるわけですよ。
――それは恐ろしいというか、考えるだけでもうんざりしますね。
すると、来世で幸せになるというより、輪廻そのものから抜け出したい。それが果たしてバラモンの儀礼によってできるのか、と疑う人たちが出てきた。それが自由思想家、シュラマナと呼ばれる修行者なんですけど、インドの場合、地方の発音では言葉の最後の母音が落ちるんです。そうするとシュラマンとなり、これが中国で沙門(しゃもん)と音訳されました。
沙門は出家した修行者・思想家のことであって、この人たちがいろいろな説を唱え出した。すべては運命である、すべては物質だけである、すべては偶然である、すべては神が定めた、いや、これこれだと決めることはできない、などと。そうした中で、因果(原因と結果)というものがあるんだ、と言ったのが仏教。つまり仏教というのは、ヴェーダの権威に逆らって出てきた「新興宗教」の一つだったわけです。
――具体的にはどんな点が違っていたんですか。
バラモン教ではバラモン(司祭者階級)、クシャトリア(王族階級)、バイシャ(庶民階級)、そして下層な仕事をするスードラという階層が定められていて、どの階層に属するかは生まれによって決まるのですが、仏教はこれを認めません。人は生まれによってバラモンになるのではない。何をするかによって尊い人になり、また穢れた人になる。もう徹底的に行い主義で、血筋は関係ないわけです。
――当時のインド社会では革新的な教えだったんですね。
言い換えると、『ヴェーダ』を信仰する主流派とは常に緊張関係にあった。仏教は温和なので暴力的な反対運動はやらないけれど、実はインド社会のあり方を根本から否定したわけですよ。インドの神々も拝みません。そのせいで、仏教は周りには広まったけど、肝心のインドでは滅びてしまった。
――なるほど。
大学の講義で、インドの人口10億のうち、仏教を信じている人はどれくらいいると思うって聞くと、学生たちは5億とか、6億とか言うんですね。でも、イスラム教が入ってきたことで、インドの仏教は一回滅びちゃったんです。現在では仏教信者もある程度いますが、これはインド憲法の草案を作成した最下層出身の政治家、アンベードカルがカースト制否定を呼びかけ、20世紀半ばに50万人ほどの人たちとともに仏教に集団改宗したのがきっかけです。
しかも、信者が急激に増えて何百万、何千万と言われるほどになったのは、アンベードカルが亡くなってからインドに渡った日本の僧侶たちの活躍によるものであって、近年のことなんです。ただ、イスラムが侵入してきても、『ヴェーダ』は生き残った。バラモン教がインドの土着信仰と結びついて庶民化されたのがヒンドゥー教ですが、これは現在までずっと生き残っているわけです。
部派仏教と大乗仏教
――仏教が一度滅びちゃう前にお話を戻しますと、仏教には「部派仏教」と「大乗仏教」というのがあるそうですが、それぞれができた経緯はどのようなものですか。
インドといっても広いので、地方によって習慣や考え方が違うわけです。たとえば、初期の仏教教団ではお坊さんはお金をもらってはいけないとなっていたのに、西の商業が盛んな地方では、いや、執着しなければもらってもいいとかなる。
教理の面でも、仏教独自の立場をあくまで守り通そうという人たちと、インドの伝統思想や社会のあり方にちょっと妥協しようという人たちが出てくる。そうやって少しずつ分かれていってできたのが部派仏教です。
――部派ごとに考え方が違っていたんですね。
微妙にですけどね。そして、部派仏教が発展していくと、ブッダはお釈迦様一人だけだということになります。元々は修行して悟れば誰でも「ブッダ」と呼ばれていたんですけど、部派仏教ではお釈迦様が絶対的に偉くて、仏はお釈迦様一人だけ。他の人はどんなに修行を積んでも仏の手前までしか行けない。仏になる前の存在が「菩薩(ぼさつ)」ですが、何回も生まれ代わって修行していた菩薩もお釈迦様一人だけ。
それが広まると、今度はそれに不満を持つ人たちが出てくる。仏に会いたい、あるいは、自分も仏になりたい。そこで、東や西の世界に仏がいて会えるとか、誰もが菩薩として修行して仏になることができるとする大乗仏教が起きてくるわけです。この大乗仏教で面白いのは、発生してまもない頃から「書写せよ」と言っていたことですね。
――お経を、ですか?
はい。部派仏教では全員が出家した「プロ」ですから、お経はすべて暗唱です。そもそもお経は韻を踏んだりしていて、覚えやすいように作られているんです。ところが大乗仏教は最初から「書写せよ」なんですよ。書き写して広めろ。
――読み書きできる人にとっては、そっちの方がとっつきやすいですね。
そうすると、面白い現象が出てくる。部派仏教を信仰しているところでは、舎利、つまりお釈迦様の遺骨が納められた仏塔があちこちにあって、僧も信者もそれを拝むんですね。仏塔はもう仏と同じなんです。
それに対して大乗の方はなんと言ったかというと、お釈迦様は般若(はんにゃ)、般若は智慧という意味ですけど、これを悟って仏になった。般若は仏の母である。つまり、般若の教えが書かれている経典自体が仏と同様というか、仏以上に尊いため、この般若経典を書写して供養せよというわけです。
――なるほど! 面白いですね。
経典が仏なら、わざわざ塔を拝みに行く必要はないんです。お経を書き写してそれを供養したり読誦したりすれればいい。『般若経』、『法華経』、『涅槃経(ねはんぎょう)』といった大乗経典はどれも経典を尊重しろと言っています。

特にすごいのが『涅槃経』で、すべての生き物の体の中に「ブッダのダートゥ」があると明言します。「ダートゥ」というのは、要素、原因、鉱石などの意味を含む言葉ですが、体の構成要素といったら骨でしょ? つまり「ブッダのダートゥ」という言葉は、仏となる原因といった意味だけでなく、「仏の骨」という意味を含むんです。すると、あなたの体の中に仏舎利がある、あなたは仏塔、つまりは仏にほかならないということになるんですよ。
――自分自身が仏であると。
だから塔を拝む必要はない。この「ブッダのダートゥ」という生々しい語が、中国風に「仏性(ぶっしょう)」と漢訳され、仏性説が東アジア諸国に広まっていきます。インドでは、すべての人は如来を内に蔵した存在だということで、「ブッダのダートゥ」よりも「如来蔵(タターガタ・ガルバ)」という表現の方が主流となりますが、この如来蔵思想も東アジアで広まっていく。
とにかく大乗では経典が最も尊い存在であって、仏塔より『般若経』をこそ供養すべきであって、『法華経』なら『法華経』を置いてあるところが仏塔と同じということになる。
――お釈迦様という「個人」よりも、彼を仏にした般若の方が尊い。
そうです。あるいは、真理としての仏の方が偉いということになる。つまり、お釈迦様が亡くなっても教えは残る。その教えに従いなさい。教えこそが真理なのだから、真理を尊びなさい。その真理が大乗経典に説かれている、というわけですね。
この立場が強まると、インドに生まれて80歳で亡くなった釈迦という人は、真理が形を変えて現れた仮の姿に過ぎない、ということになってくる。そして、その真理としての仏の本質はあなたの中にもある。
私の体の中にも仏の本質、つまり仏性があるのであれば、私と仏にはなんの違いもない。大乗はそういう方向へと進んでいったんです。ただ、実際に煩悩にまみれていますので、そこが問題になるのですが。