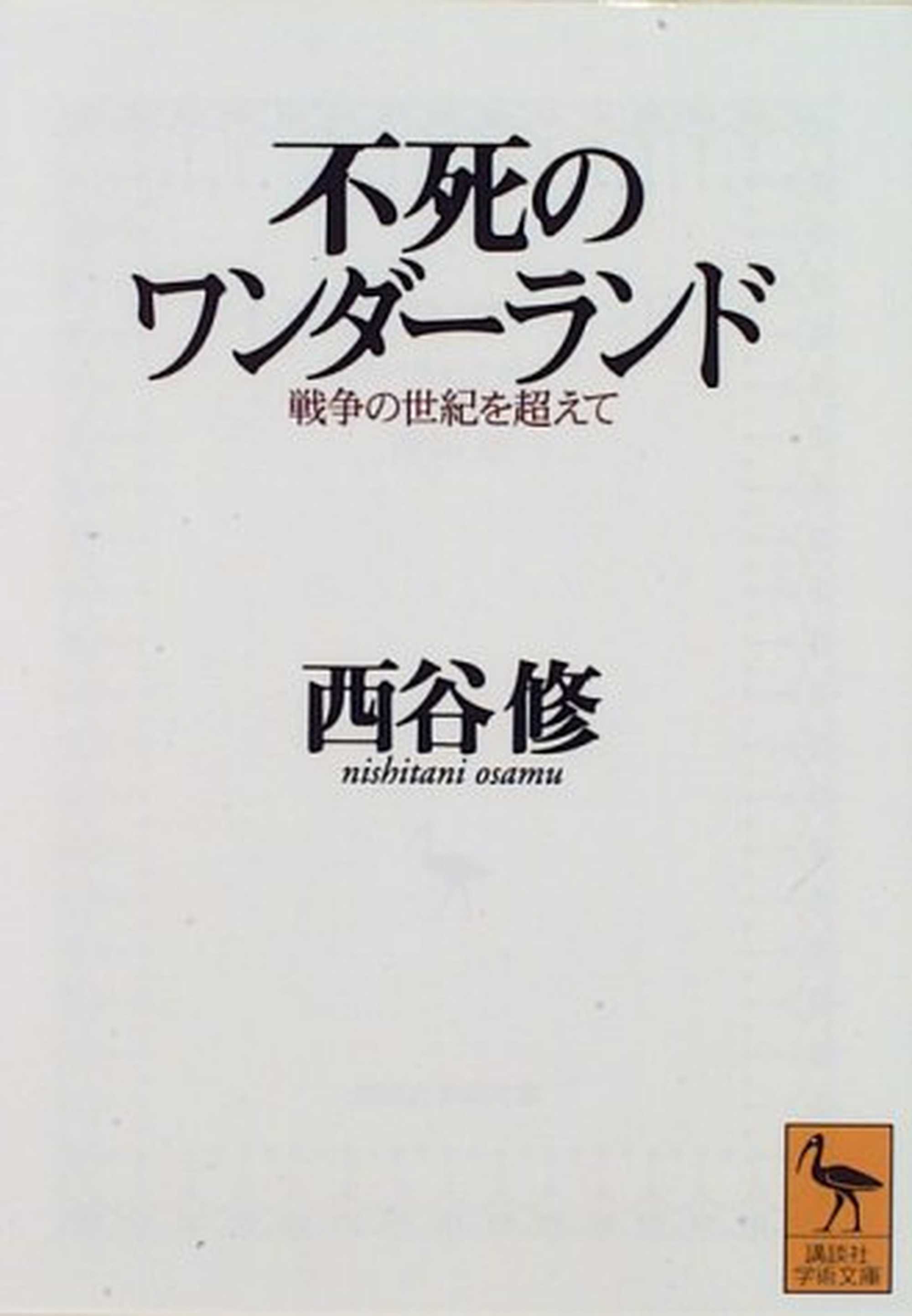ロシアのウクライナ侵攻が始まってすでに一年が経った。
この侵攻以後、世界は新たな混乱期に入ったと言われる。第二次世界大戦以前のような状況だと。
たしかに、「侵略者」がいるから戦うのは当然だ、とばかり「戦争はしなければならない」という空気が広がっている。いや、「侵略」が戦争であって、それに対する「抵抗」あるいは「抗戦」は違う。戦争を仕掛けてくるのが邪悪な国なのだ、ということなのか。しかし「敵」を立てて集団で(国同士で)戦うのが「戦争」である。別の言い方をすれば、「戦争」にはつねに集団としての相手がいて、単独ではできない行為だ。だから「桃太郎の鬼退治」(正義の戦争)も戦争であることに変わりはない。
じつは世界中が同じ「戦争」のうちで一つになったのが「世界戦争」であり(歴史的には第一次世界大戦と第二次世界大戦とに分けられているが)、その「世界戦争」を経験して以後、「戦争はしてはいけない」というのが、人間世界(国際社会)の大原則になったはずだった。この戦争は「最終兵器」も生んだが、その核兵器のもとで戦争になれば「人類の破滅」だからだ(グローバル化した世界では、どんな戦争も世界戦争になる条件を秘めている)。もちろんそれで実際に戦争がなくなったわけではないし、とりわけ軍事に自信のある国は、何とか理屈をつけて戦争を正当化し(「正義の戦争」)、「抑止力」という名の軍事圧力でものごとを解決しようとしてきた。だがそれでも、人類社会ということを考えたとき、ともかく国家間戦争はしてはいけない、というのが大原則になったはずだった。
ところが、国際法秩序が脅かされている、侵略者を「勝たせてはならない」、そのためには戦わなければならない。そんな現実的危険の前に、戦争を準備しなければならない、という風潮が一般的になってきた。ロシアのウクライナ侵攻は、そんな脅威の現実化なのだ。だから、これを許してはいけない、明日は他の国も侵略されるのだから、と「正義の戦争」の宣伝に世界が動かされる。
とはいえ、そのような傾向に傾いているのはいわゆる「西側」世界だけである。その他の国々は「侵略戦争」を否定しても、「西側」に同調するのは避けようとしている。「西側」は自分たちの正当性を主張し、その他の国々に同調を迫っているが。
たしかに、「西側」の見方に立てば、今は「世界戦争」前夜のようである。共通の「脅威」の前に軍備を増強し、先制攻撃能力が必要だとさえ言う(とくに日本政府)。まさに、かつて、軍縮会議や不戦条約の試みが水泡に帰したのと同じように、「明日は戦争」という気配だし、いや実はもう始まっているとばかり、世界の分断に余念がない。民主主義国と専制主義国との戦争はすでに始まっているのかもしれない(フランスのエマニュエル・トッドが「第三次世界大戦はすでに始まっている」と言うように)。
いったい何がどうなっているのか?
ここで呈示できるのは、現実の混乱(あるいは蔓延する惨劇)への直接の処方箋ではない。私は政治家でも、国際機関の責任者でもないからだ。ただ、起こっている事態の意味や構造を照らし出し、それに対して人びとがどう対処すべきか、その判断に資するベースを示すことだけだ。
戦争と人間を考える
私はずっと戦争のことを考えてきた。べつに戦争にとりわけ興味があったからではない。もとはと言えば20世紀の世界を「限界状況」として生きた作家・思想家たちの書いたものを研究していたが、彼らの生きた時代が「戦争と革命の世紀」とよばれる時代であり、とりわけ世界全体が戦争の坩堝(るつぼ)に呑み込まれた時代であったことから、戦争とは何かを避けがたく考えるようになったということだ。そのときにはもちろん、日本の作家・思想家たちの書いたものにもあたってみた。日本も地球の反対側から「同じ戦争」に関わっていたからだ。
20世紀の戦争とは基本的に「世界戦争」だった。世界戦争と一口で言うが、その意味は多義的である。というよりむしろ「全体的」である。これはたんに地理的な意味で世界全体を意味するだけではない。哲学では「世界」という概念が使われるが、それが主要なタームとなったのもじつは20世紀である。
フッサールは「生活世界」を語り、ハイデガーは人間(現存在)を「世界内存在」だと規定した。その場合「世界」とは人間の生きる環界、あるいは人間のもつ関係の総体、もっと的確に言うなら人間が存在するその「実存の厚み」のことである。「世界戦争」というのは、戦争が一地域での国家間抗争ではなく、それが国際関係や経済利害を通じて連鎖的に世界全体に広がり、あらゆる国を巻き込んだ。そのうえ、とりわけ主要国は産業化しており、人びとの生活は国民経済の仕組みの中にすっかり取り込まれていて、国の戦争はそのすべてを動員して行われる「全体戦争」だった。そのため戦争は、それぞれの国の人びとの生きる「世界」をも丸呑みにしたのである、そのような複合的な意味で戦争が「世界化」したということである。
もちろん歴史学では「第一次世界大戦」「第二次世界大戦」と事後的に分けて言う。ただし英語では"World War I"、"World War Ⅱ"である。つまり「世界戦争Ⅰ・Ⅱ」だ。だが、「世界戦争」というのがどのような名づけ、あるいは規定なのかを考えると、その内実は上記のような「世界中が戦争に呑み込まれた」という事態であり、歴史的事象としては、それは二波にわたって起こったということだ。その二波がそれでも一続きであるのは、第一波は関係国が「それと知らず始めたら世界戦争」だったが、第二波は、どの国も「そのつもりで準備した(わかっていてやった)世界戦争」だったということに示されている。要するに、この時代に起きたのは「世界戦争」なのである。
最初の著書『不死のワンダーランド』は、この時代を限界状況として生き、その限界との格闘を書かざるをえなかった(これはどういうことかと悶え考え、言葉にせざるを得ない、そして生きる――でなければ死ぬ――のが人間の生だ)作家たち、ジョルジュ・バタイユやモーリス・ブランショ、エマニュエル・レヴィナス、マルグリッド・デュラスといった人たちの著作から、その「経験」の核心(といっても核は崩壊すると放射性物質を放出し続けるが)を洗い出し、その「効果」を描き出すものだった。それが「死の不可能性」というテーマに集約される。
その際、時代の問いの共通の参照項となったのはマルチン・ハイデガーである(それにジャン・リュック・ナンシーの換骨奪胎が加わる)。そこから、(古から)現代にまでつながるテーマが浮かび上がる。「人はひとりでは死ねない」、「死は完結しない」、個的な主体の未完了、死は共有される、そして生も、共同性とは分離と別のことではない…、言葉と死の関係、コミュニケーションの実相、信はいかにして生じるか…、といった存在論の基底を破るような「ある(生きてある)」ことの相が洗い出された(と私は考えている)。そしてこのような限界状況を生み出した「世界戦争」とは何だったのか、どのようにして生じたのかを考えることになった。
「世界戦争」とは何だったのか?
まず戦争とは何かを「人類学的」に考えてみた。戦争とは人間の集団的行動の特異様態だからである。特異というのは、戦争はすべてを呑み込み、それまでの集団(共同体)のあり方を、他の集団との戦いのなかですべて坩堝に入れ、作り変える、そんないわば集団を超えた出来事だからだ(「平時」に対する「非常時」)。そこで秩序が更新され、新たな価値や力のあり方が鋳直される。命の消尽を通して、物語が英雄を讃え、哀歌が犠牲を悼む。じつは「考える」ことさえそこから生じたのかもしれない(これについては別途扱おう)。
しかし、集団間の抗争がいつか「世界戦争」になった。それはどういうことなのか、なぜなのかを考えると、ここ五世紀あまり展開され、現代世界を形作ってきた「西洋の世界化」あるいは「西洋による世界統合」という事態に思い到らざるをえない。それまで、広域に展開した戦争(たとえば一二世紀のモンゴルの遠征)は、世界全体を統合するというヴィジョンをもっていなかったからだ。
一六世紀以来、「西洋」(これについては後で正確に規定しよう)諸国は大西洋を西と南に超えて地球上の他の地域に進出し、「発見」し「到達」し、征服し、あるいは植民地とし、各所を支配下に置き、そこを西洋式の制度システムのなかに統合してきた。「西洋」自身はみずからを「文明的」「近代的」と規定していたから、それは世界の「文明化」であり、「近代化」とみなされた。
このプロセスは世界の「未開」の地域に「文明」をもたらすはずのものだったが、その基礎には「野蛮」な地域のキリスト教化(「罪=因習」からの「解放」)があり、とりもなおさずそれが「文明化=近代化」の端緒だとされた。
一方、「西洋」世界内部では「宗教(キリスト教)」は棚上げされ、「現世(地上の国)」は合理的・技術的に物事が進められて、内部の戦争を抑止して外部への展開のドライブとなる国家間秩序(ウェストファリア体制)が作られた。そして「海の彼方は自由」という原則のもと、西洋諸国は世界に展開し領土を広げてゆくことになる。このプロセスで「戦争」は国家間戦争としての規範性を得る。そしてこれ以後起こる戦争は、多かれ少なかれ「西洋の世界化」言いかえれば「西洋が世界になる=全世界が西洋化する」プロセスの一局面という意味合いをもつことになる。
そのことを意識化したのがヘーゲルの全体性の哲学である。デカルト以来の近代哲学は基本的に、近代的主体の自己把握(自己解明)といった性格をもっていたが、ヘーゲルはそれらの試みを統合して、「精神の自己実現」の現実を記述する論理として「絶対知」の哲学を作り上げた(『精神現象学』)。それは「精神」が「全世界」として自己を実現するという論理だった。
ただし、普遍的とみなされたその「精神」とは「西洋」という限定がついている。そのことは、その「世界化」の波を外から蒙った日本のようなところなら、すぐに理解できることである。ただ、日本はみずから「西洋近代化」をめざし、西洋的世界秩序のアクターとなることを選んだ。西洋化することでみずから「文明世界」の一翼を担う、言いかえればこの秩序における主体となるということだ。だから「因習からの解放」を自身の解放とみなし、この秩序を自らの秩序とみなし得たのである。
「西洋の世界化」の成就と崩落
だがこの「西洋の世界化」は、全世界が西洋化されるというその成就のときに、まさに世界を一つにする「全体戦争」のうちに実現したのである。ヘーゲルが言ったように、このプロセスは「闘争の歴史」だった。具体的には戦争の歴史だ。それが世界を一つにするはずだったのだが、その「歴史の成就」はまさに世界全体の「戦争化」として実現したのである。
戦争原理によって進められた世界の統合は、最終的に全面戦争のうちに実現した。それがヘーゲル的な歴史の弁証法のいわば「真理」であり(ヘーゲルはその意味で正しかった)、それを事後的に確認したのが、アドルノ・ホルクハイマーの『啓蒙の弁証法』である(世界を照らし出す啓蒙の光は、発展の頂点で世界を焼きつぶす「原子の光」であることが明らかになった)。
だから多くの哲学者たちは、思わずキリスト教の終末論をなぞるかのように「世界の終末」を語った。宗教的な「始めと終りのある時間」を世俗化・合理化したはずの「無限の進歩の時間」は、「文明」という力による「正義」の展開の果てに、「終末」に至りついてしまった。おそらく理由は単純で、「進歩の時間」は無限でも、人間の生きる地球には現実的な限界があったということだ。
したがって当然、「文明」は大きな転換点を迎えたと言わざるをえない。「西洋」はもはやそのままでは「世界」たりえない。「進歩の時間」は消尽された。それは「未来」を持つためには(西洋にとっても世界にとっても)変容を余儀なくされるのである。
そこから「戦後」の、つまり「終末後の蘇生」のためのさまざまな原則が模索され、国際的な規範として作り出された。簡単にいえば、非戦、人権(生存権)、協調・共生(民主主義)といったことである。それは西洋が自らの主体性のために打ち立てた原理を、西洋の他者たちと「分有」することである。西洋が「普遍性」を主張し武器としたとしたら、その「普遍性」を他者たちに預け、自らはその「普遍」を生み出した一地域として、他と並ぶ「個別」に還ることである。
だが、現実にはそうはならなかった。
最終兵器(殲滅兵器)の登場によって戦争は技術的に「不可能」になったにもかかわらず、その技術を政治化することで「不可能」な戦争が新たに開始される。それが「核抑止」のもとでの「冷戦」である。そしてそれ以降も世界的な「戦争レジーム」は更新される。
いま、世界には再び、「戦争やむなし」の気配が蔓延している。世界戦争以前のように危険な領土的野心をもつ「帝国主義国」あるいは独裁者の指導する「侵略国家」が登場しているからと。その「蛮行」を許さないため、「平和な秩序」を守るために、「抑止」に足る軍事力を整え、戦争の準備をしなければならない、と。
世界の実情が、そのように世界戦争以前の状況に戻ったのか、あるいは、世界戦争が起こったということの真の意味を忘れ、拭い去り、再びそれに備えさせることで、「現状」を維持しようとする傾向が引っ張っているのか。