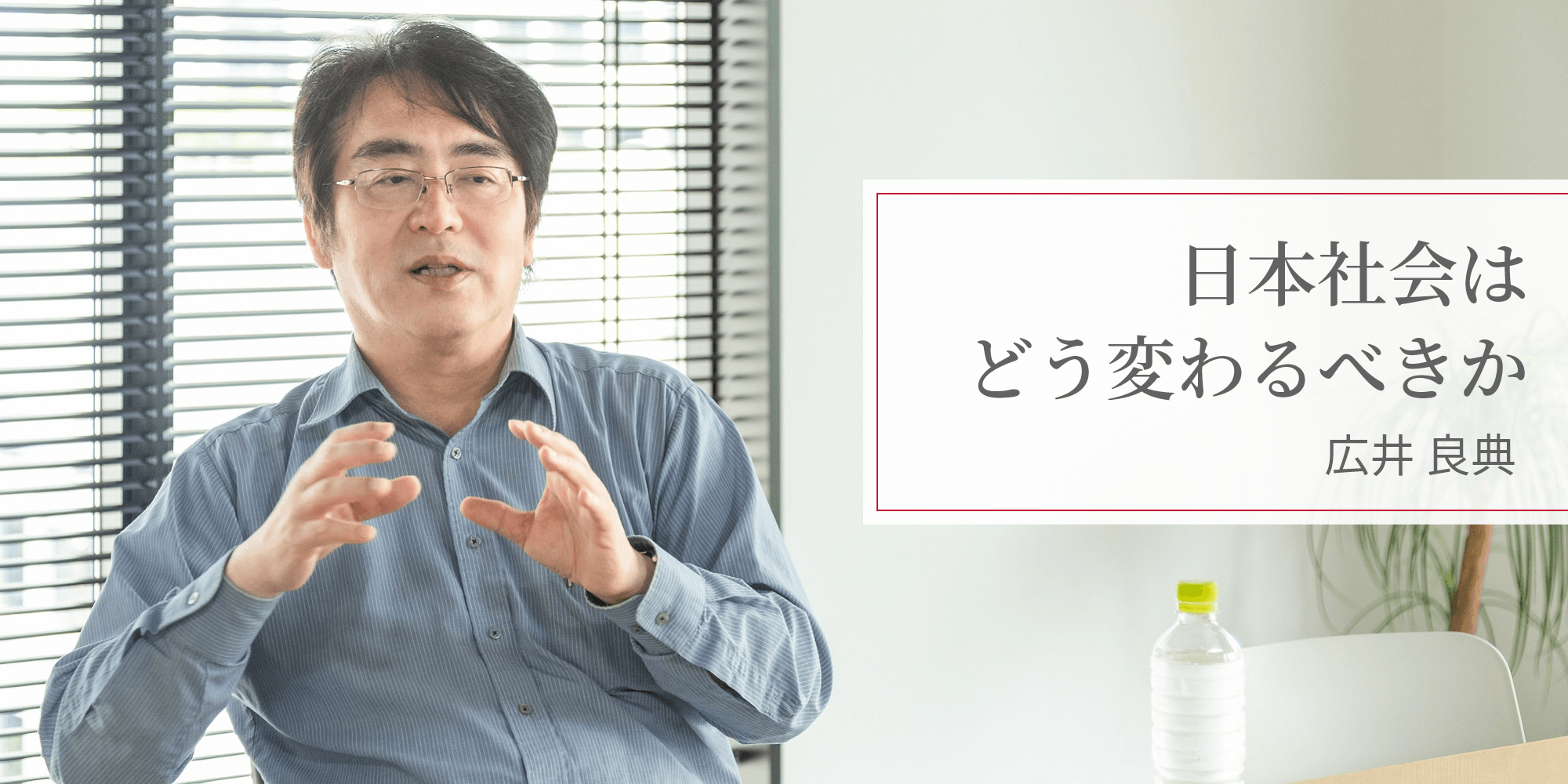――今日は、持続可能な社会とコミュニティとの関係といったテーマでお話をお聞きしていければと思います。まずは人間にとってコミュニティとはそもそもどういうものなのか、といった辺りから教えていただけますか。
わかりました。私はもともと科学史・科学哲学という文系と理系の中間のような専攻でしたので、コミュニティというのも人間だけでなく――もちろん人間に固有の話もたくさんあるんですけど――、人間が生まれるまでの生命の進化も含めて捉えるのが重要だし面白いのではないかと思っているんですね。
そういう点でいいますと、「情報」というのがひとつの鍵であり、切り口になるだろうと思います。コミュニティには情報を共有している集団という側面がありますので。思えば、コミュニティとコミュニケーションは「コミュ」が共通していますよね。コミュニケーションというのは情報を伝達するということですから、そういう意味でもコミュニティと情報はつながっています。
――コミュニティと情報という組み合わせは、ちょっと意外な感じがしますね。
アメリカの宇宙物理学者にカール・セーガンという人がいて――彼はジョディ・フォスターが主演した『コンタクト』という映画の原作も書いているんですけど――、その彼がピューリッツァー賞を受賞した『エデンの恐竜』という本の中で情報の進化ということを言っているんですね。情報には遺伝情報、脳情報、デジタル情報という流れがあると。
どういうことかというと、話はわりと簡単で、もともと生物というのは親から子に情報を伝達するわけです。原初の生物はDNAの中の遺伝子をバトンタッチしていくことで、親と同じような子が生まれ、親と同じような行動をする。それが一つめの遺伝情報です。
――ふむふむ
ところが、生命がだんだん複雑になっていくと、遺伝情報だけではすべてを伝えきれなくなる。それで何をしたかというと、DNAの遺伝情報だけではなく、脳情報というものを使うようになった。脳情報というのはわかりにくいかもしれませんが、要するに個体と個体が関わりをもち、それによって情報を伝達するわけです。いちばんわかりやすいのが哺乳類。哺乳類というのは「哺乳」という言葉が示すように親と子が関わりを持ち、コミュニケーションの中で情報を伝達していきます。
たとえば魚だったら親の遺伝情報がただ子に伝わっていくだけですが、哺乳類は個体と個体がコミュニケーションをとることで、親が脳に蓄えた情報を子に伝えていくんですね。それが二つめの脳情報。
――コミュニケーションによって伝わるのが脳情報。
その脳情報が最高度に発達したのが人間ということになるのですが、人間の歴史が続いていくうちに今度は脳情報でも足りなくなって、話が一気に最近になりますが、コンピューターというのを作り、その中に情報を入れてやりとりするようになった。いわば脳を外部化したわけですね。それが三つめのデジタル情報で、ここから現代のネットコミュニティみたいなものも生み出されていく。要するにコミュニティは、遺伝情報、脳情報、デジタル情報という、情報の進化とともに発展してきたということがいえるかと思います。
――面白いですね! つまり、哺乳類までの魚類や爬虫類っていうのは、子どもを産んだら産みっぱなし。
そうです。遺伝情報を伝えたらそれで終わり。それに比べて哺乳類のやり方はまどろっこしいというか、非効率的にも見えるんですけど、ゆっくりと時間をかけて多くの情報を伝達することにより、種をつないできたということができると思います。
――ただ、そうすると今度は情報伝達の個体差というか、不確定性が出てくるようにも思えますが。
そのとおりです。遺伝情報というのはDNAの情報をただバトンタッチするだけですから、まさに確定的というか、親と同じように育ち、同じように行動するわけですが、哺乳類や人間の場合は不確定で、言い換えると多様性ということだと思いますが、それによって複雑に発展したり、場合によっては情報の受け渡しがうまくいかなかったり、ということも起きてくるだろうと思います。
――なるほど。いずれにしても、コミュニティの基になるのは親と子の関係だということなんですね。
そうですね。親子関係は一つの原型ではあるんですけど、当然きょうだいという関係もありますし、家族以外の個体ともやりとりをするわけですから縦、横、斜めというか、いろんな他者と関わるのがコミュニティの特徴ですね。これに関連して人間には「重層社会」という特有の現象があります。
農耕がもたらしたもの
日本では霊長類学、つまり「サル学」が非常に発達していて、ちなみに私がいる京都大学は総長の山極寿一(編注:インタビュー当時)さんがゴリラの専門家ですし、他にもチンパンジーをやってる人とか、ボノボをやってる人とかいろいろいます。私が非常に面白いと思ったのは、『子どもと自然』(岩波書店)という本を書かれている河合雅雄さんが、人間社会の特徴ということで、さっきお話した「重層社会」ということを言われていて。
猿も含めた哺乳類は群れを成すことでひとつの「社会」をつくるんですけど、人間以外の動物では個体があっていきなり社会なんですね。ところが人間の場合はその間にも集団がある。それは差し当たり家族というのが一番わかりやすいですけど、個体があっていきなり社会ではなく、重層構造になっていると。
――その個体と社会の中間の集団がコミュニティというわけですね。
それはどういうことかというと、コミュニティの内側の関係と、コミュニティの外側の関係の両方があるということです。つまり、家族の内と外で他者との関係性が異なってくる。
たとえば子どもの成長でいうと、コミュニティの内側で特に重要なのが母親との関係です。しかし人間は家族の中だけにいると引きこもりになってしまうので、家族の外ともつながっていく必要があり、一般的には父親がその橋渡しをする。実際にはもちろんいろいろな形がありますが、子どもは成長していくにつれてコミュニティの内側だけでなく、コミュニティの外側との関係も築いていくようになる。私はこれを関係の二重性と呼んでいますが、人間の非常に特徴的なところだと思います。
――なるほど。家族がコミュニティというのは理解しやすいのですが、家族以外のコミュニティというのはどのようにして生まれてきたんでしょうか。
そうですね。20万年前にアフリカでホモサピエンスが生まれてからの社会は、大きくいうと「狩猟採集社会」、「農耕社会」、「工業化社会」という風に変化してきたということができます。それぞれの社会では拡大・成長と定常化が繰り返されていて、つまり狩猟採集で人口が増えて定常化し、1万年くらい前に農耕が開始されるとともにまた人口が増えて、それが落ち着くのがいわゆる中世と呼ばれる時代。そしてこの300~400年の工業化によってまた人口や経済が一気に拡大し、いま限界を迎えているという状態です。
この3つの中でコミュニティが非常に強固になったのは農耕社会です。想像してみるとわかりますよね。狩猟採集社会というのは、良くも悪くもその日暮らしみたいな感じなので、集団の凝集力というのはそれほど強くない。もちろん、マンモスをみんなで追い掛けて捕まえるといったことはあったでしょうが、集団が準拠すべき規範といったものはあまりなく、それぞれが比較的自由に行動していたと考えられます。
――狩りの時だけ協力しあう、みたいな感じですね。
ところが農耕というのは土地を開墾するにしても、苗を植えたり、害虫を防いだりするにしても、一人や一家族だけではとてもやっていけない。日本であれば稲作が中心ですから、米をつくるためのコミュニティが形成され、その中では集団に同調する行動が強く求められる。いわゆる同調圧力みたいなのがどんどん強くなっていくわけです。

しかも農耕というのは1年のサイクルですからね。狩猟採集であれば、単純にいえばその日その日の獲物を追い掛けたり、木の実を採ったりしていたのが、農耕では1年という長いスパンで人びとが共同し、支え合いながら生活していく。生きていけるかどうかがコミュニティにかかっていたわけです。
――それは結束が強まりますよね。
そうするとそこでは、作物を育てる雨を欲したり、その年の豊作を願ったりといった共通の価値観や世界観が形成され、ものすごく単純に言うと、それが宗教へとつながっていったのではないかと思います。
――農耕によってコミュニティが結成され、その性格が強まることで宗教が生まれたと。
さらに言うと、先ほど農耕の開始によって人口が拡大したと言いましたが、その上り坂の途中、生産にある程度余裕ができてきた段階で、都市というものが生まれます。同時にその生産物、つまりは富をたくさん持ってる人間とあまり持っていない人間の格差が生まれ、それが権力として構造化されることにより、宗教の形も変質していくことになります。
そして、ドイツの哲学者ヤスパースが「枢軸時代」と呼んだ紀元前5世紀頃、地球上の各地で今に続く普遍的な思想や宗教が同時多発的に生まれました。インドでは仏教、中国では儒教や老荘思想、中東ではキリスト教やイスラームの原型となったユダヤ教、ヨーロッパではギリシャ哲学などです。
これらは「普遍宗教」とか「普遍思想」といわれますが、私の理解では、農耕社会で人口や経済がどんどん拡大していったところ当時の環境や資源の限界にぶつかり、人間の欲望のままに拡大していってはまずいということで、内面的な価値の重要性を説くものとして生まれたのではないかと。話がややこしくて恐縮ですけど、つまり宗教も単に豊作を神に祈るというだけではなく、コミュニティやそれを取り巻く環境の変化の中で、形を変えて展開してきたということがいえるかと思います。