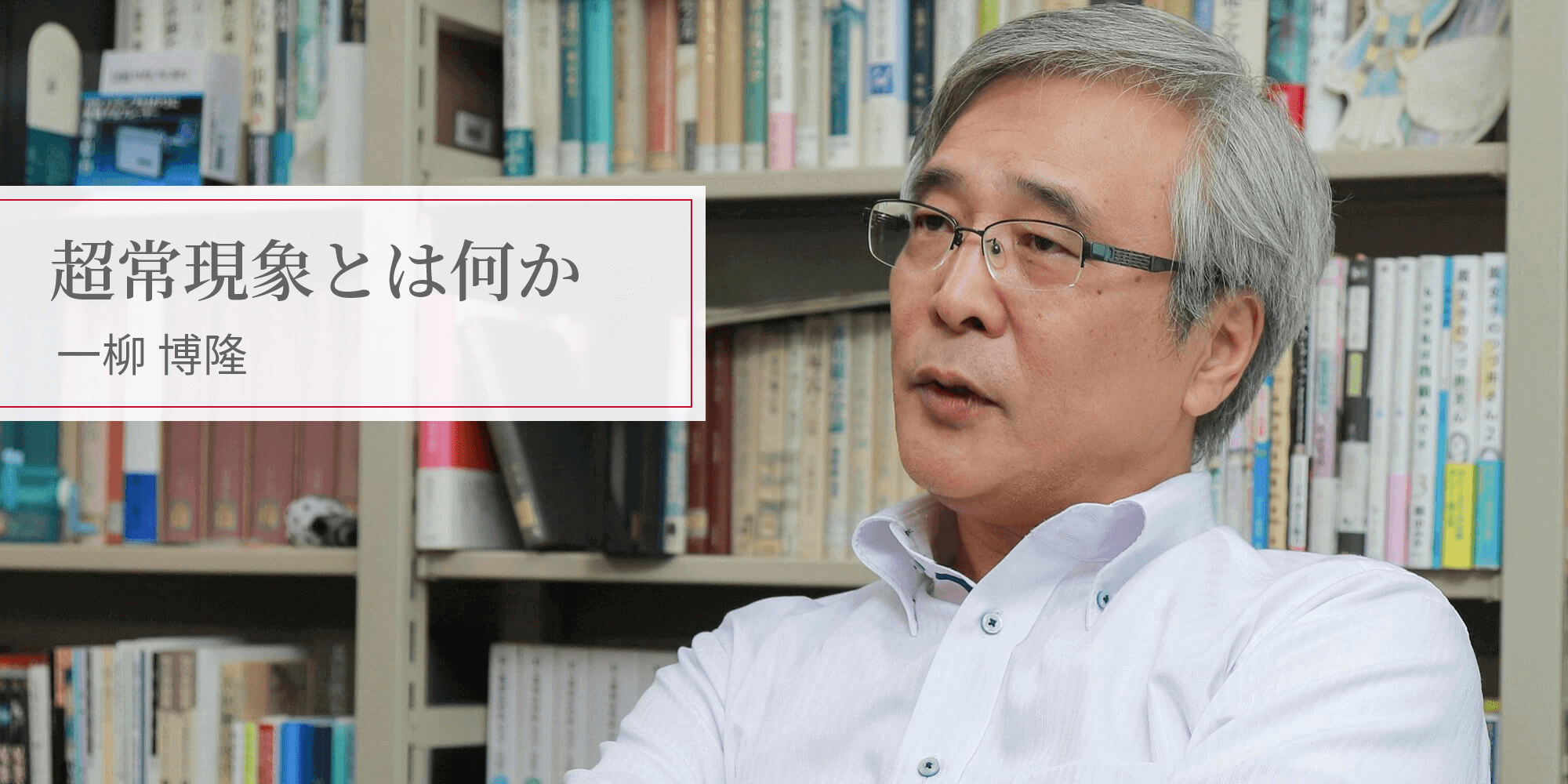――私今まで知らなかったんですけど、フロイトって、日本の心理学的には傍流というか、亜流的な位置づけなんですか。
そうなっちゃいましたね。
――「無意識」なんて、日常的に使うような概念を生み出したのに。
最初はすごく注目されたんですけど、結局は受け入れられなかった。日本ではドイツ発祥の実験心理学がメインになります。その立場から言えば、フロイトは「文学」的すぎるということになる。「無意識」という仮説はとてもロマンティックで魅力的ですが、科学的には証明できないんですよ。
――ふつうにあるものだと思ってましたけど、科学的には証明されてないんですね。「意識」が仏教用語だから、「無意識」という言葉が日本人には受け入れやすかったというか、分かったような気になった人が多かったということでしょうか。
たしかに、すんなり入ってくる言葉だったのかもしれませんね。無意識って、良くも悪くもすごく便利な概念で、説明のつかないことがあったら全部無意識のせいだって言うことができる。でも、その無意識自体はブラックボックスで、誰にも説明ができない。するとそれは科学なのかという話になり、フロイトの無意識って霊と同じ空虚な概念に過ぎないんじゃないのって、そういう暴論というか、極論まで出てくる。フロイト自身はもちろん、科学だって信じていますけど。
――世の中に霊というものが実在してそれを見ているのではなく、人間の意識の下層にある無意識という領域で起きたことが作用してその人に霊を見せてるんだ、みたいな理屈でしょうか。
そういう解釈もあり得るでしょうね。さらに、そもそもあるかどうかわからない無意識を持ち出した段階で、もうそれ科学じゃないよねって言われちゃうわけです。
――なるほど。よくいわれることですけど、科学技術の進化によって夜でも明るくなり、かつては秘境とよばれていた場所も開拓されつくされた結果、地球上から謎がなくなってしまった。それで、最後に残ったのが人間の心の中の闇、無意識ってことなのかなって。でも、それは科学じゃないっていわれると辛いですね。
最後の秘境、最後の謎が脳と無意識みたいな。それはありますよね。
ドッペルゲンガーとアイデンティティ
――ご著書(『無意識という物語』)によると、明治時代に西洋の思想が入ってきたことによって、日本人の「心」に対するイメージも変容してきたとのことですが、そのことが西洋列強に対抗する日本人としてのアイデンティティ、大和魂とか武士道精神といったものをどうつくり上げていくか、ということにも影響を及ぼしたと考えられますか。
日本人のアイデンティティを論じるのは、なかなか難しいですね。西洋の場合のアイデンティティは、基本的に神との関係性の問題になります。つまり、絶対的な神と向き合うことによって、ひとりひとりの自己が保証される、という構造がキリスト教の中にあるわけですね。なので、この近代化された神なき世界にあって自己をどうやって確立すればいいのかってなったときに、アイデンティティの激しい動揺が生まれる。それで、自分の影が消えちゃったり、自己が分裂したり、いわゆるドッペルゲンガーと呼ばれるような現象が起きるようになります。
――なるほど、ドッペルゲンガーはそういう文脈で生まれたんですね。
ドッペルゲンガーを取り上げている近代日本の作家は、芥川龍之介や梶井基次郎など、けっこういるんですけど、日本人だと、ドッペルゲンガーが「アイデンティティ=神との関係性」の揺らぎによって生じるというのはあまりピンときませんよね。芥川が書いているものは割とそれに近かったりもしますが、たとえば泉鏡花だと、もっと霊魂的な問題というか、魂と肉体の分離といった意味のほうが強いように思います。
江戸時代の随筆の中に「離魂病」っていう話があるんですけど、あれなんかは完全に魂と肉体の分離ですね。離魂病は魂が肉体から離れかかっているということだから、死ぬ予兆なんだそうです。よく言われる「自分の姿を見た者は死ぬ」というのはこの文脈によるもので、西洋の場合はドッペルゲンガーを見ても必ず死ぬわけではありません。
――ということは、以前からあった魂と肉体との分離みたいな話が、ドッペルゲンガーという言葉によって衣替えした、みたいな感じですかね。
そういうケースもあるかなって思います。
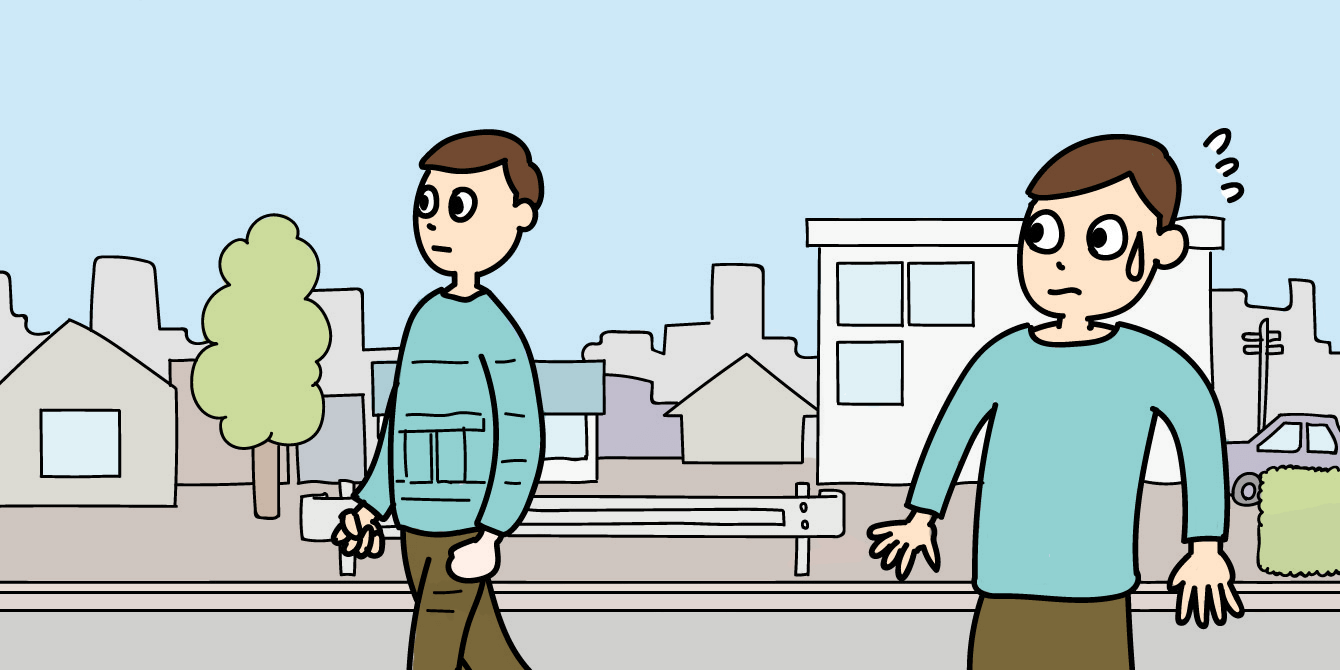
――日本人のアイデンティティというところにお話を戻すと、明治の終わりごろからエリートの若者たちがろくに働きもしないで哲学に現(うつつ)を抜かす、いわゆる「煩悶(はんもん)の時代」がはじまるそうですが、その理由としてはどんなことが考えられますか。
「煩悶の時代」は明治36(1903)年頃からなので、日露戦争が始まる一年前ですね。よくいわれるのは、「おやじ」に対する反発だというものです。
彼らの父親は明治の第一世代、幕末から明治の激変の時代を生き抜いた世代です。ものすごい勢いで社会制度が変わり、世の中が劇的に変容していく。こうした混沌とした状況は、才能のある者から見れば、千載一遇のチャンスですよね。立身出世、一攫千金。だからどうしても、目の前の状況にどう対処するかという、現実主義者になりやすい。
でも、次世代を担うエリートの若者たちは、そんな父親の姿を見て失望する。「ほんとに立身出世や金儲けが大事なんだろうか。自分の一生を賭けるに値するのか」と疑問を持つようになった。煩悶の時代のきっかけを作ったのが藤村操の自殺だといわれてますけど、もう少しシニカルな見方をすれば、彼ら明治第二世代には、もう一発逆転がないんですよ。
――といいますと?
幕末から明治だったら、戦国時代と同じで、どこかの農民が国家の中枢まで一気に昇りつめるといったことがあり得たわけです。でも明治30年代にもなると、官僚機構も一般企業もほぼ体制ができあがっていますから、下から順番に積み上げていくしかない。30年、40年かけて何か事を成す、それはそれで立派な人生だと思うんですが、そんな辛くて長い道のりをいかなくちゃいけないのか、みたいな。
――現実っていったい何なんだと。
夏目漱石の『それから』の主人公、長井代助がまさにそんな感じですよね。明治の成功者のひとりである実業家の父を軽蔑してるくせに、その父から金をもらって、まったく働かない。日本は玄関ばかり大きくなってそのくせ奥行きがなくて、こんな見栄ばかり張ってる国のなかに、俺が活躍できる場所なんかどこにもないとか言って。
――いわゆる高等遊民ですね。
それに激しく共感するのが、武者小路実篤や芥川龍之介たち。彼らが東京帝大の学生だった頃に『それから』が出て、長井代助は俺だ、と感じる。
――父親の世代によって国の骨格も制度もつくられちゃって、俺らもうやることないじゃんと。
そうなると、心や広大な無意識、最後の秘境、そこに行くしかないということで、煩悶の時代に通底する精神主義的なまなざしがつくられていった、という感じではないかと思います。