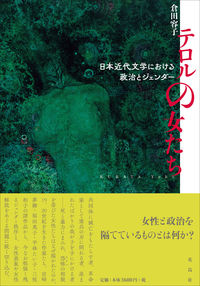主人公 児島文子
明治の初め、ロシアの陸軍中将兼警視長官であるハクブノップが、留学していた日本人の男女によって殺害される事件が起こりました。女の名は児島文子、男は三浦卓(たかし)。両名はその後、取り押さえようとした警官に抵抗し、卓は逃走、文子は警官と揉み合った際の負傷がもとで死亡しました。近代の歴史にくわしい人でも、この事件を知っているという方はほとんどいないでしょう。それもそのはず、実はこれは宮崎夢柳(1855-1889)の政治小説『芒の一と叢』(すすきのひとむら)の中のエピソードです。
「政治小説」という言葉にもあまりなじみがないかもしれません。政治小説は文字通り政治や政治思想を描いた小説のことです。文学史的にはとくに、明治10年代から20年代にかけて数多く書かれた、自由民権運動の主義主張を人びとに伝えるための小説を指し、戸田欽堂(1850-1890)の『民権演義 情海波瀾(じょうかいはらん)』を嚆矢とします。この狭義の政治小説の中でも『芒の一と叢』(さらにはその前作にあたる『鬼啾啾(きしゅうしゅう)』)は、女性を主人公としている点が注目に値します。
『芒の一と叢』の主人公 児島文子は、ロシア皇帝アレクサンドル2世を暗殺して後に処刑された革命家ソフィア・ペロフスカヤ(実在する人物です)の伝記に感銘を受け、「彼の蘇比亜(ソフィア)が勇気を学び」、自由のために立ち上がり、「志に斃(たお)る」ことを決意します。そして、同じく自由権利を希求する「国事熱心家」である三浦卓と出会い、ともに海外にわたって「共産党社会党虚無党などの仲間に入り」、冒頭のテロ事件を起こすに至るのです。
それにしても、夢柳はなぜ文子を主人公にしたのでしょうか。日本版ソフィア・ペロフスカヤを描くという意図はあったにせよ、自由民権運動に従事した活動家の中心は男性であったことを考えると、運動の機運を高めるという目的のためには、彼らが感情移入しやすい男性を主人公にした方が効果的であるように思われます。この問題を考えるには、自由民権運動の内実を見ていく必要がありそうです。
自由民権運動=権力復帰のための運動?
自由民権運動は板垣退助らによる「民選議院設立建白書」に端を発する運動であり、一般に、すべての国民に「自由」をもたらす、近代的立憲制国家の樹立をめざしたものと見なされています。しかし、これに対して歴史学者の松澤裕作氏は、自由民権運動は近世身分制社会にかわる社会のあり方を模索する運動であり、その新たな構想を実現する主体として、「知識と意欲を持つ士族集団」(松沢裕作『自由民権運動――<デモクラシー>の夢と挫折』岩波書店 56頁)が想定されていたことを指摘しています。
松澤氏によれば、民権派が要求する民選議院の設立そのものに反対する論者はいなかった一方で、建白書の提出者たちに対しては、直前まで自らも政府のメンバーであった彼らに「有司専制(編注:官僚が独断的に事を進めること)」を批判する資格があるのかという疑問が投げかけられたと言います。また、実際、立志社(編注:自由民権運動の中心となった政治結社。1874年に高知で結成された)は県庁と癒着しており、板垣らはそもそも自分たちの行動を「反体制」的なものだと思っていなかったとした上で、次のように述べています。
板垣らの目的は、民選議院という魅力的なポスト身分制社会の構想を掲げることで、権力復帰をはかるという点にあったと言ってよいだろう。(前掲書55頁)
こうした歴史の見取り図にはさまざまな議論があると思いますが、運動の広がりを支えた政党新聞の記者=政治小説の作者にエリート意識が見られることは確かです。たとえば、夢柳の『高峰乃荒鷲』の「緒言」には「下等社会の提醒誘導」という目的が明記されていますし、板垣らによって結成された「自由党」の機関紙である『自由燈(じゆうのともしび)』という新聞名からも、自分たちが「燈」となって暗がりにいる民衆を照らしてやるのだという意識がうかがえます。
こうした選民意識は、記者の多くが士族であったことと無関係ではないでしょう。実際、政治小説の中には、勤皇志士の詩文やエピソードが数多く引用され、志士の絆や精神性が肯定的に語られています。つまり、自由や民主主義といった近代思想の導入を主導したのは、かつての身分制社会における支配階級の出身者であり、しかもその権威を自らのアイデンティティの拠り所としていた者たちだったということができそうです。
「自由」の行方
これを踏まえ、改めて『芒の一と叢』を見てみましょう。主人公 文子の父は武田耕雲斎(編注:幕末の水戸藩士。尊王攘夷派の一派である「天狗党」の党首)の血統の者であり、養父は同じく尊攘派の志士という設定になっています。つまり文子は勤皇の志士の血脈に連なる人物なのです。であるにもかかわらず、彼女は蘇比亜(ソフィア)に感化されて自らの志を遂げるため国を捨て、「欧米」の反体制運動に身を投じていきます。
これは、男性に尽くし支えるという当時の女性像の規範だけでなく、天皇の民たる「臣民」の規範をも裏切る行動です。もしも彼女が男性であったら、(三浦卓がそうであったように)国内での政治的活躍を嘱望されていたでしょうから、そもそも国家や社会を離脱する契機を持ち得なかったように思います。
また、「自由」な「個人」としての登場人物を造形するには、忠義のために自己犠牲を貫くという志士の規範を否定する必要がありますが、そのような男性をヒーローとして描くことは、夢柳にとって困難だったのではないでしょうか。夢柳が学んできた漢詩文の言語体系には、その隅々まで志士のエートスが息づいています。このエートスに背く「個人」としての男性像を肯定するだけの論理は、夢柳の小説に内在していないように見えます。
女だからこそ、つまり皇恩と忠の互酬関係から疎外され、国内に政治的活躍の場はなく、また志士の絆や文学的言説からも締め出されていた「婦人女子」であったからこそ、文子は「個人」の「自由」を体現する「自由の使者」となることができたと考えられるのです。
しかしこのままでは、この国で自由を手にできるのは女性だけということになってしまいます。それを解決するのが、物語最後の場面です。『芒の一と叢』は文子と卓の息子である秀(ひいず)が、ロシアの警吏に殺された文子の髑髏を小脇に抱えて演説するシーンで幕を閉じます。文子の髑髏は蹂躙され剥奪された自由の隠喩であり、それが秀に「所有」されることによって、自由が夢柳および自由民権運動の中心を占めていた男性たちの手に奪還されるのです。
『芒の一と叢』に、女性の自立や権利を擁護する描写があることは確かです。しかしその主目的は「自由の使者」としての女性像を造形することでした。夢柳は男性によって抑圧され、政治の場からも排除された女性を「他者」として利用することで、「自由」の概念を描き出したということができます。では、当時の女権論者の主張は、夢柳の描く女性像とどのように異なっていたのでしょうか。その違いが、「愛憐の情」の捉え方によく表れているように思われます。
「公私」を問い直す
女権論者の一人である中島湘煙(1863-1901)は『同胞姉妹に告ぐ』の中で、「男女の間は愛憐の二字をもて尊しとす」としたうえで、その「愛憐の情」を打ち壊す男子の「権柄」を強く非難しています。この当時、家庭の主は夫(父)であり、妻(母)である女性はそれに仕えるのが当然だとされていました――いわゆる「家父長制」です――。こうした状況に対して湘烟は、男女が互いに相手を思いやることの重要性を説き、男女関係の変革を訴えたのです。
これに対して夢柳は『芒の一と叢』の前作である『鬼啾啾』の中で、「愛憐の情」は「社会の事」(社会的使命)を忘却させる「私事」だと切り捨てています。一個人を愛憐するのではなく、一千万人の同胞を愛憐してその身を捧げるべきだ、というのが夢柳の言い分です。こうした考えは、自己を犠牲にして公に尽くすという点において、まさに志士のエートスに連なるものだといえるでしょう。
こうした夢柳の議論には近代的な「公私」の概念の萌芽を見ることができます。明治期は、近代的な諸制度が確立されるとともに、公私の区分が再編成された時代でもありました。選挙権を直接国税を15円以上納付する満25歳以上の男子に限定した1889年(明治22年)の衆議院議員選挙法や、女性の政談集会・政治結社への参加を禁じた1890年(明治23年)の集会及政社法により、女性は政治参加の機会を奪われました。
また、1898年(明治31年)、私人間の日常生活における権利や義務の関係性を定めた民法が施行されます。その中で妻の権利は著しく制限され、一定の法律上の行為に夫の許可が必要とされました。そうなると必然的に、女性が活動するのは家の中に限られます。その結果、公的な領域=男性の世界、私的な領域=女性の世界という構図が一般的なものになっていったのです。
このこと自体が不当なのはもちろんですが、もう一つ重要なのは、「自由」や「平等」といった理念は公的領域における規範であり、家の中はそうした理念の及ばぬ領域だとされた点です。家庭が公権力の介入しない場であるということは、個人の自由という面からは良いことのようにも見えますが、しかし、実際には家の中での男性(父、夫)による支配には法による公的な承認が与えられていました。その一方で、家の中で妻が夫に打ち据えられていたとしても、それは各自が処理する個人的な問題(私事)と見なされるなど、公/私の境界線は、弱い立場に追いやられた人たちの問題を不可視化するような形で、恣意的に引かれていたのです。
多くの人が自明視している公私の区分は、今なお、あいまいで恣意的なものです。たとえば、子どもを産むことや育てることは家庭内の問題だと見なされがちですが、それと直接的に関係する出生率は公共の問題に他なりません。子どもが生まれず国民がいなくなれば、日本という国は成り立たないのですから。であるにもかかわらず、妊娠・出産や育児環境に関する問題はあたかも個人の(多くの場合は、女性の)私的な問題であるかのように扱われ、自己責任に帰されがちです。
また、公私の恣意的な区分の問題は、同性婚の議論にも通底しているように思います。日本では法律上の性別が同じ人同士は結婚することができず、そのパートナーシップは公的な制度の外側へと追いやられています。私たちが生きる社会には、法的に不安定な状態に置かれているために困難に直面している人たちが、いま現に大勢います。にもかかわらず、同性婚を公共の問題として議論することさえ拒む人たちがいるのです。
近代の自由主義は個人の権利を尊重し、その意思に基づく社会の実現をめざしてきました。しかし、そのようにして打ち立てられた公共の場から、家事・育児・介護といったケアの問題や、異性愛規範から外れた関係性や個人の存在は周到に排除され、私的な領域に押し込められてきたこともまた事実です。近代日本の黎明期に書かれた政治小説には、こうした公私二元論の萌芽が刻印されています。いま改めてそれらの小説を読み直すことで、これからの社会を考えていく手掛かりの一つになるのではないかと思います。
※本稿は2022年5月から6月に配信された駒澤大学公開講座「革命の女たち ―政治小説に描かれた女性像―」の内容とトイビトのインタビューへの応答を基に構成しました。