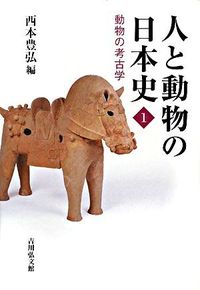縄文時代の遺跡からはイヌの骨が多数見つかっています。その中にはほぼ全身骨格を保ち、埋葬された個体に由来する資料も少なくありません。縄文時代人はなぜイヌを埋葬したのでしょうか。
1962年に愛媛県久万高原町(旧美川村)の上黒岩岩陰遺跡で発掘された2体の犬骨は、国内最古の埋葬犬資料としてつとに知られていましたが、不幸にして発掘後約半世紀に亘って所在が不明となっていました。私達は、2011年に慶應義塾大学三田キャンパスでこの犬骨を再発見、改めて精査したところ、2体とも生前に歯牙の一部を失っていたことがわかりました。こうした歯牙の生前喪失は、この2体がしばしば「猟犬」として利用されていたことを示唆してくれます。


アメリカの古人類学者パット・シップマンは、ネアンデルタール人の絶滅にも犬が重要な役割を果たしたと説きます。更新世末期のヨーロッパで、共に頂点捕食者であったネアンデルタール人類、ホモ・サピエンス、オオカミが獲物を奪い合っていた状況下、やがて、サピエンスがオオカミの馴化に成功。馴化されたオオカミ、すなわちイヌと連携して狩猟に当たり、獲物の捕獲精度を高めたことが、ネアンデルタール人類が絶滅に追い込まれた一因だというのです。ヒトよりも足が速く、逃げ足の速い獲物を噛み止めすることができるイヌ。足の速さには劣るものの、道具を駆使し、獲物を仕留めることには長けたヒト。その両者の連携が、体格に勝りより多くの肉を必要としたネアンデルタール人類から必要な栄養を奪い取ったとする仮説は、学会に少なからぬ衝撃を与えています。その当否はともかく、ヒトとイヌは更新世の昔から互恵的な関係にあったことは間違いないでしょう。
興味深いことに、縄文時代の遺跡から出土する埋葬犬骨には、四肢骨に骨折・治癒痕が確認された事例も知られています。副木を用いた整復処置なども無かったとみられる往時、骨折したイヌは、猟犬としてはもはや使いものにならなくなったはずです。にもかかわらず、骨折が治癒するまで生きられたことは、不具になった後もエサを与え続けられたことを意味します。この事実は、縄文時代人が少なくとも一部のイヌを、狩りの道具としてのみ見ていなかったことを示唆してくれます。もしかすると、彼らは一部のイヌを、共に生きる仲間あるいは家族同然の存在と考えていたのかもしれません。
神話研究で著名な文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースは、先住民にとって、人間と動物は分かちがたく結びつく存在であることを指摘しました。ハイダ族やトリンギィット族など北米先住民に知られる、特定の動物を自分たちの出自とも結びつけるトーテミズムは、その最たる例と言えます。また、サハリン、北海道、千島列島に暮らすアイヌの人々は、自身に肉や毛皮をもたらしてくれる動物を神の化身と考えてきました。こうした、異なる事象を結びつける能力は、私たちサピエンスの心の基体をなすと見るべきでしょう。
自己と他者、文化と自然、人と動物、宗教と科学、過去と未来など。西洋近代科学はその誕生から一貫して「分離すること」「区別すること」を志向してきました。既存の学問が専門分化によって発展・深化してきたことを否定するつもりは毛頭ありません。ただ、その一方、今日では、一つの事象を一つの学問領域だけで研究することが困難になりつつもあります。遺跡から出土する犬骨の研究ひとつとっても、動物考古学のみならず、生物学、解剖学、獣医学、年代学、遺伝学、骨化学などとの連携が欠かせません。考古遺跡から出土する動物遺体の研究は、深めれば深めるほど、それが文化の研究なのか自然の研究なのかわからなくなる側面も持ちます。もとより、自然も文化も西洋近代学が創出した概念に過ぎませんから、それも蓋し当然と言えましょう。新たな知の地平を開く上では、異なる事象を結びつける流動的知性を発動させ、既存の学問の枠組みを超える営みこそが不可欠なのだと思います。
文責:トイビト加藤