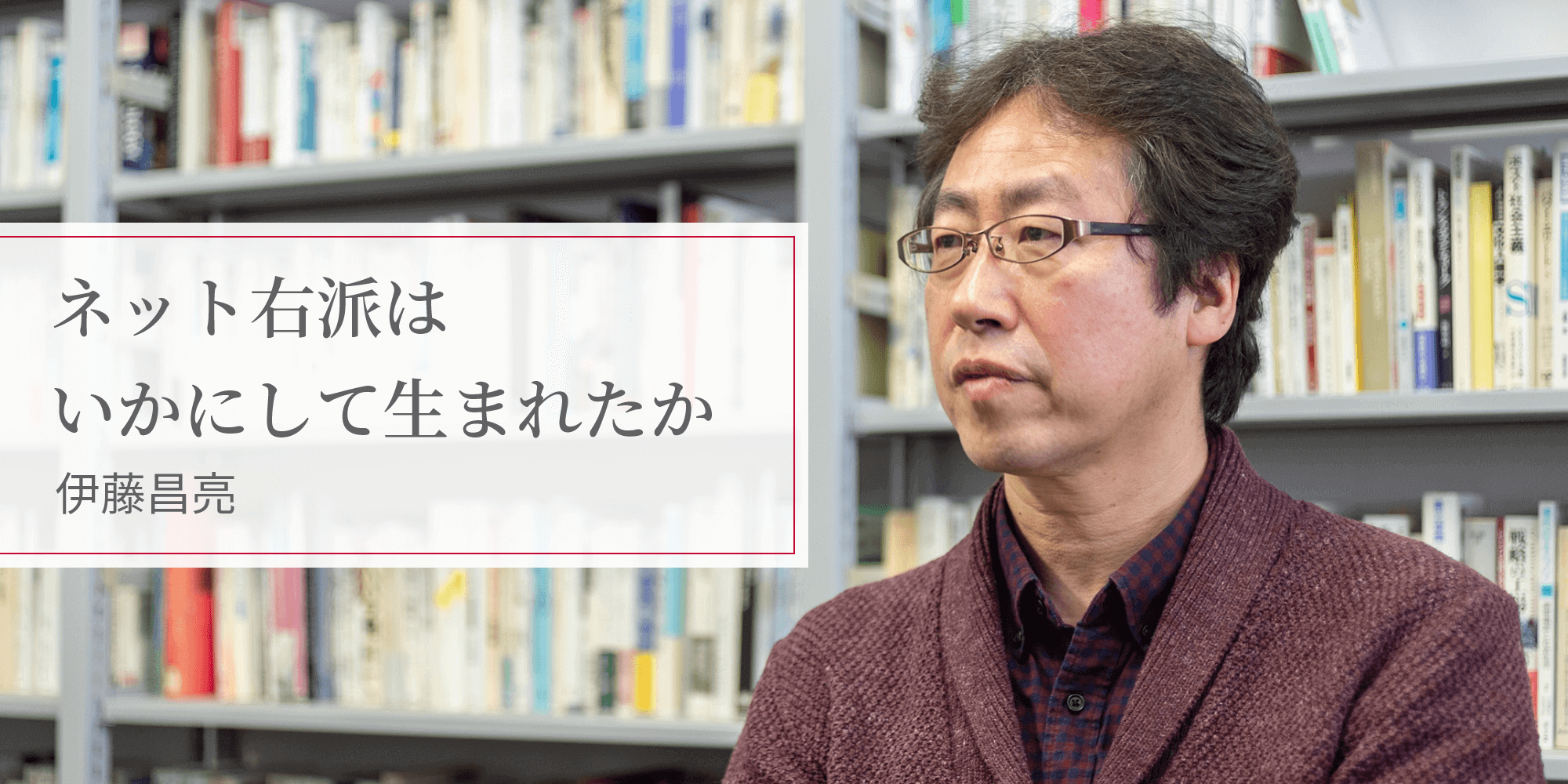――それにしても、戦前の右翼には農民を擁護するような思想があったとは知りませんでした。
過激な思想ですけどね。血盟団事件の「一人一殺(いちにんいっさつ)」のように極端なものではあるけど、明治から戦前の右翼にはある種の思想があったとは言えると思います。権藤成卿(1868-1937)や橘孝三郎(1893-1974)など、農本主義と言われる動きにはそうした思想が顕著でした。しかし戦後になると、こういったものはあまり見られません。
――それはなぜでしょうか。
右翼は軍部と結びついて戦争を起こしたということで、主だった右翼団体は戦後に解体させられたんです。それが60年安保の前あたりに、反共(=反共産党)の盾になるという名目で復権を許され、いわゆる街宣右翼や行動右翼になっていく。それに対し、戦前の思想をもう一度取り戻そうという新右翼が60年代末の学生運動をきっかけに出てきます。戦後の右翼は左翼をつぶすために復権してきたので「反共親米」が基本なんですけど、新右翼は反体制派なので「反共反米」です。
――右翼にもスタンスの違いがあるんですね。
もう一つ言うと、戦後の右翼は反共なので、韓国に味方して北朝鮮を攻撃する。つまり、いまのネット右派とはちがって「嫌韓」ではなかった。こうした部分は、今ほとんど認知されていません。
――私も知りませんでした。
丸山真男の弟子の橋川文三(1922-1983)や、いまだと中島岳志さんのように、戦前の右翼思想を見る研究はあるんですけど、戦後の右翼には誰もあまり触れたがらない。新右翼にしても、野村秋介(1935-1993)とか鈴木邦男さんとか、あることはあるんですけど、いまではふつうの人はなかなか読まないですよね。

だから右翼史自体が謎というか、戦後民主主義の中でタブー視され、封印されてきたところがある。それはある意味正しいことではあるのですが、一方で、よくわからないからこそネット上で恣意的に用いられ、おかしなものになっていったということがあるのかもしれません。
――一方の左翼の歴史についてはいかがですか。
日本の左翼は中江兆民(1847-1901)などにはじまっているので、こちらにも明治からの歴史があります。思想的には諸外国と同様にマルクス主義を軸としていますが、マルクス主義をそのまま使うのではなく、日本の状況にどう照らし合わせていくかという視点で研究が続けられてきました。
戦前であれば、それこそ明治維新をどう捉えるか、つまり、あれはブルジョア革命だったのか否か、どうやったら本当に革命が起こせるのかといったことが議論され、そこから、いきなりプロレタリア革命(=資本主義体制の解体をめざす革命)を起こすのではなく、最初にブルジョア革命(=封建主義体制の解体をめざす革命)をやってからプロレタリア革命をやるんだという「二段階革命論」が提唱されました。まずは民衆が一丸となって天皇と軍部のファシズムに反発していかなければならないと主張し、戦争に反対する大きな勢力へとなっていきます。
こうした思想は戦後にも引き継がれ、1951年の「旧安保条約」や「60年安保条約」――その間には自民党が与党、社会党が野党のそれぞれ第1党を占める、いわゆる「55年体制」が確立します――の際には、日本政府がアメリカ側とだけ結びつくことに反発する大きな動きを生み出しました。
新しい正しさ
――左派の思想というと「市民」や「リベラル」という言葉が一般的になっていますが、これはいつ頃から使われるようになったんですか。
「リベラル」という言葉がよく使われるようになったのは90年代からだと思います。冷戦が終わったのが89年、バブルの崩壊が91~93年、そして先述の55年体制が終わったのが93年。つまり、その辺りで社会の枠組みが大きく変わった。その中で、それまでマルクス主義を訴えていた左翼も――ソ連が解体した影響もあって――それができなくなり、「革新」というキーワードがあまり使われなくなってくる。それに代わって出てきたのが「市民」や「リベラル」という言葉で、それと同時に、プロレタリア革命によって資本主義体制を倒すんだということではなく、市民が一人ひとり自覚を持って国家に対抗していくんだ、という考えになっていく。これは、まさにソ連を解体へと導いた東欧の市民革命の影響が大きかったんじゃないかと思います。
――時代の変化に対応する新しい言葉、新しい価値観が必要だったわけですね。
そういうことですね。これまであった枠組みがなくなり、バブルの崩壊で不景気にもなる。さらに95年には阪神・淡路大震災が発生して、社会に失業者や被災者といった多くの弱者が生まれます。市民主義やリベラリズムはそういった弱者を助けていく運動の中で成立していったわけですが、その源流はやはり、戦争に反対し、戦後民主主義を推し進めようとしてきた人びとの流れだと思います。
――個人的にはとても共感できる動きです。
ただ、ある人たちには、そういう新しい動きが目についたんでしょう。いまも気候変動やLGBT、フェミニズムといったものに対して「行き過ぎだ」と言う人がいっぱいいるじゃないですか。それと同じことが90年代にも起きていて、市民主義やリベラリズムという左派的な動きがすごくうっとうしい。そう感じる人たちが小林よしのりなどを中心に集結し、リベラリズムなどという「きれい事」を言っている連中が一つの権威になっていると主張するようになりました。
国家の横暴を批判したり、弱者の権利を擁護したりということ自体は正しいんだけれども、その言い方が断定的・絶対的なものになっていると反発したわけです。「これが正しいんだ」と先生のように押し付けてくるのが気に食わないと。その反発が後に、右派が融合する一つのきっかけになっていきます。
――高圧的な感じがしたわけですね。
時代が大きく変わっていく中で、市民主義やリベラリズムは「新しい正しさ」を打ち出した。それは必要なものであり、実際に正しいものだと思うんですね。ただ、その正しさに一元化されていくということに対し、違った正しさとか違った弱さを持った人たちが異議申し立てをしていく。かれらには、その正しさを主張している人たちがある種の権威に見えた。もともとは国家や市場といった権威に異議申し立てをする市民主義やリベラリズムなのに、それ自体が権威になってしまっているではないかと。
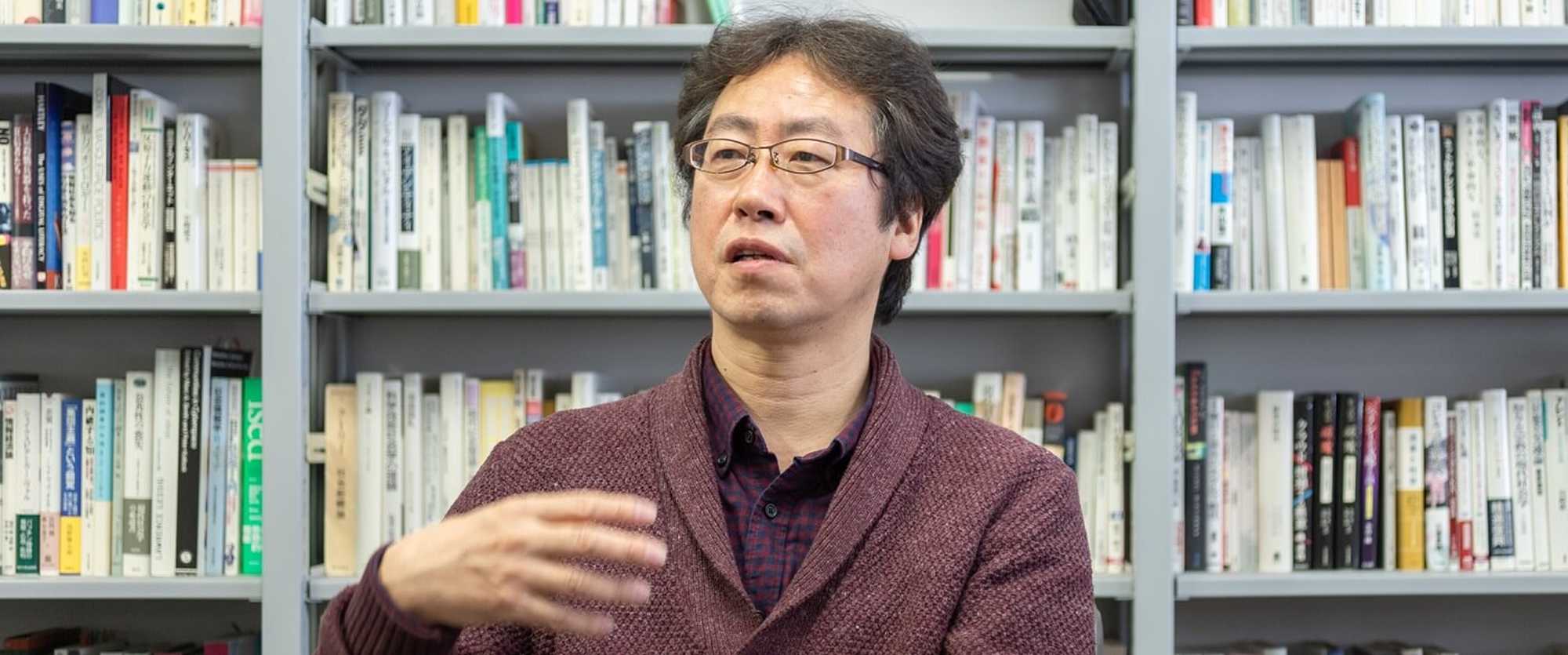
たとえば、バブル崩壊のあおりを受けて困窮している地方の中小企業の経営者といった人たちは、リベラリズムが助けようとしている弱者には入っていないわけです。彼らはもともと自民党の政策によって支援されていました。利益供与型の、いわゆる「バラマキ政策」というのはある種の福祉だった面があり、地方の農家や中小企業、自営業の人たちを助けていました。道路やダムを造るといったことも含め、ある意味では日本型のニューディール政策みたいなものだったんですよ。
つまり自民党の政策は暗黙裡に「福祉国家」としての役割を果たしていたともいえるんですけど、55年体制の終結や構造改革によってそれができなくなっていった。その一方、市民主義やリベラリズムにより、女性や戦争犠牲者、少数民族、外国人といったマイノリティーが新しい時代の弱者、助けられるべき人たちとして認定されていく。こうした「弱者認定」の構造の変化が90年代からゼロ年代にかけて起きてきたわけです。
――それで、これまで自民党の政策に助けられてきた人たちが「ちょっと待て」と。
その人たちからすると左派の言動は、自分たちをないがしろにする、すごく恣意的なものに見えたのではないでしょうか。市民主義やリベラリズムという「新しい正しさ」に対し、それだけでは困ると主張する人びとが出てきたわけです。
それと同時に、55年体制が終わり、国際関係にも新しさが求められる中で、93年には細川政権が先の戦争は侵略戦争であったと認めて謝罪をする。これも「新しい正しさ」ですよね。すると、これに対しても、自分たちがないがしろにされると思う人たちが出てきた。それは日本を戦争に引っ張ってきた人や、その思想を継ぐ人たち。彼らは日本を一方的に悪者扱いする「東京裁判史観」に異を唱え、政府の靖国神社参拝を実現するといった活動を展開していました。そういう人たちにとって、当時の政府の態度は許せないものだった。
それで、日本に戦争責任はない。あの戦争はやむを得ないものだったということを検証しようとする動きが出てきます。戦後の日本がずっと考えてきた「正しさ」が90年代に一層強くなった結果、それへの反発が生まれ、歴史をもう一度自分たちなりの見方でつくり直すんだという動きになっていく。
――「新しい正しさ」への反発から一方では「反リベラリズム」が、他方では「歴史修正主義」が生まれたわけですね。
「歴史修正主義」を担っていたのはもともと自民党右派、戦前のエスタブリッシュメントを系譜に持つ政治家を中心とするオーソドックスな勢力だったのに対し、「反リベラリズム」の方は、先生的な言い方が鼻につくという若者や、小林よしのりの読者を中心とするサブカルチャーの愛好者なので、ぜんぜん違った人たちなのですが、この両者がネットを媒介にして結び付くということが起きていくわけです。