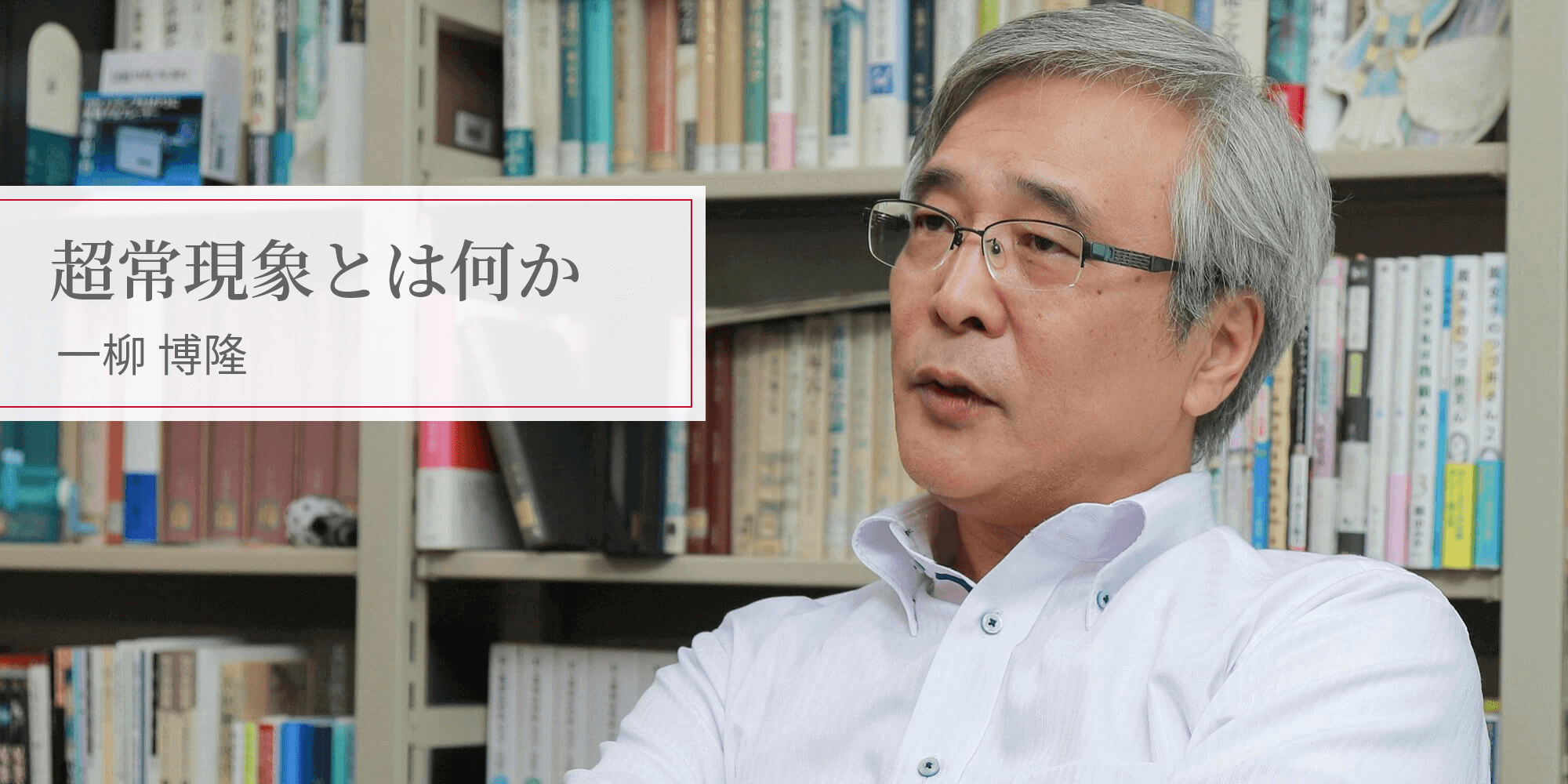――超常現象というと、個人的にはまず幽霊や妖怪が思い浮かぶのですが、この二つ、二人? というのは、どういう定義で分かれているんですか。
それはすばらしく学問的な問題です(笑)。江戸時代の妖怪カタログを見ると、河童や天狗なんかと一緒に、人間の生霊や死霊、怨霊も収録されています。つまり、妖怪と幽霊を区別していません。幽霊って、「お化け」とか「化け物」とも言いますよね。江戸時代の感覚では、「この世ならざる者」が姿を変えてこの世に現れたら、全部「お化け」だったと思われます。
ところが近代になって、民俗学を創始した柳田国男が、妖怪と神をセットで考えます。神の劣化した最終形態が妖怪だっていう仮説を立てる。
「八百万(やおよろず)の神」と言うように、日本には神様がいっぱいいるわけですけれど、柳田は、その神への信仰にも「はやりすたり」があったと考えます。天照大神(あまてらすおおみかみ)みたいに、権力に守られてきた神様は別ですが、民間の神様だと、あるときはすごく祀(まつ)られていたのに、いつのまにか忘れられていた、といったことが起こる。日本の神様って、キリスト教みたいな絶対神じゃないので、すごく人間臭いんですよ。つまり、祀られている間は人間にいいことをしてくれるんだけど、祀られなくなると祟(たた)るんです。
――気持ちはとてもよくわかりますね。
あそこに行くと何か変な感じがする、何か怖い。そういう場所には、かつて特定の神様をお祀りした神社や祠(ほこら)があった。でも誰もその神様を祀らなくなって廃れてしまうと、かつて神だったものが落ちぶれ果てた姿で現われる。それが妖怪だと柳田は考えた。かつて祀っていた神への畏怖や恐怖が、場所の記憶と結びついて妖怪になるというわけです。そうすると、人が死んだ後に変化した幽霊を妖怪と一緒には扱えない。それで柳田は、両者を切り分けました。
――妖怪と幽霊は別だと。
柳田によれば、妖怪は今お話したように場所に憑くけど、幽霊は恨み辛みで出るものだから、特定の人間に憑く。それから、出現する時間帯が違う。妖怪は薄明の時間帯、明け方と夕方に出るけど、幽霊は真夜中、丑三つ時に出るっていうんです。現代では成り立たないですけどね。じゃあ幽霊屋敷はどうなんだ、あれは特定の場所に出るわけだから妖怪なのか、とか、タクシーに乗り込んでくる幽霊の話は、特定の運転手さんに固執しているわけじゃないよね、といった具合に、例外だらけになってしまいます。
でも、柳田の立てた仮説は現代まで影響を与えていて、今でも妖怪と幽霊を分ける見方の方が多いと思います。妖怪はキャラ化されていく一方で、幽霊は怨霊的な部分、恐ろしさが強調されてますよね。
――妖怪は「もと神」で、幽霊は「もと人」だと。
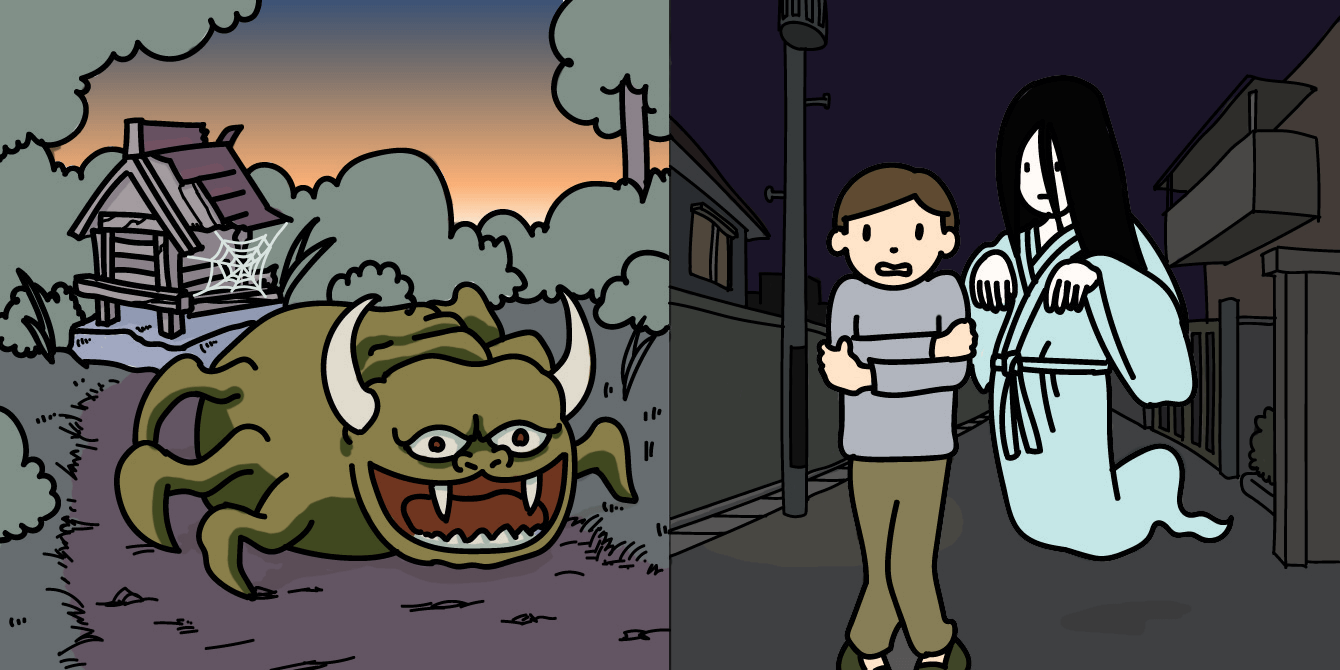
もちろん異説もいろいろあります。たとえば京極夏彦さんは、もともとは私たちが合理的に解釈できない現象や事件を「何々の仕業」という形で意味付けたのが妖怪ではないかと言ってます。
――子どもが忽然と姿を消すみたいな事件があったときに、その原因がわからなかったら、「妖怪の仕業だ」ということにして、なんとか「論理的」に理解しようとしたってことですね。
出来事、つまりコトがモノ=モノノケの仕業に変わる。このようにモノ化されたコトが妖怪である、と。
――なるほど。
他にも民俗学者の井之口章次さんは、妖怪という形で伝わってるものの6割はもともと人で、柳田が言うように元が神だったものは全体の3割程度に過ぎないと考えています。
――柳田国男の説を否定しているわけですね。
もとが人というのは、要するに無縁仏です。たとえば、「ヒダル神」という旅人に取りつく妖怪がいるんですけど、これに憑かれると全身の力が抜けて動けなくなる。そうなったときには、何でもいいから口の中に入れろと。何も持ってなかったら道端の草でもいい。草に手が届かなければ、手のひらに米と書いてなめろ。そうすれば落ちる、といった伝承があります。
これは、かつてそこで不慮の死を遂げた旅人がいて、近所の村人が埋葬してくれたものの、誰も供養してくれないし、もちろん、そこで死んだなんて連絡が自宅に届けられることもない。それで、無念の気持ちを抱いたままそこに佇んで、自分の死の様子を伝えるために人に取り憑くんだという説明ですね。供養されない霊魂が妖怪として語られるケースです。
また、これも京極さんの説ですが、お玉さんとか太郎左衛門さんといった特定の個人と結び付いて語られているうちは幽霊なんだけど、そういう固有名詞を構成する情報が消えてしまい、行動様式や意匠だけが残って、それに名前が付けられると、妖怪になる。
学校の怪談
――ちょっと前になりますけど、『学校の怪談』ってすごく流行りましたよね。
90年代の半ば以降ですね。
――そのときに世間の人だけじゃなく、民俗学の研究者たちもすごく驚いたっていう話をお聞きしたことがあります。まだこんなテーマがあったのかって。
民俗学は地方の山村や農村に行ってフィールドワークをする、というイメージだったのに、調査すべき対象が都会の、しかも学校にあるじゃないかってことですよね。常光徹さんが先駆者ですが、あれは大発見というか、すごく大きな事件だったと思います。ちょうどこの前「学校の怪談」の歴史を調べてたんですけど、その手の話は明治時代からあるんですよ。
――そうなんですか?
たとえば夏目漱石が赴任していた旧制松山中学校には、寄宿舎の一室に老女の霊が出るっていう話があったようです。ちょうどそこが、松山藩の処刑場の跡地だったから、というのですが、土地に眠っていた伝承が、近代になって学校が作られることで蘇るっていうのも不思議ですね。
――場所の記憶が呼び覚まされるってことですかね。
旧制第一高等学校にも怪談があるんですけど、これも舞台は寮です。昔の旧制高校は全寮制のところが多かったので、学生は大体寮で生活していたんですけど、ある部屋に「出る」と。
――それは、どなたが?
藤村操です。
――華厳の滝で身を投げた一高生ですね?
そうです。
――それは有名人が……。
で、これがまた後になると変な話になっていくんです。由緒ある学校であれば、怪談のひとつやふたつないわけがない。つまり、怪談がない学校は駄目なんだと。それで昭和の初期に旧制の姫路高等学校で、うちは歴史が新しいから怪談がない、じゃあ自分たちで作ろうということになって、柔道部の連中が毎晩トイレにこもり、個室のドアを中から押さえて、夜中になるとあのドアは開かないっていう噂を広めた。
あるとき、剣道部の連中が夜中に飲み会をやってるうちにトイレで何かあるらしいという話になり、部室にあった日本刀を持ってトイレに行った。そしたら本当に開かない。そんなわけないだろうと、酔っぱらった先輩が日本刀で突き刺したら「うわっ!」という声が聞こえ、中にいた柔道部員が血まみれで出てきて、そのまま死んでしまった。それからそのドアは本当に開かなくなったと。
――本当に怪談ができたわけですね。
おそらく全部、創作でしょうけど(笑)。
――それにしても、なんで学校なんでしょうか?
学校って、怪談の発生する条件がすごく整っているんですよ。第一にメリハリがある。昼間は子どもたちが集まってエネルギーが爆発するような賑やかさだけど、夜になると静まり返りますよね。光と影、明と暗のメリハリもあります。校舎の配置を見てみると、南側の日の当たる方にはいわゆるホームルームが並んでて、あまり日の当たらない北側には理科室や音楽室といった特別教室、トイレ、階段がある。学校の怪談って、大体はこの北側に多いですよね。

――たしかに。トイレ、理科室、音楽室は定番ですね。
次に、時間の問題があるかなと。一人ひとりの子どもたちは1年生、2年生、3年生と直線的に時間を過ごしていきますけど、学校そのものは毎年同じことやっていますよね。4月に入学式があって、遠足があって、夏休み、運動会、冬休みと、同じ行事を毎年繰り返している。だから、学校で起きた事件は毎年その行事、運動会なら運動会が来るたびに「何年前にこんなことがあって」と、語られやすい。
――私の通っていた学校でもありました。
あと、土地の問題もあります。1872(明治5)年に学制が、1879(明治12)年に教育令が制定されて、近代の学校制度が動きはじめます。全国の市町村に学校が作られていくんですけど、どこの地域だって、子どもの足で通えて、なおかつまとまった広さがある土地なんてそうそうありません。まさか田畑をつぶすわけにもいかないし。じゃあ、どうしていたのか。
学校の怪談のなかには「この学校はもともと墓地だった」という話がよくあります。そういうケースは、実際にあったと思うんです。無縁墓地を整理して、そこに学校を建てるという。そうすると、最初の妖怪の話と同じで、学校が土地の記憶と結び付いた形で語られるようになる、ということがあるんだと思います。
――「学校の怪談」は生まれるべくして生まれたわけですね。